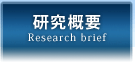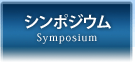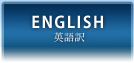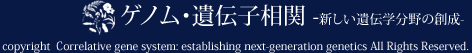文部科学省科学研究費補助金「新学術領域研究」
新学術領域|ゲノム・遺伝子相関
月別アーカイブ
計画研究班別アーカイブ
公募研究班別アーカイブ
旧公募研究班別アーカイブ
「研究経過報告」内を検索
【ROIS】岡班の記事を表示しています
総説が日本遺伝学会誌Genes & Genetic Systems (2014, vol.89)に掲載されました。
Regulatory divergence of X-linked genes and hybrid male sterility in mice
長浜バイオ大学にて開催されました日本遺伝学会第86回大会にて、九州大学の酒田祐佳さん(佐渡班)と「マウス遺伝学が牽引する最先端生命科学」と題しましてワークショップをオーガナイズしました。
マウスは、哺乳類を代表するモデル動物として近交系が数多く樹立され、遺伝学的研究が盛んに行われてきました。近年は、次世代シークエンサーを利用した大規模な情報解析やゲノム編集技術の応用により、生命現象のメカニズムに関する新たな知見が増大しています。ワークショップでは、特に生殖関連の分野でご活躍されている先生方をお呼びして、その最先端の話題を提供していただき、マウス遺伝学が果たす生命科学における役割について活発に議論する場となりました。
WS17-1 変異Xist RNAがつくるヘテロクロマチン様構造の詳細
酒田祐佳(九州大学)
WS17-2 ゲノムイメージングから迫るリプログラミング機構
宮成悠介(岡崎統合バイオサイエンスセンター)
WS17-3 遺伝子発現におけるシス調節領域の進化と生殖隔離
岡彩子(新領域融合研究センター)
WS17-4 マウスSox9遺伝子の生殖腺、軟骨エンハンサーの同定
高田修治(国立成育医療研究センター研究所)
WS17-5 多機能性幹細胞と生殖細胞を隔てるエピジェネティック障壁
松居靖久(東北大学 加齢医学研究所)
講演頂いた松居靖久先生、高田修治先生、宮成悠介先生、誠にありがとうございました。また本領域の佐渡敬先生にもたくさんのご助言を頂き、感謝いたします。
異なる生物集団の間では、交配しても子が生まれない、生まれても生存できない、交配自体を行わないといったことがありえます。たとえば、祖先が共通であっても「長い間、地理的に隔てられる」といった要因によって、子孫を残せなくなることが知られています。このような現象は「生殖隔離」とよばれ、動物や植物で広くみられます。生殖隔離は、新たな種を作り出すためにきわめて重要です。生殖隔離がなければ、一度分離した集団でも再び交配することで遺伝子が混ざり合い、種として成り立たないことになってしまいます。古くより、生殖隔離がおきるメカニズムとして、「ドブジャンスキー・ミュラー (Dobzhansky-Muller) モデル」が提唱されてきました。このモデルでは「分離した集団において、互いに作用する複数の遺伝子が独立に進化した後に交配すると、生まれた子(雑種個体)で、遺伝子の働きに不適合が生じるため」と説明されており、実際に、X 染色体上の遺伝子が不適合をおこしやすいことが知られています。ただし、その具体的な分子メカニズムについては、ほとんどわかっていませんでした。
今回、50〜100 万年前に共通祖先から分かれた2 亜種のマウスを対象にした実験を行うことで、謎だった分子メカニズムの解明に向けて一歩前進することが出来ました。生殖能力の低下が観察されるX 染色体のみが別亜種から由来する雄のマウスの全ゲノムについて遺伝子の発現解析を行い、X 染色体上の遺伝子に発現異常が生じていることを突き止めました。この発現異常は、転写調節機構における、転写調節因子などのトランス因子とシス調節領域の亜種間多型が原因であると考えられました。興味深いことに、X染色体上の発現低下していた遺伝子の多くが生殖関連遺伝子であり、トランス因子とシス調節領域の間に起きた遺伝的不適合genetic incompatibilityが原因であることが示されました。このことは、生殖関連遺伝子で、転写調節機構におけるシス・トランス因子がそれぞれの亜種の中で速いスピードで共進化した結果と考えられます。トランス因子とシス調節領域の間の遺伝的不適合は、雑種の細胞環境において普遍的におこっている可能性があり、生殖隔離に伴う様々な表現型を説明できるかもしれません。
この成果は、新領域融合研究センター、国立遺伝学研究所の哺乳動物遺伝研究室、国立統計数理研究所との共同研究によるものです。
Ayako Oka, Toyoyuki Takada, Hironori
Fujisawa, Toshihiko Shiroishi
Evolutionarily Diverged Regulation of X-chromosomal Genes as a Primal Event in Mouse Reproductive Isolation.
PLoS
Genetics e1004301
2013年9月21日(土)に慶応大学日吉キャンパスで開催された日本遺伝学会第85回大会にて、本領域との共催ワークショップ「異なるゲノム間の軋轢と強調 〜相互作用のゲノミクス〜」を開催し、領域内の寺内、松田、岡がそれぞれの研究対象とするゲノム間の相互作用についての講演を行いました。また、北大の久保友彦先生に、ミトコンドリアと核のコンフリクトのお話をしていただきました。改めて、「病原菌と宿主」、「雌雄」、「亜種間」、「ミトコンドリアと核」など、植物動物の様々なレベルでのゲノム間相互作用を見ていくと興味深い現象が数多く見えてくること、また遺伝子重複やエピジェネティクスを含む転写調節機構の進化など共通性のある要素が存在することが浮き彫りとなりました。学会最終日の午後でしたが、50名を超える来聴者を迎えて有意義なワークショップを行うことができました。また、本大会では本領域の田中、北野による共催シンポジウムも開催され大変盛況でした。
大阪教育大学 鈴木剛
首都大学東京 高橋文
2013年9月19日から21日に東京工業大学で開かれる日本遺伝学会85回大会にて、日本遺伝学会と新学術領域「ゲノム・遺伝子相関」との共催でワークショップ「異なるゲノム間の軋轢と協調 ~相互作用のゲノミクス~」を開催します (http://gsj3.jp/taikai/85taikai/index.html)。 9月21日(土)13:30~15:15
9月21日(土)13:30~15:15
「異なるゲノム間の軋轢と協調 ~相互作用のゲノミクス~」
世話人:鈴木 剛 (大阪教育大学)、高橋 文 (首都大学東京)
13:30 WS10 はじめに ○鈴木 剛(大阪教育大学)
13:35 WS10-1 花粉形成をめぐって生ずるミトコンドリアとのコンフリクトを、核はどうやって解消するか:テンサイ(サトウダイコン)の事例
○久保 友彦(北海道大学大学院農学研究院)
13:59 WS10-2 マウス亜種間ゲノム多型による転写調節のゆらぎと生殖隔離
○岡 彩子1、城石 俊彦2(1)情報・システム研究機構 新領域融合研究センター、2)情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所)
14:23 WS10-3 植物-病原菌相互作用の集団ゲノム解析
○寺内 良平((公財)岩手生物工学研究センター 生命科学研究部)
14:47 WS10-4 異種ゲノムの不適合性が引き起こす雑種の不妊・発育不全現象の遺伝的制御機構
○松田 洋一(名古屋大学大学院生命農学研究科動物遺伝制御学研究分野)
15:11 WS10 討論 ○高橋 文(首都大学東京)
一部、講演の順序が変更されるかもしれませんので、ご注意頂ければと思います。
直前のお知らせとなりましたが、学会に参加される方、会場でお会いできればと思います。
すずき・たかはし
- 1
- 2