種をまいて約40日(経:小松香於里)
2019年12月 4日 (水)
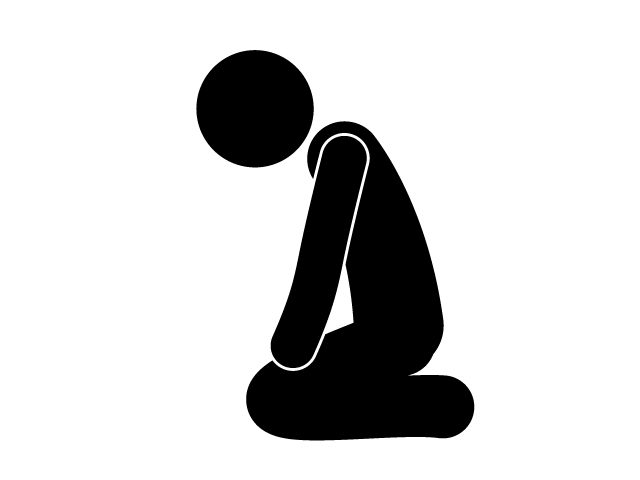
本当に2020年ってやってくるんですね。オリンピックの招致が決定したのが2013年。
私はまだ中学生で、あれから7年たったのだと思うと不思議です。
社員さんから、小学生までは日々のすべてが新鮮だから1年が長く感じられるけど、
同じような日々の繰り返しになってくると1年は短く感じられるようになると思う。
というお話を聞きました。
2020は盛りだくさんの長い1年にできたらいいなと思います。
一応順調に育っています。10/23に種をまきました。
これは水分不足か、はたまた寒さが原因なのでしょうか。
日光の向きに伸びているため、鉢の向きを定期的に変えれば、まっすぐに伸びてくれるのかなと思いました。
植物の発育を止めないために施すため、効果がすぐに現れない肥料を使う。過剰に施してしまうと、植物の根を傷めて枯れさせてしまう可能性がある。
油かす、米ぬか、草木灰、腐葉土、魚粉、骨粉、堆肥などがよく用いられる。
追肥・・・植物の生育の過程に合わせ、必要な栄養を補うために追加で施す肥料。すぐに効果が現れる化成肥料や速効性の液体肥料を一般的に利用。
今回頂いた肥料はどのような成分なのか気になりますね。
しかし調べてみると、栄養素がたくさんあるゆえの弊害が多いようです。
虫がわいたり、土が硬くなったりするなどです。
https://makotti.com/archives/3450.html
寒さが厳しくなるので寒さ対策も考え始めなくてはと思います。
また帰省するのでその間のお世話についても考えます。
コメント
経済学部・小松さん
育種の渡辺でございます。今回の記事についての細かなコメントは、ラボスタッフのオガタくんからコメントが書かれると思いますので、そちらを参照して下さい。別件で大事なこと。1つ前の中間発表の記事にタイトルがないと言うことを、その記事へのコメントで書いてあると思います。この記事を投稿するシステム上の問題で、タイトルがないと、それ以降の記事が集計されないという形になっています。現在は、特殊な方法を使って表示されるようにしていますが、中間発表へのコメントの通り、中間発表のやり方について記載した渡辺の記事に従い、「タイトル」をつけて下さい。これは必須です。
わたなべしるす
さて続けてコメント致します。
誰にも時間は過ぎるものです。とはいえ、大学一年生ではまだまだまだまだ新鮮なことが多くあり、楽しいでしょう。時間が短く感じられたというのは実は幸せなのかもしれません。かなり辛いことが続けば逆に長く感じられたと思います。
東北大は確かに刺激は少ないかもしれませんが、国立大学中トップレベルの穏やかさと伸びやかさを持っています。これは他と比べてはじめて分かることです。もっとクソ大が多くある中で東北大をわざわざ選ばれたことは幸せですよ。
さてミニダイコン、あの播種から成長してきました。やはり時期的な遅れのため小さいのですが適切に管理していきましょう。今の時期からは3日に1度の水やりでは多いかな、と思います。もう一本くらい間引きしてもいいですね。上からの写真しかないのではっきり分からないのですが、もっと増し土をしてもいいと思います。鉢縁からはゆとりがありそうですから。傾くのは根元がしっかりしていないからで、鉢の向きを変えることはそんなに意味がありません。むしろ植物は位置の移動を嫌いますからそのままでいいかと思います。
肥料についてはよく調べました。
全くその通りです。米とぎ汁についての記載もそうですね。ただし悪いことばかりではありません。
元肥と追肥はだいたい半々にやるものです。元肥はもちろん一度まとめるものですから、長くゆっくり効かないといけません。その意味で微生物によって分解されてはじめて植物に利用される有機質肥料が使われます。追肥は逆に即座に吸収されるタイプの化学肥料ですね。
ただし現在は化学肥料でも、コーティングなどでゆっくり効くタイプも出回っています。コストの関係で畑に使う物ではありませんが園芸用品ではそういう化学肥料も売られています。
さて、これは最新の話題です。
生物はその個体の中で、情報をもの凄く複雑にやり取りしていることが分かってきました。更に、食物採取を通じて外界から栄養だけではなく、情報を取り入れています。植物も有機質肥料などから養分だけでなくて、情報を入手して変化しているのかもしれません。
ではまた、報告お待ちします。
ラボスタッフ・オガタ



