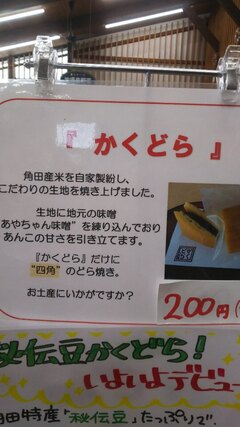11.「オイディプス王」(文:小松澤亮晴)
2020年12月 4日 (金)

1.挨拶
こんにちは、小松澤です。今回はギリシア三大悲劇、その中でも屈指の名作といわれる、ソフォクレスの「オイディプス王」を紹介します。オイディプスは、彼自身よりもその伝説中の怪物であるスフィンクスの方が圧倒的に有名でしょう。「朝は四本足、昼は二本足、夜は三本足」という謎も有名です。当然答えは「人間」です。そしてこれを解いたのがオイディプスです。しかし悲劇はここからです。なぜ、謎の答えが「人間」だったのでしょう。それは、アポロンの神託である「汝自身を知れ」ということです。この作品もアポロンの神託(「汝自身を知れ」とは別)を中心にして展開されます。汝自身を知ったオイディプスはどうなったのでしょうか。彼は、自身が過去に知らずのまま父を殺し、その妻、つまり母と結婚し、子を授かっていたということを知ってしまうのです。そして自身の両眼をメッタ刺しにし、破滅する、という悲劇を迎えることになります。しかしこれは抽象して考えるべきであり、人間はすべて、実は直視できないような存在であるかもしれません。学問はすべて、人間を理解するためのものです。自己言及のパラドクスにより、我々は他者を通して、例えば星(工学や天文学では「無限遠」、すなわち絶対に到達できない、世界外に位置するとされています。二つの望遠鏡は平行につけられます)を通して、人間を理解します。しかしその究極において、我々はともすれば自身の眼をつぶさなければならない事態に直面するかもしれないのです。
~目次~
1.挨拶
2.経過観察
3.結び
2.経過観察
では、今回はベビーリーフを少し中心にして見ていきたいと思います。まずは小松菜と芭蕉菜です。ちょうど50日目です。
以前は、水やりの時に、倒れてしまわないようにちょびちょび水を与えていたのですが、もうしっかり根が張ったようでそんな心配はいらなくなりました。気になったところは、葉っぱの表面に黒いつぶつぶがあったことです。土のようでしたが、なんで急に葉っぱについたのでしょうか。もしこれが実は虫の卵(ほかの受講生のところでは発生しているみたいですね)だったら本当に最悪です。
では、ベビーリーフの2回目の収穫です。50日目です。
2回目の収穫では、赤い葉の割合が減って、他の葉っぱの割合が増えたかんじでした(赤い葉の数が減ったというわけではないです)。しかし、茎がすごくがっちりしていて、「ベビーリーフ」という名前がだんだんふさわしくなくなってきました(笑)。
3.結び
以上になります。今回は2回目のベビーリーフの収穫でしたが、次の三回目が、おそらく記事に載せられる最後の収穫になるかと思います。そしてたぶん次の次の記事くらいで小松菜と芭蕉菜の収穫ができるかと思います。では、第11回の記事でした。
コメント
小松澤さんこんにちは
オイディプス王......
先ずはこういうものを読まれたということが驚きですね。今の学生さんも捨てたものではないと認識させられます。決して多いとも思えないのですが、真摯に古典を読む学生さんもいるんですね。加えてその読み込みの深さ...... アポロンの神託が人間には厳し過ぎるものであり、自己直視が実は耐えられないことであると。オイディプス王の動きから抽象化してそこまで感じ取りましたか。加えて、人間は他を通してしか自己を知り得ないとか。
なんとも凄いですね。この展開ゼミが思わぬ深みを持ちました。
さて、私からも一つなんですが、もしも将来言語学方向に行かれることがあればやってほしいことがあります。それは日本語の処理速度ということです。ご存じかどうか、日本語の音素数は他言語に比べて極度に少ないものです。母音が5つというのは、世界的にそんなにおかしくない(主な言語は母音が5~7が普通、中には英語や仏語のようにめちゃくちゃ多いものもあるが)のですが、子音もまた少ないのです。そこに加えて、日本語はシラブル言語といって、アクセントがピッチアクセントのみであり、音節が決して弱勢で消えることも、逆に長くなることもありません。とどめに各音節は1母音1子音で固定され、他言語のようにいくつもの子音が入ってくることはありません。
つまり日本語は音節一つ一つが極度に単純化され、かつ情報量が少ないという特異な言語です。それが非常に早いリズムで繋げられています。よく日本語が機関銃のようだと言われるのはそれゆえです。
さあそんな日本語の情報処理はどうでしょうか。ソシュール言語学を学べば、「言語間に優劣はない」というのが基本ですが......
ここで工学的な話ですが、コンピューターの演算装置の種類でRISC(縮小命令セットコンピューター)というのがあります。それは少数のよく使われる命令だけを、しかも一定長さに整えてから処理するというものです。その詳しい歴史は省略しますが、今のコンピューターはみんなその方向に向かっています。対義語であるCISC(複雑命令セットコンピューター)はもう純粋には存在しません。コンピューターの世界でははっきりと優劣が出るもので、RISCの計算速度の優位性は明らかですから。
ここで日本語の構造を見ると、他言語と違って見事にRISCではないでしょうか! もちろん日本語の特性や比較は私が知るよりはるか多くが研究され、膨大な知識の積み重ねがあるでしょう。しかしながらRISCとの比較はそう無いと思います。これは言語学と工学のどちらも知らなければできないことですから。そしてRISCを当てはめたら、そのパイプライン構造やアウトオブオーダーといった計算機理論を日本語学に持ってきて、独自解釈ができるのではないでしょうか。そんなことを文系の誰かにやってほしいですね!
まあ余談はさておいて植物の話に行きます。
先ずはコマツナとバショウナですね。以前のような頻繁な萎れは改善したでしょうか。丈夫になってきたので一気に水をやっているとのことですが、それはいいことですね。
黒い粒は害虫の恐れがありますね。ここから順次観察し、害虫を見つけるというより葉に食害の跡があるかどうか見て下さい。害虫の方は案外と賢く、隠れていることがあります。
もう一つ、写真では色味が分かりにくいのですが、少なくとも同じ鉢の中に「葉の濃淡」が見えるのではないでしょうか。色の薄い葉があるっぽいですね。つまりそういうものがあるのは肥料不足の状態です。植物は重要な部分(比較的新しい葉や芽)に肥料分を送り、重要でないところはむしろ分解して送り出してしまうという特性があります。そこで追肥をやや多め(一ヵ所当り20粒から30粒にするとか)にして一定期間ごとに与えて下さい。
ベビーリーフの収穫が続いているのも凄いですね。本来なら30日ほどで終わるベビーリーフを間引き収穫でここまで続けています。まあ、栽培期間が長くなれば茎も幼若ではないのでしっかりしてきます。食味とのバランスを考えながら栽培して下さい。まだあともう一回収穫予定なんですね。
コマツナとバショウナの収穫はまだ遠いことのように感じます。定規での計測がないのですが、市販のコマツナはもっと大きいですね。鉢が小さいので限界があることと(市販品のようにはなれない)、害虫のことがあるのでそれもまた考えるべき課題になります。
ではまた、記事お待ちしています。
ラボスタッフ・オガタ