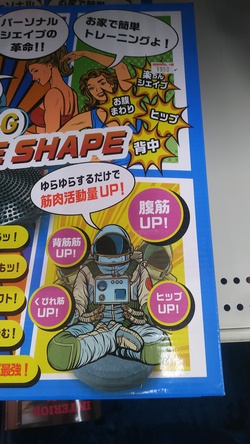ひまじのカブ栽培日誌 第3回~急成長~(工:田中大翔)
2023年10月26日 (木)

こんにちは、ひまじです。今回はまず写真の話から、今回はまたサークルで今度は福島へキャンプに行ってきました。これはあぶくま洞という鍾乳洞の写真です。福島中を回り様々なところへ行きましたが、さすがにすべて書いていてはそれだけでブログが終わるのでいくつかに絞ります。
まずあぶくま洞ですが写真の通り大きく、しかも道がしっかり整備されていたので非常に良かったです。つぎに、この寒い時期にキャンプ場でサップ、カヤックを体験したのですが、意外と水は暖かく、寒い思いはせずに済みました。初めてでしたが落ちなくてよかったです。(友達は落ちてました笑)他には会津の鶴ヶ城や福島原発も見に行きました。福島原発はまだ近くで見ることはできず、車で通りすぎるだけでしたが......。 アニメや二次小説の話もしたいのですが、そろそろ書きすぎなので次回に回して本題に移りましょう。
アニメや二次小説の話もしたいのですが、そろそろ書きすぎなので次回に回して本題に移りましょう。
栽培記録
さて、本題に入ります。前回は小さな鉢植えに8つという過密状態だった株を半分別の鉢に移し、屋内で育てることにました。今回はその後の様子です。これから外で最初からそだてている鉢を外鉢、屋内で育てている鉢を内鉢と呼ぶことにします。
まず、内鉢の生育環境ですが、窓とカーテンの間に鉢を置き、できるだけ日光を受けられるようにしています。部屋の気温は移してから現在までで最低16.4度、最高22.6度なので最低一桁、最高25度行く外よりはるかに安定した気温となっています。部屋は南向きで正面に狭い道路があるため、日光は内外どちらにも十分当たります。正確に計測したわけではありませんが外鉢には直射日光が6時間、内鉢にも5時間は当たります(窓一枚挟むが)。
これが間引きをした次の日、11日目の外鉢の写真です。間引き後も問題なく、逆にのびのびと大きくなっている印象を受けます。測ってないので何とも言えませんが、一日で急に大きくなったような......。あとは子葉の間から本葉が生えてきました。内鉢は変化はありませんでした。 13日目になりました。右が外鉢、左が内鉢です。ここで内鉢の間引き時に根が切れてしまった株が倒れてしまっていました。外はさらに元気に成長しています。この日までだと内鉢は成長が遅く、外鉢の成長の方が早い印象です。やはりガラス一枚分の日光が影響しているのでしょうか。
13日目になりました。右が外鉢、左が内鉢です。ここで内鉢の間引き時に根が切れてしまった株が倒れてしまっていました。外はさらに元気に成長しています。この日までだと内鉢は成長が遅く、外鉢の成長の方が早い印象です。やはりガラス一枚分の日光が影響しているのでしょうか。
14日目になりました。ここで大きな成長が見て取れます。外鉢はたった一日で見てわかるぐらい本葉が大きくなりました。また、内鉢は枯れるかと思った株がなんと復活‼。生命力を感じました。上が外鉢、下が内鉢です。
 ...かと思った17日目。やっぱりだめでした。これはもう無理でしょうね......。ここでコメントのアドバイス通り外鉢の土を減らしました。また、更に外鉢と内鉢の成長の差が開いたので晴れの日には内鉢は日中外に出すことにしました。コメントで知りましたがいくつか作れるのですね。ちょっと大変ですが、株を少しずらす作業を次の間引きのときやろうと思います。最終的には3つにする予定です。
...かと思った17日目。やっぱりだめでした。これはもう無理でしょうね......。ここでコメントのアドバイス通り外鉢の土を減らしました。また、更に外鉢と内鉢の成長の差が開いたので晴れの日には内鉢は日中外に出すことにしました。コメントで知りましたがいくつか作れるのですね。ちょっと大変ですが、株を少しずらす作業を次の間引きのときやろうと思います。最終的には3つにする予定です。 上が内鉢、下が外鉢です。外鉢は3枚目の本葉が出てきました。
上が内鉢、下が外鉢です。外鉢は3枚目の本葉が出てきました。
毎回1000文字ちょっとを心がけているのですがついつい書きすぎそうになってしまいます。私の場合このブログの更新は今のところ全く苦ではなく、むしろ楽しいのでこの調子で頑張っていきたいです。(勧められた二次小説はまだ読めてません......。)
コメント
ひまじさんこんにちは
先ずは鍾乳洞の話、あぶくま洞は車でないと行きにくいのですが、行くとなかなかの規模に驚きます。書かれている通りしっかり整備もされていて歩きやすく、出口には店もあります。あぶくま洞と似た感じの鍾乳洞は秋芳洞でしょうか。それもまた整備が行き届いています。し、しかーし! 私が最もお勧めする鍾乳洞は岩手県岩泉町にある龍泉洞です! 鉄道で行きやすい場所にあり、そして入ってみると程よい探検感があります。加えて、何といっても地底湖が美しい!
この時期福島旅行はいいですね。というか福島自体に見どころがたくさんあります。私は福島に移住したいくらい好きですね。福島県人の人柄も良い(演劇やコンサートに行くとよく分かるのですが、福島は仙台より明らかにマナーがいい)ですから。
さて本題の植物栽培についてですが、驚きの栽培条件ですね! 今までの受講生で、こんなに日照の良い条件で栽培できた人がいるでしょうか。外で直射日光一日6時間はもう充分です。この展開ゼミでは、常に日照不足で悩まされ、徒長に対処するのが精一杯であるパターンが普通でしたから。それなのにここで日照の不安が無いとしたら成功は約束されたようなものです。逆にこれで失敗したら驚いてしまいます。
成長記録を見ると順調のようです。コメントを付けるとすると、外鉢で本葉が展開したら間引くのは早めですね。二株程度で生育させていき、カブの根部の肥大が始まる時期あたりに(この密集具合では根の肥大でお互い邪魔し合う)一株にするのがいいかと思います。その時に葉の食レポができるかもしれません。
内鉢の株について、「ずらす」とは...... どんな作業か分からないのですが、もしも根を引っ張るような意味ならば絶対的にNGです。正直内鉢に移動させた段階で根に大きな傷がついています。これ以上のダメージを与えられたら、葉はそこそこ成長できても根の肥大は期待できません。もしもこれから株の間の距離を空けるのなら、「根全部とその周辺の土を丸ごと鉢の縁に寄せる」、つまり「株の間の土に、定規か何かを深く差し込み、土ごと真横に動かし、空いた穴には土を入れて埋めておく」イメージになります。土には柔軟性がありますので圧縮したらその分動きます。ただしこれは高度な作業なのでお勧めしません。
実際のカブやダイコンの農家は、畑の土に細心の注意を払い、どんな小石でも除きます。あるいは石どころか堆肥の塊りですら(通常の野菜栽培なら問題にしないような塊りでも)見逃しません。それほど根の生育を順調に保つことに腐心し、結果的に真っすぐのダイコンや真ん丸のカブを収穫できるようになるのです。
内鉢と外鉢の生育の違いですが、これは主に移植したためかと思います。元々生育環境的にいくつも条件が違いますから、はっきりしたことは言えません。普通ならば室内の光環境の話になるのですが、前述の通り、室内でもその光量があれば大丈夫ですから。それにはもう一つ根拠があり、「葉の色がどちらもあまり変わらない」のです。葉の色というものは主に窒素肥料の程度と光環境で変わります。肥料の点ではどちらも鉢も同じ土で、元肥はまだ充分残っています。とすれば光環境がどちらも良いので色が同じなんでしょう。もちろん、長期で見れば内鉢の方が緑が薄くなるかと予想します。
さてここで見逃せない記述が出てきました。内鉢を日中外に置く......敢えて実験的意義を諦め、生育重視にするんですね。それはそれでいいのかもしれません。
だがしかし、「内鉢を夜間室内に置く」、これはもはや「考えられる限り最悪の選択」になります。毎年不思議に思うのですが、受講生のなかで一定数こういうパターンをする人が出てきます。なぜでしょうか。植物栽培の常識からすれば、「温帯性植物は耐寒性があり、夜間の低温はあまり気にしないでいい」、そして「置き場は動かさない」のが不文律です。なぜなら植物は昼間に光合成を行い、夜間はもちろんできません。しかし「呼吸」は休むことなく常に行っています。ここで夜間の温度が高いと呼吸が無駄に盛んになり、せっかく貯えた光合成産物を消耗してしまいます。夜間に低温の方がむしろ正しいことです。
福島なんかの盆地で野菜や果物、米も美味しいのは夜間に低温だからです。他の盆地(山梨など)でもその通り、果物栽培が盛んです(例外的に岡山あたりでも果物栽培が盛んですが、これは夏にかけて雨量が少ないためです)。
人間に無理やり例えると、毎日「昼間のあいだ札幌で凍え、夜の寝る時間になれば那覇へ移動させられ、熱帯夜を味わう」といったクソ生活になるでしょうか。とにかく鉢の移動は避けて下さい。おいおい、機会を見て「温帯性植物と熱帯性植物の違い」や「温室というものの役割」なんかを書いていこうと思っています。
さて最後に文字数ですが、これは簡単に1000文字を越えますね。というかこの展開ゼミ、数日で嫌でも情報量が貯まってしまうものです。
どうでもいいことですがハーメルンやなろうでは一話4000字くらいの作品が好まれるものですが、アルファポリスでは何と800字くらいで毎日淡々と更新する作品も多くあります。私は短くて毎日更新の作品が好きですね。ちっともストーリーが進まない(特に私の好きな悪役令嬢系作品は女流作家が多く、そのためか文の大半が内面語りになっていたりする)のも味なものです。
次回の更新もお待ちします!
ラボスタッフ・オガタ