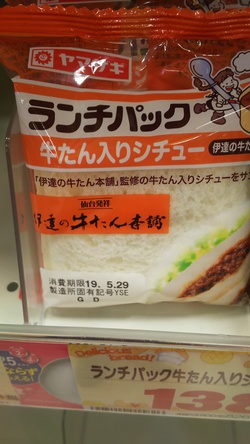ほうれん草を作ろう その5(間引き)(工:柳澤暢孝)
2023年11月 3日 (金)

こんばんは。柳澤です。
大学祭に合わせて東京から母親が、また、静岡から祖母も一緒に来てくれました。祖母は車いすでしたが、はるばる仙台まで来てくれて嬉しかったです。
月曜日には僕のアパートにも来てくれました。帰りの新幹線の指定席をとっていたので1時間ほどしか居られないようでしたが、お盆ぶりに(もう3か月前...)たくさん喋ることができて楽しかったです。
↑鉄道研究会で展示したプラレールです 手前側の車両は僕が作りました
ほうれん草ですが、まずは1週間の成長の様子を見てみます。
【栽培30日目:10/28(土)】
[最高20.5℃/最低10.6℃]
気温は日本気象協会のホームページより

【栽培31日目:10/29(日)】
[最高19.5℃/最低13.9℃]
【栽培32日目:10/30(月)】
[最高19.6℃/最低11.4℃]
【栽培33日目:10/31(火)】
[最高20.7℃/最低9.2℃]
【栽培34日目:11/1(水)】
[最高23.6℃/最低11.4℃]
数日ぶりに水やりをしました。(夜に撮ったのでブレてます...)

【栽培35日目:11/2(木)】
[最高22.8℃/最低12.1℃]

【栽培36日目:11/3(金)】
[最高24.4℃/最低11.4℃]
天気を見て今更感じたのですが、ここ数日は最高気温が20度台なのですね。僕は20度を超えると着る服が半袖になる(気がしている)ので、11月に半袖...と考えれば、確かに相当暖かいかもしれません。ほうれん草も成長しており、5、6枚目の葉を見せている苗も3個ほどあります。
ここ数日の写真を見ると、だんだんと鉢の中が混みあっていることがわかります。定規をあてられるほどの隙間も無かったので、今週は定規付きの写真はありません。水曜日当たりから、重なり合って倒れはじめている苗もあります。あまり元気ではなさそうです。
また、体感にはなってしまいますが、太陽の光が全体に当たっていなくなっている気がしていました。実際に、上から見下ろすと、葉が重なっている部分が何個かあります。
現在のほうれん草は徒長気味です。とは言うものの、今まで徒長について正直よく分かっていませんでした。「通常より茎が長く」なり、枯れやすくなったり、上手く育てられなくなるようなのですが、通常のほうれん草を育てたことが無いので、先生からコメントをいただくまで感覚が無かったのです。
昔のブログの記事(ここ や ここ)やいろいろなWebサイトによると、
①日光不足
②水分不足
④栄養過多
が原因で、なってしまうようです。後述しますが、①②は心当たりがあります...。
そのことも考えて、今日(11/3)に間引きと植え替えを行いました。学祭後はずっと授業と課題をしていたこと、植え替え先となる牛乳パックの中身を飲み干すのが遅れたことが重なって金曜日までかかったのですが、文化の日にのんびり植え替えできたのはむしろ良かったのかもしれません。
そうえいば、植え替え先として、峠の釜めしの容器も考えていました。材質が硬く、手持ちの電動ドリルでは全く穴が開かなかったため、今回は使わないことにします。面白そうだったんだけどなぁ...
植え替えをする前に、牛乳パックで新しい鉢を作ります。苗を複数移すことを考えて、横向きにしました。

面を切ってテープやホチキスで留め、側面に穴を十数個開ければ完成です。

牛乳パックに土を入れて、苗を4つ移しました。間隔は5cmとしました。また、今までの鉢に残った苗も、少し場所を動かして間隔を今までの2cmより広く、4-5cmに取りました。土も増やし、土寄せをしました。
移し替えるとき、根が入った土の塊ごと鉢から取ることを意識しました。それでも、少し苗に触ってしまい、
茎や葉が折れてしまったものもあります。これらの苗も引き続き育てますが、うまく成長できないかもしれません。どうなるのでしょうか。
もう一つ心配なのが、日光の当たり具合です。
 僕の住む部屋は、南向きにベランダがあるアパートの1階にあります。今週になって気付いたのですが、日が短くなったからか、昼間10-12時台でも、ベランダの床までは直射日光が当たっていません。今まではもっと日が長かったので、そこまで徒長にならず成長できたのかもしれません。ただ、まだ冬至にもなっておらず、これからもベランダの底に置くのは厳しそうです。
僕の住む部屋は、南向きにベランダがあるアパートの1階にあります。今週になって気付いたのですが、日が短くなったからか、昼間10-12時台でも、ベランダの床までは直射日光が当たっていません。今まではもっと日が長かったので、そこまで徒長にならず成長できたのかもしれません。ただ、まだ冬至にもなっておらず、これからもベランダの底に置くのは厳しそうです。
一応、ベランダの壁の上に置く、という選択肢もありました。しかし、僕の家から少し離れたところではありますが、電灯があるので、そこに置くと苗が夜も照らされてしまいます。夜を暗くした方が良いと思って、今までベランダの下に置いていたのです。


一応今週の中盤には、鉢を置く台を作ってもみました。しかし、手持ちの木材では高さが足りず、直射日光は当たりませんでした。ただ、窓から反射している光が若干当たるようになっているので、無いよりはましと考えましょう。これについては、もう少し高さをあげられるよう考えます。

今回鉢が増えたので、新しい牛乳パックの鉢を、試しにベランダの上に置いてみることにします。これによって、日中は直射日光をたっぷり浴びられるでしょう。ただ、このままでは電灯の光も浴びてしまうので、その対策として、帰宅後は上に段ボールの箱をかぶせることを考えています。上手くいかないかもしれませんが、これも無いよりはいいでしょう。
まとめると、徒長対策として、この1週間では
①鉢を台に乗せて光が当たるようにする
②一部の苗を植え替えて、苗同士の感覚を増やす
③水やりを減らす(今週の水やりは水曜日と金曜日のみ)
④もとあった鉢には土寄せをして、土がかぶさる部分を増やす
⑤新しい牛乳パックの鉢は、直射日光が当たるベランダの上に置く
ことをしました。
来週は、さらに元気なほうれん草になっていることを祈りたいです。
今週は以上です。
コメント
柳澤さんこんにちは
学祭での展示、「見る人は分かる」という感じでしょうか。いかに手をかけたか、情熱が伝わると思います。
そしてわざわざ静岡から...... まあ気持ちは分かります。孫の晴れ姿(?)は見たいでしょう。それにしても東海道新幹線と東北新幹線はなぜつながらないのでしょうか。制御系が違うのか、単に会社的なことなのか、あるいは政治的なことなのか、誰かに教えてほしいものです。
さて話は本題ですが、ホウレンソウの成長は悪くないですね。仰る通り徒長気味ではありますが、極端なほどではなく、生育できています。光条件がもう無理なほど悪いということはないのでしょう。
一般的には、徒長についていえば現象的に「茎が細長く」「柔らかく」、結果的に「倒れ気味」になることであり、付随して「緑が薄く」なります。これは栽培上困ったことになります。そうなる原因は記事に列挙してある通りです。個人的に列挙はあまりしてほしくないことです(例えば「この腫れは炎症かもしれずその場合外傷もありえるが感染の可能性もあり、ただし腫瘍性病変の疑いもある」と言う医者が信用できるかという話)が、まあ理解を深めるためこの場合はいいでしょう。
そして2番目の項目で「水分不足」は「水分過多」の間違いですね。現実的にはこの場合水分過多というほどでもありません。確かに土の表面が乾いている写真はないのですが、毎日毎日水をやっているわけではなさそうですし、お渡しした土は水はけに充分考慮した特製ブレンド土ですので。
結論からいえばやや日照が足りないのですね。ベランダの底部には、今後、直射日光が行かない感じがします(日の長さというよりも、太陽の入射角度が浅くなってくるため)。
そこで、解決策として何と手作り台の製作とは!!
これは素晴らしい! もう手作業のプロですね。その台はもはや椅子、かなり丈夫そうです。高さもいいくらいではないでしょうか(手持ちの木材っていう表現が......既に一般人ではない)。実のところホウレンソウは日射量と収穫量が比例するくらい日光好きではあるんですが、逆に日陰でもそんなに枯れはしない、丈夫な作物です。
ああ、そういえば台の設置にはもう一つ効用があります。コンクリート表面は冬場に非常に冷たくなり、鉢を直接置くと冷気が伝わり、昼間にも根の活動できる温度以下になってしまいがちなので、その意味でもいいことです。
そして今やるべきことは、株が風でフラフラするため、根が安定しないという徒長の弊害を無くすることです。これについて過去の受講生は添え木という方法をとった人もいますが、まだこの大きさでは無理でしょう。素直に土寄せすべきです(今よりもっと)。
また牛乳パックへの植え替えも面白いですね。私はてっきり縦に使うものだと思っていたのですが、横向きはなるほどいい感じです。植え替えは根を痛めてはなりませんが、写真を見る限り下手なことにはなっていないようです。
植えた間隔もいいですね。ただ、たぶん茎葉のことに目が行ってしまったのでしょうね。お渡しした鉢は5号鉢というサイズ、土の容量は1リットル強だと思います。この牛乳パックはもちろんそれより小さいため、一株当たりの土の容量はどうなるでしょうか。ホウレンソウはイチゴやナスと違い、それほど土の容量を必要としない作物なので、育てられると思うのですが......より盆栽的になりますね(盆栽は「土の量を制限することで茎葉の成長を意図的に抑える」技術)。
牛乳パックの置き場所について、今の場所はやめた方が...... これは日照や街灯の問題ではなく、安全のためです。今の時期限定で、成長にいったんブーストをかけるという意味でしょうか...... 仙台に一年住んでみれば分かるんですが、冬の終わりごろにめちゃくちゃ強い風が吹く時期があります。一階ということで誰かにぶつかることはなさそうですが、それでも落ちたら始末に困るでしょう。更にダンボールをいちいちかぶせるのも大変なことです。
日照不足について、過去の受講生も色々考えて対策をしています。置き場の日照を丹念に探ったり、あるいは背後に反射板を置いたり、電照を使ったり...... さすがに光ファイバーを使った人はいませんでしたね(そこまですればもはや植物栽培というより人工物的)。考えること自体に意味があります。
最後に峠の釜めしは残念でしたね。そんなに硬いとは、恐るべしです。
次回記事も期待してお待ちします。
ラボスタッフ・オガタ