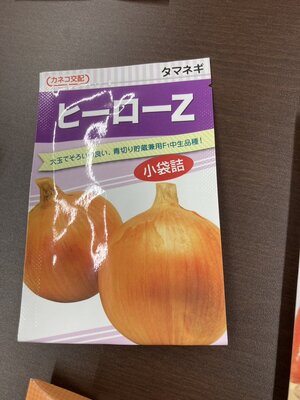目標はおいしく食べること!(文:佐藤 壱英)
2024年10月10日 (木)

目次
1.自己紹介
2.現状把握
3.10月4日~10月10日
4.今後の展望
1.自己紹介
皆様こんにちは。文学部一年目の佐藤壱英(いぶき)と申します。
岩手県のど真ん中、盛岡市出身です。大学入学後は学友会弓道部と釣り同好会に所属しています。上の写真は、夏休みに同好会メンバーと船釣りに行った時のものです。とってもいい天気だったので思い出になってます。
大学生活での目標は自転車で日本一周をすること。大学生活はまさしくモラトリアム期間。時間があるのだから、やりたいことは何でもやろうの気持ちで毎日を生きてます。この講義を選択したのも、やりたいことと講義内容が合致したからにほかありません。野菜、育てたいなーという軽い気持ちと文章うまく書けるようになりたいな、という気持ちが私の原動力です。
とはいえ、やると決めたからにはマイペースにつき進んでいくのが私の特徴。じっくりやっていきたいと思います。これからよろしくお願いします。
2.現状把握
さて、では本題に入りましょう。私が主として育てるのはユニコーン(キャベツ)とヒーローZ(玉ねぎ)の二つになります。
種の形は直径 4mmほどの球状。表面に種子粉衣をまとっています。極早生の品種であり、栽培期間は約80日。最大の特徴はその形状にあり、うまく結球させることができたら世にも珍しいとがったキャベツが完成します。「萎黄病Aタイプ抵抗性」があるようです。
種の形状は一粒2~3mmのレーズンのような形。表面にはしわが入っており、紫色の着色が施されています。5月中旬収穫のF1(?)中生品種で、青切り(?)・貯蔵兼用とのこと。玉は大玉で丸~豊円によく揃うそうです。
ほとんど配られた物のままですが、温度計とじょうろを100均で買ってきました。足りないものは適宜追加していきたいと思います。
玉ねぎとキャベツを選んだ理由なのですが、普段から食べているものがいいなと思って選びました。しかし、どちらも栽培が難しいようで... 。YouTubeとかで調べてみると、定植や虫対策、日照の確保、適度な追肥などなどやることがいっぱいで何が何やら。いろいろ教えてください。よろしくお願いします。
3.10月4日~10月10日
さて、難しいことは明日以降の私に任せるとして、まずは簡単なところから。さっそく種まきをしてみました。
事前準備として、鉢に土を入れ、水をまいたものが次の写真になります。
諸先輩方の記事についてのコメントで、鉢の下から水が出るくらいが良いといった内容を読んだため、受け皿に水がたまるくらいに入れました。土の量は、締まった状態で縁からマイナス2.5cmほどの高さになりました。
種まき
キャベツは好光性種子らしいのでユニコーンの種は、人差し指で土に穴をあけてその中に入れました。上から軽く土をかけ、ぎゅっと圧迫し、最後に水をかけて完成です。9個種をまき、最終的には一つをこの鉢の中で育てたいと思います。
玉ねぎは嫌光性種子らしいですが、種の大きさがユニコーンよりも小さかったので同様にして蒔きました。上にかぶる土の量が種の大きさの2~3倍のと情報を得たので、それに従ってやってみています。数は同じく9個で、いくつかは後々2Lペットボトルにでも植え替えて育ててみようかと考えています。
経過観察
自宅のベランダに置いています。10月4日の深夜に植え、以降は同じ場所に置いています。
10月5日から10月9日の期間、連日の雨により気温が上がらず少し不安でしたが発芽適温内での変化であったため、室内には入れず外に置き続けていました。気温は16℃~18℃を保っていました。なお、この気温は午前7時と午後10時の定期計測の際に得られたものであるため、昼間はもっと高くなっていると考えられます。
10月9日の朝。
気温を測りに外に出てみると...
ユニコーンが発芽してる!!!
昨晩の観察の際には発芽もしていなかったのですが、朝になると急激に成長していました。これは、夜の観察で私が見落とした可能性が高いです。高さは土から5~8mmほど。双葉の形状が確認できるほどしっかりと発芽していました。半分開きかけの個体もあります。しかし、中央に植えたはずの種がまだ発芽していないようです。また、思ったよりもひょろひょろしていて頼りない感じがあります。これが徒長か..?
ヒーローZの方は、まだ発芽していないようです。パッケージに発芽目安の表記がなかったためどれくらいで発芽するかは分かりませんが、種の大きさから考えてみると妥当かもしれません。大きい種のほうが養分を蓄えていると思うので、特に心配せずに様子を見ることにします。
中央のユニコーンが発芽していました。高さも他のものの3分の2ほどで、双葉も小さく縮こまっています。色も若干薄く、やや黄色成分が強いように感じます。これからの葉緑体の成長に期待です。
そして...
ヒーローZが発芽しました!!
まだ大部分が土の中ですが、よくよく見ると白い根のようなものが観察できます。どのような子葉の形状をしているのでしょうか。選択できる作物の中で唯一の単子葉類とのことなので、そこのところも詳しく観察していきたいです
4.今後の展望
どちらも無事に発芽したところで、今回の報告を終了とさせていただきます。こんな感じの報告でいいのかちょっと不安です。徒長問題や気温など、これから多くの困難が待ち受けていると思いますがなんとかあきらめずに取り組み続けたいと思います。次回以降は、観察・評価軸を増やして、もっと多くの情報を比較、考察できるように頑張りたいです。
まだまだ育てていない作物も残っていますからね、ここからしっかりと頑張っていきます!!
目標はおいしく食べること!
コメント
佐藤さんこんにちは!
おおお、実に若者らしい爽やかなプロフィールですね! 弓道と釣りという微妙なラインがまたいいです。ガチ体育でもなく、かといってインドアでもないあたりがポイント高いです。
モラトリアム期間というのは正しくその通りです。何かを思いっきりやるのも良し、ただダラダラしているのも良し、です。何であれ「ポジティブな記憶」を蓄えておけば、その貯蓄?で人生やっていけます。苦労は後からいくらでも出てきますので、若い時からわざわざ苦労しなくても構いません。
ちなみに東北大は全国の大学でも、必要単位数が最低クラスです。これは大学が学生を信用しているからで、ギリギリ勉強に追い込むことをせず、ほっといても伸びると思っているからです。その意味では良い大学選択でした。
それと出身地が盛岡! ここはいい地ですね。むろん気候の厳しさを知りませんが、清潔感のある綺麗な街です。これは単なる私の感想ですが、盛岡は他の東北の都市と比べても茶髪率が低い気がしますし......
さて投稿内容に入ります。
先ずはキャベツとタマネギ...... 思いっきり難易度高いツートップです。キャベツは生育は悪くないのですが、結球に至るまで行くのは大変です。タマネギは初期生育がのっそりしていますので、見ていて歯がゆく思われるかもしれません。まあどちらも幼植物のうちから食用にできるといえばそうですので、気長にいきましょう。
種子の観察、そして情報の提示は良い感じです。タマネギの情報提示でF1、中生、など疑問符がありましたが、これはおいおい説明するつもりです。さすがに文学部ではこの講義以外にそういった文言に触れる機会は無いと思いますから。
播種の方法は事前に情報を得て、それを活かして適切に行っているようです。粒数、覆土も問題ありません。好光性種子・嫌光性種子もよく考えました。まあキャベツとタマネギはそう厳密なものではありませんので、めちゃめちゃ深くさえしなければオッケーです。
敢えて言うと、水やりで「鉢受けに水が出る程度」というのは間違いないことなんですが、それは鉢受けに水を貯めておくということではありません。水が出過ぎたら適宜除去して下さい。水が常にあると、過湿、塩害、低温、といった害になります(それらの意味については折があれば説明します)。
次の投稿も期待しています。
温度情報について、せっかく温度計があるなら、写真撮影時の時刻で構わないのでしっかり測定し、提示した方がいいですね。来年度以降の受講生にとってはその温度が重要な情報になります。
そして環境のことでは温度と共に光の情報も重要です。置き場の日光の当たり具合のことです。理想的には直射日光が一日二時間以上欲しいところですが、なかなか難しいことで、過去の受講生も苦労したものです。
あ、そして写真撮影はこれで問題ありません。というのは科学論文において写真撮影は垂直方向と水平方向、つまり真横からか真上からか、どちらかにしておくものです。ただし、この展開ゼミでは斜め方向の方が見やすいということもあり、そこまで求めません。
ともあれ順調に行けばいいですね!
 モテま...... どっちなんだい!
モテま...... どっちなんだい!
ラボスタッフ・オガタ