第27回生命科学セミナー「The Status of Brassica plants and studying in Yunnan」開催(1/17)
2017年1月17日 (火)
週末にかけての猛烈な寒気団も少しどこかへ。気温がプラスになり、今日あたりは、5oCを越えることもあり、日陰の雪も少し残りはするものの、少ししのぎよい気温になってきました。そんな火曜日。科研費・基盤研究(B)の分担をしている「アブラナ科植物の伝播・栽培・食文化史に関する領域融合的研究」の関係で、雲南省農業科学院・園芸作物研究所・副所長である和江明教授と徐学忠教授が渡辺の研究室を訪問。今回の訪日は、日本のアブラナ科作物の品種改良についての調査。せっかくの機会ですので、渡辺の所でセミナーをお願いして。同行頂いたのは、昨年もこの科研費での調査に行かれた佐藤先生。以前は、ゲノム継承システム分野におられて、渡辺もお世話になっていました。
 セミナーでは、雲南におけるアブラナ科作物(ハクサイ、カラシナ、キャベツ類、西洋ナタネ、ワサビ、マカ、ダイコン)の育種、栽培の現状を。お国柄もあると思いますが、ハクサイについては、耐病性育種がずいぶんと進んでいるようですが、キャベツ類(B. oleraceaに分類される、ブロッコリー、カリフラワー、ケール、芽キャベツ)の種子の大半は、日本からの輸入品であり、ずいぶんと高価であるとか。。。日本の農業技術というか、そうしたことも世界に貢献していることを実感。ワサビというのは、国際語のようで、雲南にも野生の集団があると。
セミナーでは、雲南におけるアブラナ科作物(ハクサイ、カラシナ、キャベツ類、西洋ナタネ、ワサビ、マカ、ダイコン)の育種、栽培の現状を。お国柄もあると思いますが、ハクサイについては、耐病性育種がずいぶんと進んでいるようですが、キャベツ類(B. oleraceaに分類される、ブロッコリー、カリフラワー、ケール、芽キャベツ)の種子の大半は、日本からの輸入品であり、ずいぶんと高価であるとか。。。日本の農業技術というか、そうしたことも世界に貢献していることを実感。ワサビというのは、国際語のようで、雲南にも野生の集団があると。 マカも実はアブラナ科。種名は、Lepidium meyenii。マメグンバイナズナ属に分類されるもので、日本の道ばたにもこの属に分類されるグンバイナズナに似たものは、見かけると。で、雲南がorignというわけではなく、南米からいくつかの品種を輸入して栽培していると。また、ダイコンの栽培の一部は、日本に向けて輸出と。Brassicaでは、種間交雑により、雄性不稔系統が育成されており、よくありがちな不稔系統になると、蜜腺もなくなると言うことがなく、育種的には利用価値の高い系統も育成されているようで。
マカも実はアブラナ科。種名は、Lepidium meyenii。マメグンバイナズナ属に分類されるもので、日本の道ばたにもこの属に分類されるグンバイナズナに似たものは、見かけると。で、雲南がorignというわけではなく、南米からいくつかの品種を輸入して栽培していると。また、ダイコンの栽培の一部は、日本に向けて輸出と。Brassicaでは、種間交雑により、雄性不稔系統が育成されており、よくありがちな不稔系統になると、蜜腺もなくなると言うことがなく、育種的には利用価値の高い系統も育成されているようで。
わたなべしるす
PS. セミナーが終わった頃に、農学部の鳥山先生もlabに。和教授、徐教授を交えて、自家不和合性の話などを。学生さんには、labの中を案内頂いたり。セミナーには、菅野さんの所の中国からの留学生も参加してくれて、中国語での交流も。。。17:00少し前には、東谷研究科長も、研究室に来て頂き、お話しの時間を。ありがとうございました。と言うことで、午後からは国際性が少し上がった1日でした。

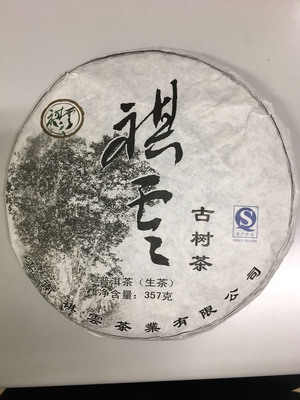
PS.のPS. あの阪神大震災から22年だと。。。17日は、昔は給料日だったので。。思い出したのでした。。。また、時間を見つけて、神戸がどうなったのか、拝見したいと。。。というか、震災後のあり方を考えるヒントに。。。

