ハツカダイコン大ピンチ(経:遠藤真由)
2017年12月29日 (金)
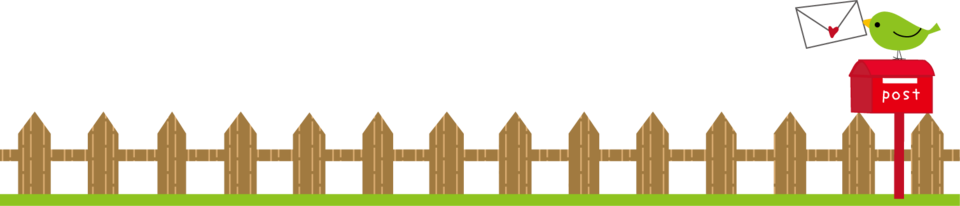
こんにちは。先日から大学も冬休みに入り、ようやくゆっくりと一息つけると思いきや、レポートなどの大学の課題にバイトにと慌ただしい冬休みを過ごしています。まさに師走です。本当は記事の更新頻度を上げたいところなのですが、自分のできる限りでやらせていただきます。
さて、先々週からハツカダイコンを簡易ビニールハウスの中に入れたまま一日中外に出すようにしたのでその経過を週ごとに報告したいと思います。
まずは昼は外に置き、夜は室内に置いていた時の写真がこちらです。茎から根にかけて細いです。
・12月13日 (水) 気温:最高気温4.2℃ 最低気温1.5℃
続いては一週間後の写真です。葉の緑色が濃くなりました。また、先端部分の葉だけでなく茎部分の小さな葉が大きくなりました。緑色も濃くなりました。
・12月21日(木)気温:最高気温7.4℃ 最低気温3.2℃
ここまでの経過は良好でハツカダイコンの状態が少しずつよくなってきつつありましたが、昨日夜風が吹いている中でしたが変わらず外に置き続けていました。その結果、ビニールハウスが大破した上にハツカダイコンはかなりぐったりしてしまいました。しかも気温も低かったため土壌が凍ってしまいました。これが霜が降りるということなのでしょうか。今回は風と気温が原因でこのようになってしましました。それと私の判断ミスです。ネットで調べたところ、ハツカダイコンの適正な生育気温は18℃~30℃とあったのでそれに比べると低すぎのような気がします。とりあえず今はハツカダイコンを室内に置き、凍った土を溶かしながら様子を見ようと思います。
・12月30日(木) 気温:最高気温4℃ 最低気温-3℃
コメント
遠藤さんこんにちは。
なるほどー、風で大破とは、これは予想外でした。非常にこちらも残念です。ハツカダイコンはかなりピンチな状況ですね。21日と30日の植物は画像で見ると萎れている他に葉の色も悪いようです。
先ずは、これでめげないように気をしっかり保ちましょう。そしてハツカダイコンは風の当たらない場所に移動して下さい。風の避けられない場所しかなければ室内になりますが・・ 温度よりも日照の方が重要です。更に計測されたように昼間温度と夜間温度の差が少ないと思います。
今回の事件で分かったことは、ビニールハウスを壊すほどの強風のある環境だった、ということです。これまで育ちの良くないこともありましたが、原因の一端が解明できそうな感じがしますね。少し回復すれば、土寄せ、もし土がなければ添え木で根元がふらつかないようにすればいいでしょう。割り箸とクイックタイで作ればよいかと思います。
それと、また寒波がやってきても、植物を急に暖めてはいけません。風で水分を失っているところに、ふらついて根にダメージを受けて、更に温度上昇で蒸散が大きくなれば、植物は対応できなくなってしまいます。
他、工夫等について教授からコメントがあります。
ラボスタッフ・オガタ
経済学部・遠藤さん
こんばんは、遺伝の渡辺でございます。まずは、ラボスタッフのオガタくんのコメントをしっかり読んで、対応してみてください。こちらが気になるのは、13日と21日の比較をすると、比較的温度が高く推移していたのでしょうか。植物はかなり生長していますよね。葉っぱの緑色も濃い状態で維持されているので、ここまではよくできていると思います。21日の次が30日なっています。つまり、10日ありますね。今日は比較的に日中は暖かったですね。朝の最低気温、日本気象協会のHPがnetの関係でこちらから見えないのですが、朝、見た限りでは、仙台の最低気温は、0oCくらいだったような。数日前の雪が降ったときは、かなり寒かったですね。もちろん、住んでいる場所にもよると思います。それで、まず、考えてほしいのは、雪が降る前とあとで、どうだったのか。雪が降る前にしおれていたとしたら、水やりが不足していますね。それに対して、雪が降ったあとに、室内に入れるなどして、溶かすことは、よくないというのを、昨日ですが、工学部・井野塲君の記事に、ラボスタッフのオガタくんがコメントしてくれています。雪への対応は、それをしっかり読んでください。
あとは、しばらくは室内で回復を見るようにしてください。井野塲君のはすぐに入れたからかどうか、分かりませんが、比較的もどっていますので。生き物ということで、植物を材料にしていますが、何かに関わって物事をやるというのは、それをしっかり観察したり、対応することが大事です。その姿勢をこの展開ゼミで学んでほしいですね。
わたなべしるす






