レッドキャベツ最終章(農:高橋悠太)
2022年11月 8日 (火)
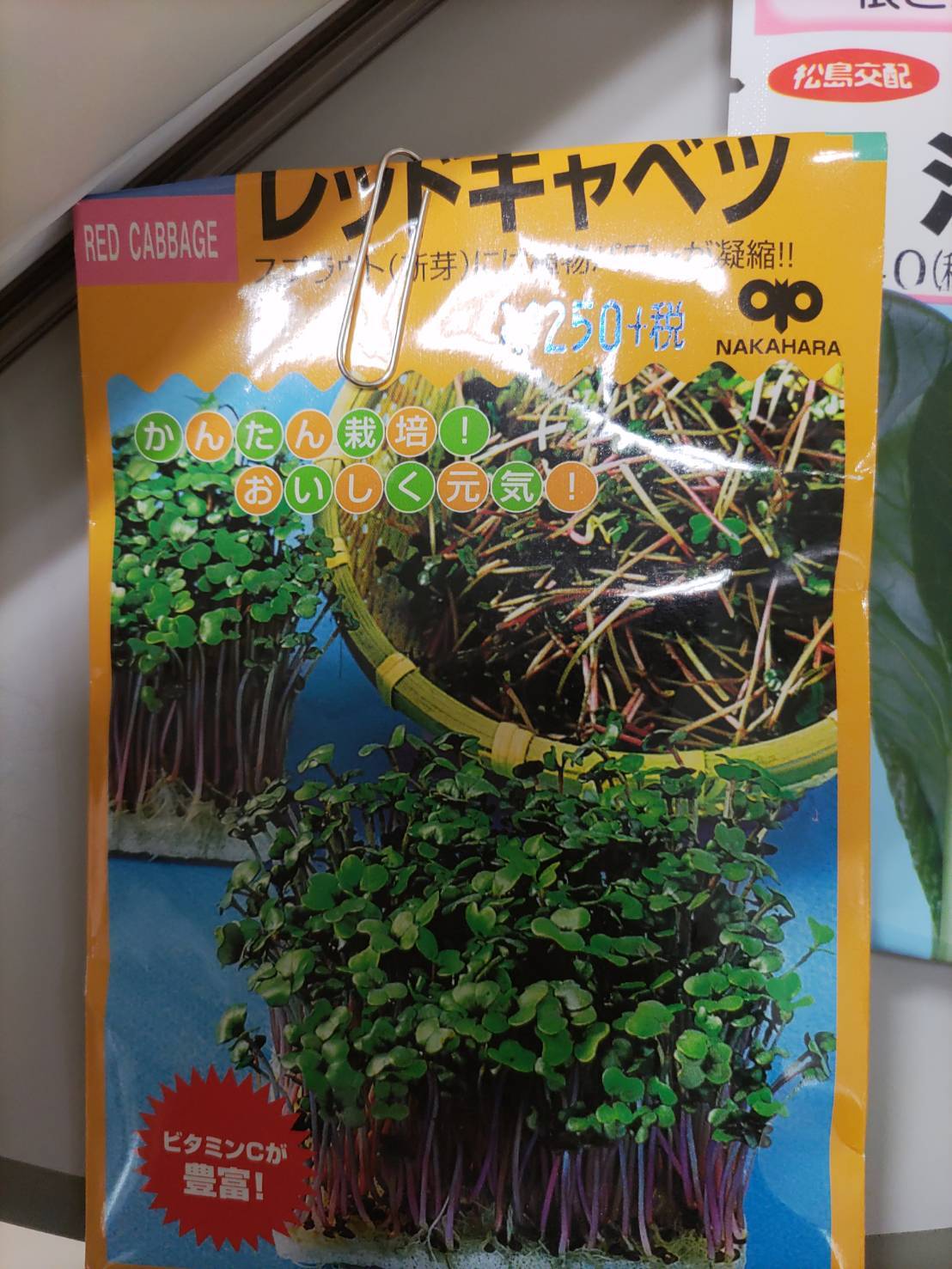
こんにちは。高橋悠太です。
昨日、ついに免許を取りました。でもまだまだ怖いので、ちゃんと練習してから走りたいと思います。それにしても雪が降る前に取れて本当に良かったです。
さて、今回はレッドキャベツ最終章と題して、レッドキャベツの育て始めから実食までを振り返っていきたいと思います。加えて少し調べたことも追記できればと思っています。
1日目:種まき
種子を発芽させるため、スポンジを敷いたコップの上に種子を蒔き、少量の水を与え様子を見る。初期の段階では気付いていなかったのだが、改めて調べてみると、先に種子に水を吸わせる段階があると良かったようで、スポンジに蒔く前にたっぷりの水で一日浸す段階を入れればより速く芽生えたのかもしれない。途中から生長に少しばらつきが出てしまったのは、この過程を省いたことで水が均一に行き渡っていなかったということが1つの要因として挙げられるだろう。
4日目:発芽から生長
生長自体は順調であったが、どこからか光が漏れていたようで、一定方向に曲がって生えていることに気付く。また、種子密度が均一でなかったせいで、少し絡まる個体が現れる。この時点で個体の大きさは2.5cmといったところである。今度はより平坦な培地を整え、種子密度を均一にし、完全遮蔽を心がけたいと思う。
10日目:5cmほどまで
5cmほどまで生長する。この時点では、再びまっすぐ生長するようになり、特に問題は生じていない。だが写真を見ていただくと、先に述べた種子密度が一定でないことが分かる。
12日目:緑化
ある程度生長しきり6cmほどまで生長したので、日に当てて緑化を始めた。今回のレッドキャベツは最後に日に当てるという方法を取ったが、スプラウト全種がそうではない。例えばもやしなどの品種は終始暗室で栽培する。かいわれ大根などは、発芽し茎が伸びた後に光に当てる。意外なところでは、発芽玄米もスプラウトの一種のようで、発芽させた後すぐ食用になる。
14日目:実食
ついに実食。サラダでシンプルに食べたが(キャベツonキャベツになってしまった)、意外と味が濃くかいわれ大根に近かった。ちなみに紫色はアントシアニンという色素によるものである。また、普通のキャベツより栄養価が高く、ビタミンCや食物繊維が多いという。
反省点はいろいろとあったが、今後の小松菜やちょい辛ミックスの栽培にもつながる大事な知見であった。次はそれらの生長についても詳しく記す。レッドキャベツについての報告は以上である。
コメント
農学部・高橋さん
ある程度の温度と水分があれば、室内で可能な「スプラウト」の栽培が完了したのはよいことです。最初の写真のように揃った状態の「スプラウト」を作ることの大変さを実感できたのではないでしょうか。スーパーなどに買い物に行ったとき、是非、市販されているプロが栽培した「スプラウト」を見る、あるいは購入してみて下さい。それと今回の写真、あるいは観察したときの感覚を比較すると、何が不足していたのか、見えてくると思います。お手本はもちろん、先達の数多くの記事ですが、食用ですから身の回りにあるわけです。そんなことも大事にして、これからも継続的な投稿をお待ちしております。
詳細へのコメントはラボスタッフ・オガタさんからのコメントをお待ち下さい。明日の午前中にはコメントができる予定です。
わたなべしるす
髙橋さんこんにちは
おお、免許を取りましたか! 早い目に取るのはいいですね! 農学部は他の学部より忙しくないものですが、それでも三年生四年生ではなかなか時間が取れませんから。
ちなみに私は47歳の時に免許を取りました。それはなぜか......自動車運転免許というものは原付講習が必ずくっついてますので、自転車に乗れない自分にはそもそも無理だと思っていたのです。ところが、原付講習では別に乗らなくてもいいと知ったので、ようやく運転免許を取ろうと思ったわけです。
ちなみにこの季節で免許を取ったのはいいですね。雪が降るとちょっと......更に言えば、日が短くなると必然的に日暮れ時の講習になってしまいます。
だいたい1日につき日暮れが1分早くなると思って下さい。これは仙台での話です。もちろん高緯度の方が激しく変化します。本当におまけの話なんですが、そういった日長の変化は農学的にも重要で、例えばタマネギの栽培において、北海道では貯蔵性の良い晩生種を栽培できるようになります。
さて、今回の記事はレッドキャベツスプラウトに的を絞った報告です。細かい観察と考察が見て取れます。発芽のバラツキ、茎の曲がり、その通りですね。播種密度はやや少なめなのですが、悪くはありません。市販のスプラウトに近いものになっています。
発芽玄米もスプラウト......そうですね。そもそもなぜスプラウトにするのか、植物は発芽時に猛烈に化学反応を開始し、種子とはまるで別の組成に変化します。人間にとっては食感なども大事なのですが、栄養的に重要です。例えば種子にほとんどビタミンCは無いのです。しかしスプラウトにすれば豊富にビタミンCを含みます。植物にとって必要な物質だからこそ作るわけですが、人間が利用するにも都合がいいですね。
さて最後は収穫、ここできちんと長さを計測しているのがポイント高いです。実食はキャベツサラダのトッピング、展開ゼミで初めてかもしれません。
アントシアニンについて、これは抗酸化物質ですから体に良い可能性がありますね。残念ですが、目に良いかどうかはエビデンスがありません。まあ料理的に面白いのは生ラーメンに加えた時です。生ラーメンの麺にはカンスイ(炭酸カリウムなど)が入っていてアルカリ性ですので、レッドキャベツスプラウトが真っ青に変化します。スープを入れるとその酸性で色が戻ったりしますが......
さあ、次記事はコマツナ等のことですね。今は変化の多い時期ですので、疑問点や修正点などありましたら早めに上げて下さい。日毎の変化を日記帳のように書くのを求めていません。そういった報告と、テーマをクローズアップするのと、メリハリがあってもいいですね。
ラボスタッフ・オガタ








 どんだけ食べにくいどら焼きなんだ......
どんだけ食べにくいどら焼きなんだ......