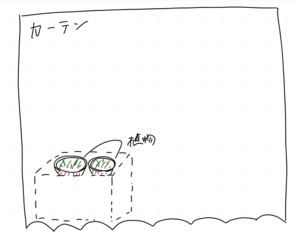初めての野菜栽培! part13(会:宮野 はるな)
2024年12月27日 (金)

こんにちは、宮野はるなです。
最近の会津若松は毎日雪が降っていて、冬本番の寒さとなってきました。
私の中で仙台は雪はふらないイメージを持っていたのですが渡辺教授の投稿を見て、今年は例年よりも寒く、雪も降るとのことだったので驚きました。
栽培状況について
前回の投稿のコメントに指摘があった、栽培状況についてです。
今回栽培していた場所があまり光の当たらない場所だったので、日中(昼間)は上記の絵のようにカーテンと窓の間の日光がよく当たる、室内の場所に置きました。
窓が近いために外の空気が少し入ってきやすく気温は室温よりも低下したと考えます。
夜に鉢を室内に入れているわけではなかったのですが、寒いところから温かいところに移していたのでその温度差や夜間高温であったことが植物にダメージを与えてしまい、生育を阻害してしまったのかと考えました。
コメントにあった、栽培を1日中屋外に切り替えることについてですが、最近会津では雪が降り続いていて、気温も0℃周辺であったので「早めの収穫」という手段を取ることに決めました。
収穫
12月25日(水) 播種24日目 18:18 室温(22℃)
市販
収穫をしました。2期生の方は例えるならば、かいわれ大根のような形状をしていました。以前ミックスを収穫した際は、葉の形状や色がかなり異なっていましたが、今回は収穫が早かったのでほとんど同じでした。
しかし、市販と比較してみると、異なる点が多く見られました。まずは、色です。2期生は緑色をしていますが、市販は黄緑色でした。
また、葉の形に注目してみると2期生は丸みを帯びていますが、市販は細長い形状でした。
その他にも2期生は茎の長さがバラバラですが、市販は比較的長さが揃っていたり、根に関しては2期生はしっかりとしていますが、市販は2期生に比べ細くなっています。
「ミックス」という植物の名前は同じなのに、こんなにも異なっているのは面白いことだと思いました。
屋内と屋外の比較について
まず、私が屋内で栽培をしたきっかけとして、これから育てていくにあたり外気温が低すぎるという理由が大きいのですが、最初育てたときに、虫害にあったので虫害を防ぐため、という理由もありました。
もし、屋内で栽培できたら手軽に農業に取り組めるのではないかという単純な気持ちで始めた比較でしたが、結果としては屋内で育てたものは途中で成長が止まってしまいました。先程も述べましたが、この理由としては昼夜の温度差であると考えます。
昼夜の温度差が生じたのは、私が鉢を室内で温かいところや寒いところに移したことが主な原因ではありますが、屋内で植物を育てるにあたり日光がよく当たり、温度差の変化が少なく、昼よりも夜の気温が低い場所というのは少ないと考えます。
栽培には屋外が最適であるということが体得できました。
コメント
宮野さんこんにちは
おお、最初からトンコツラーメンですね! 正統的なトンコツラーメンの具でありながら、やや麺が太めに見えるのも面白いことです。
さてさて投稿内容、先ずはこちらの質問に対してきちんと答えて下さってます。置き場の情報、図示までしています。実はこちらのイメージではもっと室内深くの、室内照明しかない場所かと思っていました。
カーテンと窓の間ならそんなに暗くないと想像しますが......しかしまあそれも家によるでしょうか。会津ならば家もかなりしっかりしたもので、断熱も充分、代わりに採光は少ないかもしれませんね。
ちなみに「仙台の雪」について、大雪とは「歩くのに邪魔になる」程度のことを言います。決して「歩けない」とか「道が見えなくなる」といったことはありません。数年に一度の記録的大雪で「雪のために車が出せなくなる」という現象が起こります。
確か仙台市の最大積雪量は21㎝だったと思います。私は数年前から山形で越冬していますが、山形市で最大積雪量は50㎝くらいですね。ただし、体感的には大差があります。イメージで仙台より山形が雪20倍くらいに思います。ということは......体感的に、例えばいわき市の積雪量5㎝というのは「雪無し」で、逆に米沢とか青森とかはめちゃくちゃ雪多く感じるんでしょうね。ちなみに言うと私は札幌住まいをしていた時期もありますが、雪で困ったことは一切ありませんでした。さすがに都会はしっかりしたものです。
さて植物の方はきちんと観察をしながら収穫しているようです。
せっかく二つの鉢を栽培しているのですから比較も面白いでしょう。お渡しした「ミックス」はその名の通り、いろんなものをミックスしています。アブラナ科もあればキク科(レタスなど)も入っています。これは味の変化もさることながら、多様な環境で対応できるよう(何かは成長できるよう)ミックスしたものです。そのため必然的に形や伸びはバラバラですね。それに対して市販のミックス種子はほぼキク科レタスのみで構成されているようです(まあ、レタスといってもバラエティは豊かで、普通の結球性レタスも、非結球性のリーフレタスも、サラダ菜も、サンチェも、茎レタスも、みなレタスの仲間です)。
さて結果として「屋外栽培」が良いというか、普通であることが分かりました。これは自然界での植物成長を考えたらそうなります。
おまけに言ってしまうと、温室栽培はそこから人間が「手を貸す」産物ですし、これが完全室内栽培(つまり植物工場)まで行ってしまうともはや「手取り足取り」です。逆にいえば莫大なリソースを消費する(資材面でもエネルギー面でも)ことでようやく成り立つのが植物工場です。もちろんエネルギー効率向上のためいろんな研究者が日夜努力して、LEDスペクトルや間欠点灯などトライしています。しかしそれでもエネルギーを多量に使い、得られた産物はその数十分の一のエネルギーしか持たないことには変わりなく、「栽培」ではなく「工場」というところが言い得て妙です。
ついでに言うと「魚の養殖」はいかにも食糧生産の切り札のように言われますが、何も魚が勝手に湧き出るわけではありません。あくまでイワシなどのコストの安い低級魚を大量にエサに使い、少しばかりの高級魚を得ているだけです。まあそれで市場価値には見合うわけでしょうが。
さあ、先日教授から「最終報告」について期限や内容などを示されました。これに沿って、期限に間に合うよう頑張りましょう。もちろんレギュラー投稿も大事です。あともう少しでこの講義も終わりますから、気合いですね!
ではまた、よろしくお願いいたします。
これは難易度高い!
正解は脳下垂体の前葉・中葉・後葉を表した「脳下垂体弁当」......
ラボスタッフ・オガタ