【リモート・アウトリーチ活動】岩手県立一関第一高等学校SSH特別講義、岩手県立盛岡第三高等学校・SRH(8/25, 30追記)
2020年8月25日 (火)
今年の秋はラニーニャ現象が発生するとか。その関係で、東北地方の気温は平年並みか、高め。降水量は平年並み。降水量を考えて見ると、7月まであれほど、雨降りが続いたのに、8月はほとんど降ってないような。。。カラカラに乾いた地面を見ると、樹木に冠水しないとまずいような。そんな8月が終わりそうな火曜日。
8/25(火):岩手県立一関第一高等学校SSH特別講義「将来に向けたキャリア形成と『考える基礎』となる課題研究のあり方」
先週の水曜日が同校での1年生向けに講義。改めて、撮影し直し、2年生向けに同じ講義を。課題研究とキャリア教育でしたが、どちらかと言えば、キャリア教育に重点を。プレゼンの時間を少し短めにして、質疑の時間を長めに。 前回は遠慮があった1年生。でも、2年生になると、その当たりはしっかりしていて。課題研究、部活動での研究、将来を見すえた大学進学への考え方など、多岐にわたった質問がたくさんで1hrになることはなかったですが、かなりdeepに議論ができたのは何よりかと。考えて行動する、ここで決断をする、観察をするなど、講義の中で取り上げたことはこれからの大学、社会人になっても同様に大事なこと。進路を考える頃でもあるので、その当たりも踏まえて、しっかりがんばって下さい。豊かな自然をしっかり観察して、その営みの不思議に思いを馳せることで、気がつかなかったことに気がつく観察眼が養われると思いますので。最後になりましたが、柿木先生をはじめとする関係の皆様にお世話なりました。ありがとうございました。コロナ禍の収束が見えない現在、このような形でこれからもコラボできればと思います。ありがとうございました。
前回は遠慮があった1年生。でも、2年生になると、その当たりはしっかりしていて。課題研究、部活動での研究、将来を見すえた大学進学への考え方など、多岐にわたった質問がたくさんで1hrになることはなかったですが、かなりdeepに議論ができたのは何よりかと。考えて行動する、ここで決断をする、観察をするなど、講義の中で取り上げたことはこれからの大学、社会人になっても同様に大事なこと。進路を考える頃でもあるので、その当たりも踏まえて、しっかりがんばって下さい。豊かな自然をしっかり観察して、その営みの不思議に思いを馳せることで、気がつかなかったことに気がつく観察眼が養われると思いますので。最後になりましたが、柿木先生をはじめとする関係の皆様にお世話なりました。ありがとうございました。コロナ禍の収束が見えない現在、このような形でこれからもコラボできればと思います。ありがとうございました。
8/30(日):岩手県立盛岡第三高等学校・令和2年度SRH課題研究中間発表会
前日29日、仙台でも久しぶりの降雨。20mmを超えましたが、思ったほどの気温の低下もなく。。。どうすれば、気温が下がるのか。。安眠を取り戻すためにも、気温が下がってほしいのですが。9月になると、雨が少し多くなることを期待して。8月最後の日曜日は盛岡へ。新型コロナvirusが拡大してから、3回目。
岩手県立盛岡第三高等学校の課題研究活動はSSHにはじまり、SRHに継承して今年で10年目。継続するのこと重要性を改めて、実感。研究発表は10課題。物理、化学、生物、地学、数学という多様な研究内容。身近な普段の食事の中に問題を見いだしているのは、身の回りをしっかり観察して、注意力をもつことができているのだなと。また、中間発表と言うことで、実験を始めたばかりかも知れないですが、どうやって定量化するのか、条件を変化させるのか、過去の先行研究をきちんと追試ができているのかなど、コロナ禍での実験で苦労していると思いましたが、大事なポイントですので。発表の間の「休憩」の時間にも積極的に質問に来るグループも。とてもniceでした。研究材料に、昔、土壌学で学んだ土壌鉱物の名前が。。。驚きとともに、そんな物性があったとは。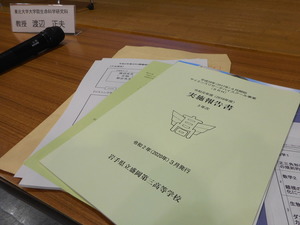 発表が終わったところで、教員側から講評。。。運営指導委員の方々から色々な講評が。いずれも納得できるもの。渡辺からは、グループの中での立ち位置(発表をする、質疑応答に対応するなど)を考えること。実験の基本原理を理解すること。実験のdataをとったら、すぐに解析すること。実験結果を放置して、あとから考えると、「あれ??」と思うようなことが出てきますので。「鉄は熱いうちに打て」と、いうとおりですので。
発表が終わったところで、教員側から講評。。。運営指導委員の方々から色々な講評が。いずれも納得できるもの。渡辺からは、グループの中での立ち位置(発表をする、質疑応答に対応するなど)を考えること。実験の基本原理を理解すること。実験のdataをとったら、すぐに解析すること。実験結果を放置して、あとから考えると、「あれ??」と思うようなことが出てきますので。「鉄は熱いうちに打て」と、いうとおりですので。
講評のあとは、生物班とのdeepな議論の時間。これも、盛岡三のSRHでの取組の1つ。よりよい方向に実験をチャレンジしてもらえれば、と思います。最後になりましたが、中島校長先生、SRHを統括されている米沢先生をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。年度末の発表が何とかできる形になることを祈るばかりです。
わたなべしるす
PS. いつもなら出前講義に行くところの先生から、その場所をイメージできる写真を頂きました。ありがとうございました。コロナ禍が終息することの祈るばかりです。

