中間発表~文字数は2765文字~(農:粥川颯人)
2019年11月21日 (木)
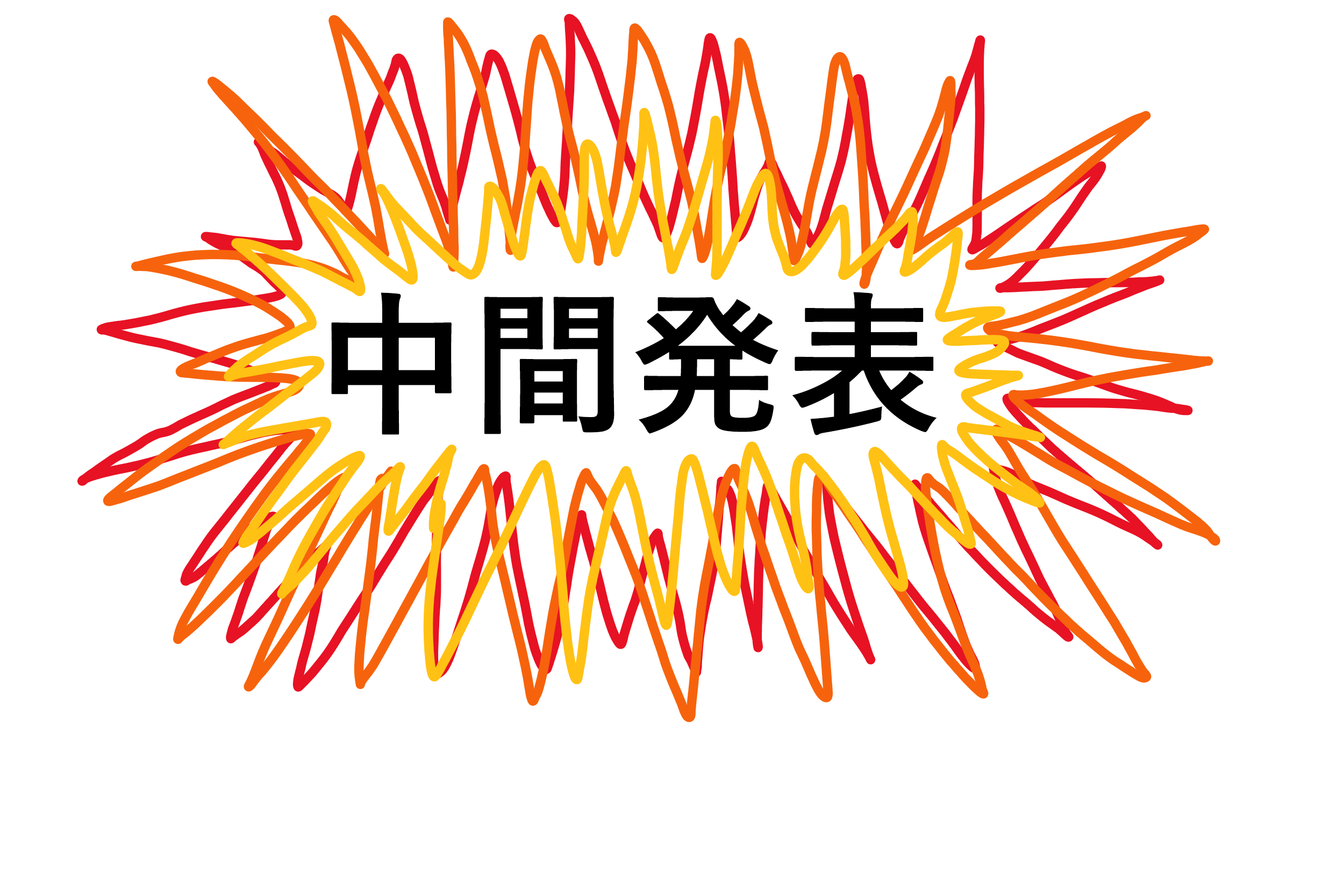
間引きのタイミングで自分の髪も切ることにした粥川です。
ここ数日でいきなり気温が下がりいよいよ冬到来!という感じですね。
東北出身でない人は寒い寒い言ってますが、僕は上り坂をチャリで爆走しながら吸う冬の空気が最高だと思います。いかにも呼吸しているという実感があっていいんですよね。
さて、今回は中間発表ということなので無駄話で文字数を稼ぐセコいやり方はせず、まじめに以下の事項について書いていこうと思います。
.
栽培において一番驚いたこと
参考になった記事
コメント等からの気づき
双方向性という特徴を持ったこの授業について
これからの栽培について
栽培において一番驚いたこと
栽培、というか観察の中で一番驚いた(面白いと思った)発見はやはり、キャベツの葉の形です。今まで、特に料理をするわけでもキャベツを栽培するわけでもなかったので、まじまじとキャベツを見たことなどほとんどありませんでした。
.
下に僕のキャベツの想像図を載せておきます。
・ほぼ円状の葉が何枚も丸まっている
・たぶん葉先は黄色っぽい
・芯のほうは白く、黒い点々がある(と思う)
.
つづいて、本物のキャベツの写真です。
 (https://getnews.jp/archives/1983655 より引用)
(https://getnews.jp/archives/1983655 より引用)
・葉のふちが波型の葉が何枚も丸まっている
・葉の色は薄緑色一色
・白いのは葉脈の部分だけで黒い点々なんてない
.
キャベツなんて週3くらいで19年も食べているはずなのにぼーっと生きていると頭の中で勝手に白菜要素の入った違う野菜になってしまうようです。
.
.
さて、驚いた点はこれ以降の話になります。上にいったん黒キャベツの写真を載せましたが、この写真と本物のキャベツの特徴①に注目してください。本物のキャベツの説明では「葉のふちが波型の葉が何枚も丸まっている」と書きました。この特徴というのは黒キャベツにも共通する特徴です。Wikipediaを見ていただければわかるのですが、ヤセイカンランというアブラナ科の植物がキャベツの祖先種でありながら結球しないという特徴を持ちます。つまり、結球しないヤセイカンランを食用に品種改良したものが黒キャベツ、結球する変異種を更に品種改良したものがキャベツということになります。
.
.
第一回記事では「(黒キャベツの)外見は全くキャベツではないです。」というコメントを残しました。しかし、実際にキャベツと黒キャベツを育ててみると、葉のふちが波型という点や葉に少し皴がみられる点など共通点が意外とあるということが分かりました。やはり、平面の画像の観察では気づけないこと・気づきにくいことをリアルな観察で気づくことができます。こういった観察は今後も大事にしていきたいです。
.
参考になった記事
参考になった記事・面白いなあと思った記事が二つほどあるので紹介しようと思います。
.
一つ目、2017年度の小笠原千夏さんの記事です。これは参考になった部門でのノミネートです。千夏さんが育てていた植物の一つがハツカダイコンだったのですが、水やりをしっかりしているのに枯れてしまうという事態が起きたようです。これは、表土が湿る程度に水やりをしていたところ、土壌中の養分の中で濃度勾配ができて塩害が起こってしまったというのが原因だったそうです。僕も普段霧吹きを使っているのでこの記事を見てからはちょろちょろと霧吹きを使わずに水をやるようにしました。
.
二つ目は今年度の松木優佳さんの記事です。こちらは面白いなあ部門でのノミネートです。何が面白いのかというと、ブロッコリースプラウトの長さを毎日記録してグラフ化したところです。しかも、最頻値と最大値のデータが出ているのでおそらく30ほどの個体のデータを全部採っていたのだと思われます。データを集め続ける姿勢とそのデータを見やすく加工する姿勢の両方をできる範囲で見習わなければならないなと感じました。日々精進。
.
コメント等からの気づき
気づきというよりもコメントに対する感想に近いのですが、コメントは毎回その問題や特徴が表れる原理を教えてくれたり、面白い豆知識を提供してくれたりするので毎回楽しく読ませていただいています。具体的には僕の第一回記事のキャベツの結球に対するコメントで「人間にとって結球は、葉が柔らかくクセがなく、旨味もある(ハクサイなどは中心部に植物性旨味のグルタミン酸を持つ)、つまり有用な性質なので選抜・育種したと思われます。」という一言で感心したり、例のショウジョウバエ事件に対する未熟な有機質が多いと腐敗・虫の原因となるとのアドバイスで問題の解決のヒントになったりしていました。
答えを提示されるよりも原理を教えてもらった方が自分なりの工夫の幅が広がるので、これからも今まで通りの感じのコメントを頂けるとありがたいです。
.
双方向性という特徴を持ったこの授業について
基本的に生徒が植物の観察記録や生育状況を発信し、教員サイドが最小限のアドバイスを与えるという授業形態はいいなと思います。ただ受けるだけの劇場型の授業は僕は聞いていないことが多いので、ある程度能動性を求められた方が学びや気づきが多いと思うからです。
しかし、今の自分の記事では「情報発信→コメントを見て満足」というパターンが多いため、双方向性を活かしきれていないなと感じています。ほかの受講生の記事を見るとだいたいは記事の最初か最後に「前回のコメントについて」というコーナーがあるので、自分も真似ていきたいと思います。具体的には、コメントに対してさらに鋭い質問で返していくということができればもっと面白い記事になるのかなと思いました。
.
これからの栽培について
キャベツの栽培を始めるにあたり、以下の三つの目標を立てました。これらの目標はこれからも目標であり続けます。
1.なるべく徒長させないこと
2.キャベツを結球させること
3.おいしいロールキャベツを作ること
このうち、一番目に関してはクリア済みかなと思います。あとは結球と料理の腕なのですが、結球に関しては見事結球させた2016年度の福島さんの記事を参考にしていきたいなと思います。実家暮らしなので料理に関しては夜食を作るなどして頑張りたいと思います。
また、この記事を作るうえで様々な受講者の記事を拝見しましたが、その中でも「数値を用いたデータの集計」、「グラフなどを用いた可視化」、「コメントをもっと活用し双方向性を活かす」という三つのことは今後取り組んでいこうと思います。
最後に、みなさんご存じの通り僕は継続が苦手な男です。そこで、この展開ゼミの中では継続の習慣を身に着ける、さらにはどうすれば継続できるのかを学んでいくということを残りの期間でやっていきたいと思います。
.
今後も記事の更新を続けていきますので渡辺先生、オガタさんはご指導のほどよろしくお願いします。
あっ、あと、この記事呼んでくれている僕の友達は記事更新を怠った瞬間に僕をビンタしてもらって構わないです。次回記事は11/26更新です。
コメント
農学部・粥川さん
遺伝の渡辺でございます。何よりも1番最初の投稿というのは評価できますね。ただ、それが木曜日というのは。もちろん、〆切の内側ですが、他にも〆切が近いものがあると思います。できるだけ、早め早めの対応をすることを心がけてみて下さい。
自分の栽培している野菜の未来想像図を書いてみるというのは、よいことですね。こうなってほしいと言うこともあるかも知れないですが、1つの目標を設定すると言うことですから。一方で、この講義はどちらかと言えば、理科に近い分類。つまり、「芯」と書いてありますが、これは、植物形態学から見れば「茎」になります。茎から葉っぱが出ているというイメージで、それが重なっていると言うことです。あと、キャベツとハクサイを混同しているようですが、ハクサイ(Brassica rapa)とキャベツ(Brassica oleracea)は、異なった種です。農学部で植物系に進むと、講義を受けると思います。もちろん、その前に調べてみることはよいことですから、やってみて下さい。
普段の栽培については、自宅生と言うこともあって、日当たりのよいところで栽培できている分、よく管理されていると思います。ラボスタッフからのコメントも有効に利活用できているのではと思います。あと、されていると思いますが、他の受講生の記事、それへのコメントを読んで、自分と比較することをやってみて下さい。
それから、中間発表の中に黒キャベツと普通のキャベツが初期生育では変わらないというような表記があったですが、これを言うために、両方の写真を並べて、説明しているのはよいことです。普通のキャベツがいわゆる「対象区(control)」になります。比べるから、何かをすることができると言うことです。一方で、細かなことですが、双方向性のところの表記に「生徒」とありましたが、大学生になると「学生」と言われます。なぜ、言葉を変えたのか、昔の人が意図を持っていたのだと思いますが、渡辺が教えてもらった園芸学の先生が興味深いコメントをくれました。「生徒」というのは、「徒(いたずら)に生きる」。学生は「生きることを学ぶ」。今でこそ、大学の講義を授業というようになりましたが、昔は講義と授業は高校と大学の境目にありました。授業は「生業(なりわい)を授ける」。講義は「義とは何かと言うことを講ずる」。つまり、高校生までは、徒に生きているので、それをよくして、生きていくための方法を教えてもらうところ。大学生は、自ら生きることを学んで、講義で話されたことについて、自分がどう考えるのかと言うことに思いをはせる。と言うようなことでしょうか。その当たりの自覚を持って、後半の展開ゼミにのぞんで下さい。それから、この後に、文系の受講生が報告をしています。文章に流れがあるというか、このパラグラフで何を言うのかなど、違いがわかると思います。しっかりと長い文章を書けるように心がけて、頑張って下さい
わたなべしるす
PS. 変換ミスもちらほら。そんなところもしっかりと。




