ほうれん草を作ろう その15.5(最終報告: ほうれん草作りと習慣作り)(工:柳澤暢孝)
2024年1月21日 (日)

こんにちは、柳澤です。
今回は最終報告になります。
自分の時間割では、来週(1/27~の週)に、期末試験がある授業が4つ集中しているため、この最終報告は早めに投稿しておきます。
(目次)
① 植物栽培で大変だったこと、うまくいったこと
② 他の講義への波及効果
③ 毎日の観察で身についたこと、感じたこと
④ 文章の変化
⑤ 自然科学的なものの見方
⑥ 先生やスタッフの方々からのコメント
⑦ 中間発表で目指したことの達成度
⑧ 授業で学んだことを、日々の生活にどう活かせるか
① 植物栽培で大変だったこと、うまくいったこと
僕は今まで、母親や小学校の先生に手伝ってもらいながら野菜を作ったことはありましたが、自分から(コメントはたくさん頂きましたが)作るのは初めてでした。今回の栽培では、どう育てれば僕の望むような美味しいほうれん草が食べられるのか、考えることがとても大変でした。例えば、育て初めのころは、水やりの頻度や、間引きのやり方がよくわかりませんでした。母親や小学校での記憶を思い出しつつ世話をしていました。
ただ、今になって見てみると最初のころが手探りなのは他の方々にもあるなのかもしれません。(田中さんも清田さんも、初めのころは色々考えていたみたい?)
 育て初めたころの写真
育て初めたころの写真
今見ると土が相当少ないので、だんだん増やしていったことが分かる
実は中学生~高校生のころ、僕は生物がとても苦手でした。細胞の中にある器官の名前や、DNAの構造など、単語はたくさん出てきましたが、仕組みがよくわからず、結局何も分からずに終わりました。生物に関する知識がそんな感じなので、特に子葉が見え始めるまでのころは、栽培のやり方を理解するのも大変でした。ただ、野菜を育てるにあたって必要となるような植物の知識は、基本的なものだと思うので、ここで知ることができたのはよかったと思います。子葉と本葉があることなど、そういえば昔教わったような気がします。
葉の形にバリエーションがあったころ
しかし、日々のお世話をすること自体は、今までを振り返ってみると、そこまで大変ではなかったような気がします。写真も毎日撮っています。やっている最中はめんどくさく感じていましたが、それでも楽しみながらお世話をできました。もともと野菜栽培をやってみたかったことが、続けられた理由として一番大きいと思います。
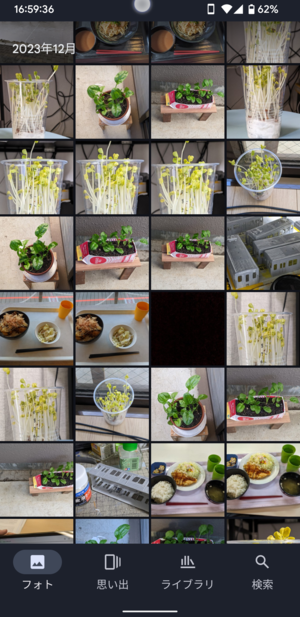
毎日植物の写真を撮っていると、撮った写真も植物だらけ
② 他の講義への波及効果
この授業から他の授業への波及効果としては、「習慣を新しく作る技術」があると思います。この授業で僕は、毎週記事を書くこと自体もそうですが、記事を書く中で、毎朝ベランダに出て写真を撮り、ほうれん草の様子を観察していました。寒いとあまりベランダにも出たくなくなるのですが、観察する以外にも写真を撮ることで、もう一つ楽しむ目的を作ることができたこともよかったと思います。
また、僕は毎週金曜日の午後に記事を投稿していますが、これは金曜日の3・4時間目に授業が入っていないので、この時間を記事を書く時間に割り当てて、記事を書くようにしていたからです。
予定管理に使っているgoogleカレンダー
別の課題をやらなければならなかったり、自動車学校の予約を入れてしまったりして守れない時もありましたが、この時間を決めておくことで、ある程度習慣づけられました。
これらのことは、僕の学科で必修になっている物理学Bで、予習を習慣化するときに役立ったと思います。物理学Bの授業では、前回やった範囲から毎週小テストを作るのですが、板書はclassroomに上がりませんし、教科書も難解でよくわかりません。自分でノートを見ながら、公式の導出をやり直したりするのですが、その時に先生に毎週聞きながらやっていたので、やる気になったと思います。
③ 毎日の観察で身についたこと、感じたこと
②でも書きましたが、「毎週」と一緒に、「毎日」何か世話をするところが、この授業の大変なところだと思います。その結果、習慣を作る技術を少し学んだと思っています。
特にほうれん草の写真を撮っていて、そう感じたことがあります。毎日ほうれん草の写真を撮っていると、様子があまり変わっていないように感じて、毎日撮る必要があるのかわからなくなってしまいます。でも、それを1週間や1か月続けていれば、大きく変わっていくことが感じられるのだと思います。ほうれん草の成長具合もそうですが、土の乾き方、肥料の効果、なども変わっていきます。毎日見た方が、長い期間での成長に気づきやすいかもしれませんし、これらの変化がすべて一定の間隔(3日とか、1週間とか)で進むわけではないので、毎日見るのが大事なのだと思います。
それから、たまにですが、突然ほうれん草の姿が変わることもありました。最近では、雪が降った日に、ほうれん草が突然縮み、次の日に復活する、ということがありました。こういうハプニングに気が付けるのも、毎日撮っていたからでしょう。
④ 文章の変化
今でもまだその部分はありますが、この授業を受ける前、僕は長文を書くことが苦手でした。何を書けばよいのかわからず、文章が短くなりすぎて、本当に伝えたいことを伝えきれませんでした。
この授業を受ける中で、文章で何かを発表したりレポートに書いたりするときに、何を書けばいいのかを少しは学べたと思っています。前期にも「自然科学総合実験」という、かなりしっかりレポートを書かなければならない授業を受けていたのですが、この授業はそれよりも自由度の高い内容でしたので、より実践的に感じました。
この授業でも、毎週何を伝えればよいのかを考えました。ある程度の型は、過去の記事で大体つかむことができましたが、この授業では「毎日の観察」と「今週やったこと」、「来週以降やりたいこと」を、ほぼ毎週書いていました。そうした点で、文章を書くことに慣れることができたと思います。これからはさらに、分かりやすく、うまく伝えられる文章を書けるようになりたいです。
⑤ 自然科学的なものの見方
ほうれん草を観察するときには、目で見て感じたことだけではなく、葉の長さや茎の高さを測って、数字で表すこともしていました。その数字を扱うやり方が、自然科学的な見方として、少しは身についたと思っています。これは自分でやっているだけなので、まだまだ遊びのレベルですが...
例えば、栽培日数ごとに葉の大きさを比較するときには、一本の苗ではなく全体の傾向を把握することが必要であり、そこから、日数以外の条件をそろえて正確に比較すること、葉が大きくなる時の日数との関係について考えれば、より正確に数字で表すことができそうです。
やること自体は、このくらいならとても単純ですし、自然科学総合実験などでも既に習っている内容です。しかし、この講義で僕は、全体の傾向をあまり見られていないと思います。今育てている苗は9本あるのですが、実際に測って比べているのは1~2本だけです。全部の葉の本数を調べるのが手間だと感じてしまい、楽で続けやすそうな方を優先したのですが、より正確に測ることを考えると、それだと全体の傾向は掴めないと思います。9本全部まではいかなくても、牛乳パックと鉢植えでの生育の違いは見ておきたかったです。
まず、続けることはなんとかできそうなので、次はさらに定量的に、全体を見られるようにしたいです。できることはまだあると思います。
⑥ 先生やスタッフの方々からのコメント
僕は生き物の知識が本当に少ないので、先生やスタッフの方々のコメントはとても参考になりました。写真や日付などの記録方法から、種の巻き方、水やり、土寄せ、肥料、...。過去の記事やWebサイトの情報もたくさん見ましたし、それを探すこともとても大事です。ただ、この授業での栽培環境を一番知っているのは開講している先生方なので、コメントでの指摘が、僕のほうれん草の環境には一番適していると感じました。
また、コメントを受け取れるという事は、一人でなんでも考えなければならないのではなく、一緒に考えながら植物を作っていけるのだ、という考え方もできると思います。
僕はもともと、趣味で何か野菜を作りたいと考えていました。しかし、もし僕が趣味でほうれん草を育て始めても、尾形さんのように毎週コメントをくれる人はいないと思います。twitter(X)などに投稿したり、園芸屋さんに持って行ったりすれば何か反応が得られるかもしれませんが、毎週そうするのは大変だと思います。そのような孤独な状況だと、ここまで枯れずにほうれん草を育てるのは難しかったかもしれません。何か月も飽きずに続けることは出来なかったかもしれません。双方向だから、折れずに今まで続けられたのだと思います。履修登録をしてよかったです。
 この土寄せも、コメントをもとにやった作業の一つ
この土寄せも、コメントをもとにやった作業の一つ
頂いたコメントは、自分のほうれん草の環境を考えつつ、なるべく早く取り入れるようにしていました。ただ、尾形さんは毎週月曜日ごろまでに返信をいただくのですが、それを見るのが遅くなったり、見ても、コメントに沿って作業をすることをめんどくさがったりして、フィードバックが遅くなることもありました。
一応、コメントをいただいた次の記事までには反映できるようにしているので、差ができるのは1週間です。植物は1日単位では同じように見えるとはいえ、1、2週間になってくると、さすがに成長も進みます。素早く対応できれば、もっと良かったと思います。
⑦ 中間発表で目指したことの達成度
11/23に投稿した中間発表では、「引き続き金曜日に投稿すること」と、「最後の収穫までほうれん草の面倒を見ること」を目標にしました。
前者については、今のところしっかり続けられています。文章を書いたり、写真を集めたりするまとめ作業は金曜日にやっていますが、その内容を考えたり、写真を撮ったりすることは、日々お世話をしながらやっています。ほうれん草をもっと成長させるために、反射板や台を作ってみたり、計測方法や帰省中の水やり方法について考えてみたりもしました。
順調にいけば、通常の記事投稿は、あと1/26と2/2の二回です。できれば、収穫までは記事を書いてみたいなと思います。授業期間が終わってしまうので、休みたくなってしまうかもしれませんが...
後者は、収穫しないと達成できないような内容ですので、達成するのはまだまだこの先です。それでも、もう少しで収穫できそうだ、ということは感じています。
また、中間発表の中で明言した目標の中にはありませんが、頭の中で作ってみようと思ったのに、結局実行できなかったアイデアがいくつかあります。
例えば11月ごろ、僕はarduino(マイコン)と温度センサーで、鉢付近の温度や湿度を測り続ける装置を作ってみたいと思っていました。僕は今までずっと、観察に仙台市の気象情報をつかっていますが、自宅のベランダはまた違った温度変化になっているかもしれません。また、測って得られた数値をパソコンに送って記録しつづけることで、変化が分かって面白そうだと思っていました。
というわけで、部品は全部10月ごろに上杉のマルツ電波で買っていたのですが、まだ何もできていないうちに最終報告になってしまいました。また興味が向いたら、作り始めるかもしれません。
マルツで買った温度センサー
下の方に入っているRCA端子は、温度計関係なく趣味で使いたかった部品ですが、これもまだ触れてません
⑧ 授業で学んだことを、日々の生活にどう活かせるか
②や③、⑥と内容が被ってしまいますが、何か習慣を新しく作ったり、作った習慣をずっと続けたりしていくことが、これからの生活に生かせると思います。記事の投稿をここまで続けられたことの理由の一つには、「授業で毎週投稿しなければいけない」という圧力と、「最後まで世話をし続ければ、おいしいほうれん草が食べられる」という楽しみの部分が両方あり、自分の中でバランスが取れたことがあると思います。
理由のうち「授業で毎週投稿しなければいけない」について、もう少し考えてみます。ここまでの授業や、授業関係なく今まで自分がやってきたことを考えると、自分の中だけで完結するのではなく、他人(ここでは先生方や他の受講生の方々)がいる環境で続けたことが、ちょうどいいプレッシャーとなったような気がしています。人を巻き込んだり、人に目標を宣言したりすることで、続けようとする気持ちが生まれると思います。
日々の生活にたとえれば、もし僕が「毎週台所の流しを掃除しよう」と決めたとします。普通にやったら、一人で毎週末がんばることになりますが、友達などに「僕は流しをきれいにするぞ!」とか宣言することで、やろうとする気持ちが少しは増えると思います。台所の流し掃除は実際のところ、本当にめんどくさいので、良い習慣が増えたらしいなと思います。
ただ、プレッシャーをかけられすぎるのもそれはそれで疲れますし、一人でのんびりやった方が楽しいこともあるので、うまく楽しめるように使っていきたいです。
最後に、今後のほうれん草の予定ですが、もう収穫の時期が見えてきていると思います。尾形さんは先週のコメントで「市販のほうれん草は高さが大体25cmだ」ということをおっしゃっていましたが、収穫するにあたっては「どうなったら収穫なのか」を考えておきたいです。「高さが20cmになったら収穫」「2/2に収穫(そのまま調理して記事にする)」などをなんとなく考えています。
(5276字)
最終報告の内容は以上です。
ほうれん草の収穫が楽しみです。
コメント
工学部 柳澤さん
この講義への向き合い方をしっかりと習得したことで、他の受講枠のことを考えながら、行動ができるようになり、翻ってこの講義の最終報告を5日前に完了できたのだと思います。生物が苦手という点、言われる通りですね。覚えることがたくさんありすぎて、それぞれの現象のつながりが分かりにくかったり、生物種によって異なったり。そんな時、細胞、DNAとかいう難しいことではなくて、小学校の頃、土から子葉が展開したのを見て、うれしかったのを思い出したのではないでしょうか。毎日が観察というので大変なところを楽しみに変えて、行動できているのが高く評価できますね。なにより一覧になった写真を見て取っても、この講義でしっかり植物に向き合い、それらを記事の中に投稿できているのがよい点です。習慣づけをしても、その時間に優先度の高いやるべきことが入るのは多いことです。その時、忘れないようにその枠でやることをしっかり対応できる「心得」を習得できたことで、他の講義にもpositiveに働いているのが見て取れます。今後、専門性の高い講義が始まると思いますが、そこにおいても講義と講義の関係等を考えながら、この講義で習得したことをさらに深化させることができる講義への取組と最終報告でした。
毎週の決まった時間に投稿され、また、毎日観察して、変化であったり、問題が生じていることに的確に対応できていることも評価できる点です。最近は自動で計測したり、何かをやってくれる装置など多くなりましたが、見てないときに限って、トラブルが起きるものです。そういう意味でも、定時に確認することの大切さを理解できています。また、それをどのような文章とそれを表す写真、最後の方はグラフ化にもチャレンジしていて、工学を学ぶ上でもグラフ化をしてみたことは活かされると思います。
こちらが意図している双方向性の重要度をしっかり分かってもらえているのもありがたいですね。これから先、色々な場面で双方向での学びというのは出てくると思います。場合によっては、教えるだけ、教えてもらうだけでなく、case by caseで逆になったり。そんな時、どちらの立場に立っても行動が起こせるのではないでしょうか。これの発展型と言うことになると思いますが、異分野間での共同研究も同じような双方向での学びになると思います。この双方向での学びを多様な場面に活かして下さい。
このタイミングであと2回の投稿を宣言していることも、開講した側としては勇気づけられます。収穫までもう少しと書いてありましたが、栽培している個体の中でも大きい個体を選んで、食してみてはいかがでしょうか。それを是非、最終回と宣言している2/2に記事になると、これまでにやってきたことを違った角度で振り返ることができるのではないでしょうか。楽しみにしております。
最後の段落に書かれてあった、みんなで一緒だからできたというのは「チーム力」というか、そんなところから由来する力になるのだと思います。みんなから元気をもらい、みんなに還元できますので。この講義を通じて学んだことを活かして、学部、大学院、社会人としての活躍を期待しています。もちろん、投稿は可能ですから、ラボスタッフのオガタくんもたのしみにしていますので。
わたなべしるす




