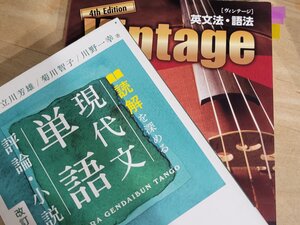初めての野菜栽培! part7(会:宮野 はるな)
2024年11月17日 (日)

こんにちは、宮野はるなです。
上の写真は紅葉がきれいだったので撮ったものです。最近葉っぱが赤や黄色に色づいてきて秋を感じるような景色になってきました。今週は比較的暖かくて最高気温が16度を上回っていました。
また、今週は定期考査2週間前になり本格的に勉強を始めました。来週はテスト一週間前なので記事をサボらないように頑張らないと、と思っていたのですが、中間発表のお知らせを見てそんな呑気なことを言ってはいられないと思いました。与えられている10日間を大切にして中間発表の記事の作成をしていきたいと思います。テスト勉強も頑張ります。
野菜栽培
さて、野菜栽培についてです。
播種から47日目です。
少し葉がしおれているようにみえました。そのため、水をいつもよりも多くやりました。その数時間後、葉を見てみたら元気になっていたので良かったです。
 根本の赤いところは直径1.5cm程になりました。先週から0.5cm大きくなりました。収穫は直径2〜3cmがベストなので来週か再来週にはできるのではないかと楽しみにしています。
根本の赤いところは直径1.5cm程になりました。先週から0.5cm大きくなりました。収穫は直径2〜3cmがベストなので来週か再来週にはできるのではないかと楽しみにしています。
そして今週一番の大きな収穫はアオムシがいなくなったことです!先週除去したおかげなのか、オルトランのおかげなのか、寒さのおかげなのか原因は不明なのですが確認した限りアオムシがいなくなっていました。三週間ほど悩んでいたアオムシから開放されるのか、?と思うととても嬉しいです。
播種から47日目です。
20:24 14℃
ラボスタッフさんのコメントで教えていただいた、追肥を行いました。肥料のやり方については同じハツカダイコンを育てている金濱さんを参考にして行いました。まず、鉢の縁に近い場所に10粒×4か所肥料を置きました。また、少し水をやった方が肥料が植物に届きやすいとのことだったので、水をやりました。
オルトラン粒剤ですが、スタッフさんのコメントを見て安心しました。ハツカダイコンを安全に食べれるのか不安でしたが必ず環境中で分解されるような化合物に設計されているとの事なので良かったです。
次回も引き続きハツカダイコンの栽培に努めていきたいです。
コメント
宮野さんこんにちは
のっけから「定期考査」なるワードに驚きました。いやあ、ここで聞くのでなければ、こちらはひょっとして残り一生聞くことがなかったかもしれません。ある種懐かしさを感じるフレーズです。
中間発表がその時期に重なってしまったのは、不運といえばそうなのですが...... 逆に定期考査一週間前に準備を始めているのが凄いですね!
勉強について何も言える立場でもないし、柄でもないのですが、定期考査は楽しみではないでしょうか。スポーツでも練習ばかりでは面白くない、試合に出て勝負が面白いと思います。また、定期考査は試験用紙が自動的に出てくるのではありません。誰かが作っているのです。だから試験用紙という紙との勝負ではなく、それを作った人との勝負になります。まるで将棋のように真剣勝負、いいでしょう。
更に言えば、今学んでいる教科書はそもそも面白いものです。倫理や世界史はもとより、国語も、化学も、ただ読めば楽しい読み物です。
さてさて本題の植物栽培の方は順調のようです。きちんと観察して管理にフィードバックしているのがポイント高いですね。例えば植物が萎れているようなら、水をしっかり与える、といったように。
管理面において、追肥を行ったとのこと、写真では非常に適切だと思います。追肥は行った日付けを覚えておき、10日ごと繰り返すのがいいですね。ついつい日付けを忘れがちになります。
そして肝心の成長度合いについて、この時期に1.5㎝まで肥大していることも驚きです。管理が良かったことに加え、最初のスタートが早かったこと、自宅栽培なので日照が取りやすかったこと、会津が仙台よりも日中気温が高かったこと、という理由があったのでしょう。ともあれ12月中にハツカダイコン収穫は歴代受講生の中でもトップランクの早さだと思います。こちらにとっても非常に大きな知見になります。仙台以外の地で行うことは滅多にないことですし......
最後に農薬について、前回はあまり詳しく書きませんでしたが、最近の農薬は非常に考えられて作られています。逆にいえば、昔の農薬は環境中において分解性の悪いものがありました。ベンゼン環に単純に塩素をくっつけたものだとか。
最近の農薬は生物分解性(環境中微生物の代謝経路に紛れ込んで分解される)の他にも、化学分解性(わざとエステル結合などのゆるい部分をつくっておき、光分解、加水分解されやすくする)なども考慮されています。最も違うのは生物の排泄性かもしれません。生物から排泄されないと蓄積され、更に食物連鎖によって生物濃縮がかかってしまいます。そうされないためには、抱合体排泄などの排泄性を考えなくてはいけません。
なかなかややこしい話ですが、化学でエステル結合やアミド結合などを習っているのではないでしょうか。それは、実は生活に密接に結びつくもので、いや本当に面白いものですよ!
ではまた、投稿を楽しくお待ちします。
この写真いいでしょう。巨大化しすぎてネコトイレに入らないうちのネコです!
ラボスタッフ・オガタ