【出前講義】仙台市立七北田小学校 NSP 4年生「ヘチマとそのなかまたち--実は、たくさんの仲間がいます--」(10/20, 27追記)
2015年10月20日 (火)
午前中に続いて、午後からは4年生。昨日の木町通小学校と同じテーマ。4年生では、ヘチマを育てるわけですが、今年は、作付けというか、栽培が苦労されたとか。。。春先は確かに天候不順だったような。そんな関係でしょうか。種播きから、栽培を最後まできちんとしたと言うことを覚えている児童の方が少なかったような。それでも準備頂いたヘチマは、小さいのから発達ステージにそって。よくできていました。できたら、そのままにして、乾燥させるのもよいのではと思ったくらいで。
 ウリ科のヘチマ(Luffa cylindrica)、カボチャ(Cucurbita maxima)、メロン(Cucumis melo)、キュウリ(Cucumis sativus)、ゴーヤ(Momordica charantia)、スイカ(Citrullus lanatus)を比べるというのが、講義のテーマ。せっかくなので、この前の文章の作物名の後ろのが、いわゆる学名。属名と種名になります。
ウリ科のヘチマ(Luffa cylindrica)、カボチャ(Cucurbita maxima)、メロン(Cucumis melo)、キュウリ(Cucumis sativus)、ゴーヤ(Momordica charantia)、スイカ(Citrullus lanatus)を比べるというのが、講義のテーマ。せっかくなので、この前の文章の作物名の後ろのが、いわゆる学名。属名と種名になります。
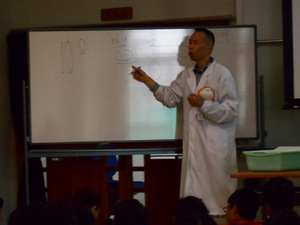 この記事を書くのに、久しぶりに調べて、ゴーヤは、ツルレイシとあって、そうだなと。キュウリとメロンのたねは似ています。それを説明したとき、属名、種 名を説明したのは、メロンとキュウリだけ。せっかくなので。また、果実の縦横比がちがうだけで、ウリ科は、縦長から、横長まで、色々な形態のものがある と。スーパーで是非、観察して下さい。では、横断面の特徴は。ということで、実際の果実の発達段階にそって、横断面を見ると、メロンのように、種が入ると ころ、loculeと言いますが、心皮だったような。それが3つあるのが特徴というのが、よくわかるのでは。大きくなると、ずいぶんはっきりしていたのを 観察してもらえたのでは。
この記事を書くのに、久しぶりに調べて、ゴーヤは、ツルレイシとあって、そうだなと。キュウリとメロンのたねは似ています。それを説明したとき、属名、種 名を説明したのは、メロンとキュウリだけ。せっかくなので。また、果実の縦横比がちがうだけで、ウリ科は、縦長から、横長まで、色々な形態のものがある と。スーパーで是非、観察して下さい。では、横断面の特徴は。ということで、実際の果実の発達段階にそって、横断面を見ると、メロンのように、種が入ると ころ、loculeと言いますが、心皮だったような。それが3つあるのが特徴というのが、よくわかるのでは。大きくなると、ずいぶんはっきりしていたのを 観察してもらえたのでは。

 また、いつも話をしますが、メロンのTの蔓が残る原因というか、その仕掛け。この前、市内の八百屋さんというか、果物屋さんで、大きなTの蔓を見かけたときは、高いのだろうと思ってみたのを思い出しつつ。ぜひ、Tのメロンを食べるようにしてみて下さい。味が違いますから。
また、いつも話をしますが、メロンのTの蔓が残る原因というか、その仕掛け。この前、市内の八百屋さんというか、果物屋さんで、大きなTの蔓を見かけたときは、高いのだろうと思ってみたのを思い出しつつ。ぜひ、Tのメロンを食べるようにしてみて下さい。味が違いますから。
 花の特徴で説明を忘れましたが、いずれも黄色。白は、ユウガオ、つまり、カンピョウ。位ではないかなと。。。ウリの仲間を集めてみるだけでも、こんなに多様性に富んでいます。他の科、バラ科、ナス科、アブラナ科など、是非、調べてみて下さいと言うことで。。。
花の特徴で説明を忘れましたが、いずれも黄色。白は、ユウガオ、つまり、カンピョウ。位ではないかなと。。。ウリの仲間を集めてみるだけでも、こんなに多様性に富んでいます。他の科、バラ科、ナス科、アブラナ科など、是非、調べてみて下さいと言うことで。。。
 最後になりましたが、4年生の担任の先生方、理科専科の福嶋先生、ありがとうございました。渡辺の時間の関係で、ゆっくり校長先生などとお話しができず。次回は、年明けになりますが。。。6年生が立派になったのを楽しみにして。。。
最後になりましたが、4年生の担任の先生方、理科専科の福嶋先生、ありがとうございました。渡辺の時間の関係で、ゆっくり校長先生などとお話しができず。次回は、年明けになりますが。。。6年生が立派になったのを楽しみにして。。。
わたなべしるす
PS. 講義で忘れていました。終わったあとに、学校の「ヘチマ」を食べるのはよくないというか、食用ではないので。繊維質が強くて。沖縄で栽培しているのは、食用のヘチマ。なので、食べることは、できます。食べるときは、必ず、おうちで栽培しましょう。という説明を忘れていました。
PS.のPS. 10/27(火), 21:20。七北田小学校のHPに当日の記事を見つけました。当日の夕方には記事がuploadされていたのですが、こちらがばたばたしており、気がつかず、失礼しました。

