【農学部FD】「双方向型授業のあり方を考える--はじめたきっかけ、大学教育への展開例から--」講師(3/7)
2019年3月11日 (月)
この記事を書いているのは、週明けの月曜日。通常であれば、講義が終わってすぐに、対応するところが、。。。先週の気温の上下動の影響なのか、体調不良で。週末を挟んでの3月11日に。。震災のことはまた、別に記すとして。。。先週の木曜日、3/7には、昨年の5月半ばくらいだったでしょうか。図書館との連携による「大学生のレポート作成入門」の講義のつながりで、農学分館長の藤井先生をご紹介いただき、その後の、数回の打合せ、mailでのやりとりを経て、遅くなったのですが、年度末に無事、FDとして開催に。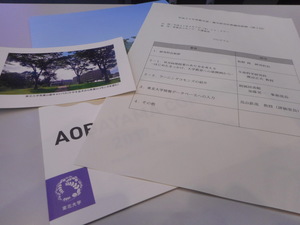
 最初に、農学部長の牧野先生から、渡辺の紹介を。PCPの編集員として、ご一緒したことなど、過分な紹介に穴があれば、入りたいくらいで。。。何よりも、講義をする半分近くの方々を存じ上げていることもあって。。。講義で取り上げたのは、最近大学でも言われるようになりつつある「双方向型授業」。渡辺の実践例で言えば、基礎ゼミ、展開ゼミでのwebを使った双方向公開型のものが、他の講義では余り行われてないだろうということで、その取組に至った経緯、実施例、この取組から見えてきたポイントなどを、整理しながら、結果として、総長教育賞などを頂けたことも。。。。webを使った双方向公開型と言うことは、この講義だけでなく、他の講義にも応用できるのではと言うことを。何よりも、渡辺は行っていない、昔で言う学部(教養部でなく)の講義を行っておられるので、釈迦に説法のような気がしたのですが、これからの講義をされる上での参考になればと。
最初に、農学部長の牧野先生から、渡辺の紹介を。PCPの編集員として、ご一緒したことなど、過分な紹介に穴があれば、入りたいくらいで。。。何よりも、講義をする半分近くの方々を存じ上げていることもあって。。。講義で取り上げたのは、最近大学でも言われるようになりつつある「双方向型授業」。渡辺の実践例で言えば、基礎ゼミ、展開ゼミでのwebを使った双方向公開型のものが、他の講義では余り行われてないだろうということで、その取組に至った経緯、実施例、この取組から見えてきたポイントなどを、整理しながら、結果として、総長教育賞などを頂けたことも。。。。webを使った双方向公開型と言うことは、この講義だけでなく、他の講義にも応用できるのではと言うことを。何よりも、渡辺は行っていない、昔で言う学部(教養部でなく)の講義を行っておられるので、釈迦に説法のような気がしたのですが、これからの講義をされる上での参考になればと。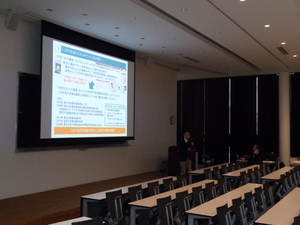
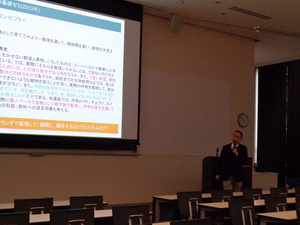
 講義の最後にも少し紹介した「ラーニングコモンズ」の紹介と言うことで、図書館の会議でお世話になっている加藤事務部長から。片平にはこれだけのスペースがなく、これがあれば、いろいろと使い勝手があるのだがと。。。。最後になりましたが、この企画を頂きました、農学分館長・藤井先生、pptを作り上げるまでの議論の時間を頂きました農学分館の方々をはじめ、関係の先生方に、お礼を申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい形で、コラボできればと思っております。よろしくお願いいたします。
講義の最後にも少し紹介した「ラーニングコモンズ」の紹介と言うことで、図書館の会議でお世話になっている加藤事務部長から。片平にはこれだけのスペースがなく、これがあれば、いろいろと使い勝手があるのだがと。。。。最後になりましたが、この企画を頂きました、農学分館長・藤井先生、pptを作り上げるまでの議論の時間を頂きました農学分館の方々をはじめ、関係の先生方に、お礼を申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい形で、コラボできればと思っております。よろしくお願いいたします。

わたなべしるす
PS. 翌日の3/8(金)には、夏に行っている河北新報社、東京エレクトロンとのコラボ企画の出前講義、みやぎ県民大学でご一緒していた金研・松岡先生の最終講義。ところが、こちらがdownして、午前中に少しばかりの議論の時間を頂いたくらいでしか、お目にかかることができず、。。4月からも近くで研究を続けると言うことから、また伺うことができればと思いますので。よろしくお願いいたします。

