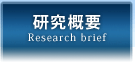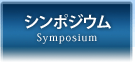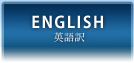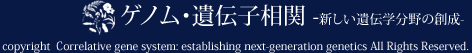文部科学省科学研究費補助金「新学術領域研究」
新学術領域|ゲノム・遺伝子相関
月別アーカイブ
計画研究班別アーカイブ
公募研究班別アーカイブ
旧公募研究班別アーカイブ
「研究経過報告」内を検索
タンパク質の合成(翻訳)は、メッセンジャーRNA(mRNA)のリボソームによる認識によっておこります。原核生物では、mRNAの5'の非翻訳領域にあるシグナル配列(SD配列)が、リボソームの小サブユニットのRNAの3'端(アンチSD配列、コアモチーフ3'CCUCC) と相補的な塩基対を作る、SD(Shine-Dalgarno)相互作用が起きます。
私たちは、藍藻(シアノバクテリア)由来の内部共生体が葉緑体などの色素体に進化する過程で、この相互作用がどうなったかを調べました。SD相互作用の消失が、緑藻 、ユーグレナ藻、アピコンプレックス門の色素体で、並行して起きていました。それらの色素体ゲノムの著しい縮小と関係するのでしょう。
古典的な SD 相互作用 (3′CCUCC/5′GGAGG (rRNA/mRNA)) が、 変則的な SD 相互作用 (3′CCCU/5′GGGA あるいは 3′CUUCC/5′GAAGG) にとりかわっている場合が、緑藻とユーグレナ藻で、発見されました。それは、rRNA 側のモチーフ配列と mRNA側のシグナル配列の双方の、足並みを揃えた変化によって起きていました(図:ユーグレナ藻)。

rRNAとmRNAのこのような共進化は、 遺伝情報発現のしくみの予想外な進化的可塑性を示しています。
Kyungtaek Lim, Ichizo Kobayashi, and Kenta Nakai. Alterations in rRNA-mRNA interaction during plastid evolution. Molecular Biology and Evolution. (2014) doi: 10.1093/molbev/msu120 [Journal]
研究成果がGGS(Genes Genet. Syst.)に掲載されました。 生殖は雌雄の異なるゲノムが相互作用するモデル的な系といえます。そのために植物の場合、雄性配偶子を有している花粉が発芽し、花粉管伸長が重要となります。今回は、花粉管伸長に機能しているだろうことは想定されていた、アクチンフィラメント(AF)とアクチン結合タンパク質(ABP)について、ABPの中でも注目度が低かったLIMタンパク質の機能を花粉管伸長で機能解析をしました。シロイヌナズナゲノムには、PLIM2の遺伝子が3つに重複しており、その中でも、生殖器官で特異的に発現が観察されたAtPLIM2a, AtPLIM2cの機能抑制系統を作出したところ、抑制系統では、花粉管伸長速度が57%に低下していました。この結果として、鞘基部の結実率が野生型に比べて低下するという現象を見いだしました。
また、本稿はその成果が評価されGGS 5号の表紙に選ばれました。Open accessですので、ぜひ、ご一覧頂ければ、幸いです。  Demonstration in vivo of the role of Arabidopsis PLIM2 actin-binding proteins during pollination
Demonstration in vivo of the role of Arabidopsis PLIM2 actin-binding proteins during pollination
Sudo, K., Park, J.-I., Sakzono, S., Masuko-Suzuki, H., Osaka, M., Kawagishi, M., Fujita, K., Fujita, K., Maruoka, M., Nanjo, H., Suzuki, G., Suwabe, K., and Watanabe, M.
Genes Genet. Syst. (2013) 88: 279-287 .
(URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/ggs/88/5/88_279/_article)
わたなべしるす
PS. 渡辺の研究室HPに関連記事があります。あわせてご覧ください。
4/5(土)は遺伝研の一般公開でした。天候にも恵まれ桜もきれいで大変良かったです。日頃のゲノム遺伝子相関の研究成果について吉田研究員と分担で説明させて頂きました。一般の方々に少しでも我々の研究内容が伝わっていれば幸いです。