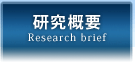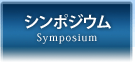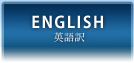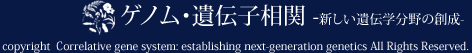文部科学省科学研究費補助金「新学術領域研究」
新学術領域|ゲノム・遺伝子相関
月別アーカイブ
計画研究班別アーカイブ
公募研究班別アーカイブ
旧公募研究班別アーカイブ
「研究経過報告」内を検索
班員の東北大学渡辺正夫教授が平成25年度野依科学奨励賞受賞(受賞タイトル:双方向交流を通じた新たな出前講義の方向性の試みと実践~児童・生徒からの手紙への返事と電子媒体活用による出前講義~)を受賞しました。授賞式は、3/25(木)に国立科学博物館で執り行われます。
野依科学奨励賞は、2001年ノーベル化学賞を受賞された野依良治博士の協力を得て、2002年度より、子どもたちの優れた学習・探究活動と子どもたちの科学する心を育てるために、優れた実践活動を行っている教員や科学教育指導者に対して、その功をたたえることを目的として創設されたものです。これまでのアウトリーチ活動が評価されたものであり、本領域の次世代育成にも貢献できたのではと思っております。
 この賞を励みとして、これからも研究教育活動と並行して、アウトリーチ活動を実践し、社会貢献ができる領域であるように努力したいと思います。
この賞を励みとして、これからも研究教育活動と並行して、アウトリーチ活動を実践し、社会貢献ができる領域であるように努力したいと思います。
わたなべしるす
PS. 渡辺の研究室のHPにも関連記事が出ております。合わせてご覧頂ければ、幸いです。
制限酵素は、特定のDNA配列の塩基がメチル化されていないときに、DNAを切断します。DNAを切るはさみとして、生命科学とバイオテクノロジーに大きな役割を果たしてきました。生命活動では、エピジェネティクスによる自己と非自己の区別によって遺伝的隔離による進化に寄与しています。
これまで知られている 制限酵素は全て、DNAのヌクレオチド単位を繋ぐリン酸ジエステル結合を加水分解します。私たちは、メチル化標的の塩基を切り出す新しい型の制限酵素を発見しました。
このような塩基切り出し酵素(DNAグリコシラーゼ)は、これまでDNA塩基損傷の修復で知られていましたが、最近動物細胞でDNAの脱メチル化に関わることが示されています。私たちの発見は、DNAメチル化によるエピジェネティクスの過程を繋げ、遺伝過程の理解を拡げるものです。
「ATGCという塩基配列で書かれたゲノム情報が、遺伝と進化の単位」というのが現在の生命観です。これに対して、「エピゲノム情報こそが、遺伝と進化の単位」ではないかと、私たちは考えました。エピゲノム情報の中でも、塩基配列に特異的な塩基メチル化が、遺伝子発現と適応的形質を変える可能性に注目しました。
この「エピゲノム駆動進化仮説」をテストするために、ピロリ菌5株について、PacBio社の 一分子リアルタイムシーケンシング技術によって、ゲノム全域でメチル化塩基を一塩基の分解能で検出しました。(ピロリ菌と、その仲間は、ヒトと動物に胃がんなどの病気を起こす単細胞の細菌です。)
メチル化の配列特異性を担う遺伝子が、遺伝子内ドメイン配列移動(DoMo)という再編機構によって、メチル化配列を切り替えている事を証明しました。さらに、メチル化配列特異性遺伝子の有無が遺伝子発現に影響することを、トランスクリプトーム解析(IlluminaマシンによるRNA-seq)で、示しました。
本成果は「生物がエピゲノム状態を作り替えることで進化する」という「エピゲノム駆動進化」仮説を支持します。さらに、エピゲノムを標的とする「エピゲノム育種」への道を開きます。
Furuta,
Y. et al. PLoS Genetics, in press.
今回の成果は、東北大・東谷教授との共同研究で、計画班の松岡班との共同研究でもあります。東北地方は今でこそ、冷害という言葉が重くのしかかることはないですが、それでも沿岸部など、イネの作付けができないところもあります。そうした低温での花粉成熟を遺伝子組換えでなく助けることはできないかという画期的な手法です。植物ホルモン・ジベレリンと糖を複合投与することで、稔性が回復することを発見し、その原因を突き止めたものです。「生殖」と「低温適応」という環境との相関のモデルになるようにできればと思います。
Reduction of gibberellin by low temperature disrupts pollen development in rice.
Sakata, T., Oda, S., Tsunaga, Y., Kawagishi-Kobayashi, M., Aya, K., Saeki, K., Endo, T., Nagano, K., Kojima, M., Sakakibara, H., Watanabe, M., Matsuoka, M., and Higashitani, A.
Plant Physiol., in press, (2014)
論文は、open acessなpdfになっております。まだ、版組がされていないですが、最終的なvol., pageが決まりましたら、情報を更新します。

わたなべしるす
PS. 渡辺の研究室HPに関連記事があります。あわせてご覧ください。