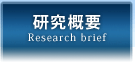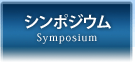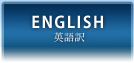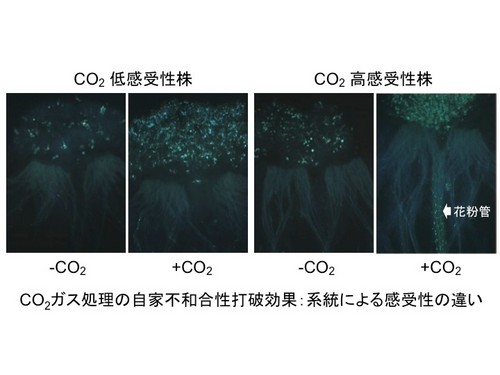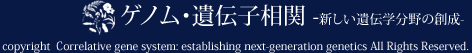文部科学省科学研究費補助金「新学術領域研究」
新学術領域|ゲノム・遺伝子相関
月別アーカイブ
計画研究班別アーカイブ
公募研究班別アーカイブ
旧公募研究班別アーカイブ
「研究経過報告」内を検索
アウトリーチ活動
リクルートの運営する無料ウェブマガジン「ゼクシイ」で、山元が男女の相性と遺伝子型(HLA)が関係するという実験について話題提供をしました。
出典:
http://zexy.net/contents/lovenews/article.php?d=20131022

図:山元の話を載せた「ゼクシイ」の1ページ
研究成果をThe Plant Journal 12月号に出版しました(Sekine D., et al. Plant J. 2013)。
多くの被子植物では、異なる種や異なる倍数性種を用いて掛け合わせをした場合(それぞれ種間交雑と倍数体間交雑と呼びます)、胚乳の発生異常が原因で生殖隔離がおこることが知られています。両者はともに、父由来と母由来のゲノムの機能の一般性が導き出されるほど、胚乳でおこる発生の亢進や抑制の表現型が似通っているため、両者の違いはこれまでの研究でははっきりしませんでした。しかしながら、種間交雑では「異なるゲノム配列の出会い」、倍数体間交雑では「異なるゲノム量の出会い」と表現することが可能で、それぞれの生殖隔離の分子機構は異なると考えられます。 発表した論文では、2倍体イネと4倍体イネを用いた倍数体間交雑を行い、交雑種子の胚乳発生を解析し、先行研究で行われた種間交雑の結果 (Ishikawa & Ohnishi et al., 2011, The Plant Journal)との比較を行いました。受粉後7日目の発生段階において、2倍体の自殖種子と比較すると、母親4倍体-父親2倍体の組み合わせでは胚乳の著しい萎縮が観察されました(挿絵右側写真)。一方で、母親2倍体-父親4倍体の場合は、肥大した子房と透明な液体上の胚乳が観察されました(挿絵右側写真)。そこで、倍数体間交雑での胚乳発生を詳細に解析し、母親4倍体-父親2倍体の組み合わせでは、多核体期から細胞化を経て細胞分裂期への発生進行が早まると共に胚乳核数の減少が見られることを明らかにしました(挿絵)。一方で、母親2倍体-父親4倍体の組み合わせでは、発生進行が著しく遅れると共に早いステージでの胚乳核数の増大が見られました。イネの種間交雑においては、同じように、組み合わせに応じて発生の進行が、著しく早まったり遅れたりすることが観察されています。しかしながら、種間交雑では、胚乳核の分裂頻度は組み合わせが変わっても差がないことが判っています(Ishikawa & Ohnishi et al., 2011)。したがって、本研究では、倍数体間と種間交雑の違いを理解することに成功しました。これらの研究成果が、今後の展開を通じて、ゲノム遺伝子相関の共通原理を理解する一助になることを期待しています。