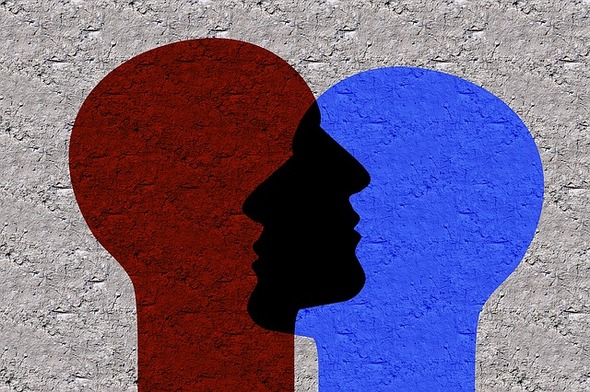 こんにちは。青森県立青森東高校2年の加藤優喜です。卵ブログ3回目の投稿になります。他の方々が第3回講義のブログを投稿されている中で、しれっと第2回講義のブログを書いております。ほんとにすみません。
こんにちは。青森県立青森東高校2年の加藤優喜です。卵ブログ3回目の投稿になります。他の方々が第3回講義のブログを投稿されている中で、しれっと第2回講義のブログを書いております。ほんとにすみません。
講義の感想
さて、今回のブログは渡辺正夫先生による「進化論を唱えたダーウィンも注目した高等植物の自家不和合性」の講義についてです。私たちに身近な植物について知らなかったことが次から次へと出てきて、大変興味深いお話でした。講義のテーマは植物ですが、進化史や哲学ともリンクする内容が多い講義だったように感じます。私自身、人類の進化について興味があり、「なぜヒトは笑うのか」というテーマに関心があるので、自分の興味につながることが盛り沢山な講義でありました。
自家不和合性とは?
自家不和合性とは、簡単に言えば「他殖性植物が自分の花粉をブロックするしくみ」です。他殖性植物とは、他の個体の花粉でしか受粉できない植物のことで、トウモロコシやアブラナ科の植物などが含まれます。これに対して、自殖性植物は自家受粉を行う植物で、イネやアサガオが含まれます。
なぜ自家不和合性があるのか?
自家不和合性によって得られる最大の利点は、種の多様性が生まれることです。自分と異なる個体と交配が行われるため、より幅広い遺伝子が生まれやすいのは直感的にわかりやすい話です。
トマトは人類の農耕によって自家不和合性を失った?
私たちに身近なトマト。実はもともと自家不和合性をもっていたのに、人類の農耕によって自家和合性になってしまったそうなんです。簡単に言えば、今まで自家受粉NGだったのに、自家受粉OKになったということですね。これには自家不和合性をもつ植物のデメリットとも言える点が関係しています。自家不和合性を持つ植物のデメリットは、悪天候や虫が花粉を運んでくれないといった環境になると、生殖が行われないという点です。このデメリットによって、人間がトマトを栽培するために使うタネは、自動的に自家和合性になっていきます。条件が整わずタネができない年に生き残るトマトは自家和合性だからです。結果的に人間が自家不和合性のトマトを排除したという言い方もできますね。
自然に自家不和合性を失ったイロイヌナズナ
トマトは人類の農耕によって自家不和合性を失いましたが、進化の過程で自然に自家不和合性を失った植物も存在します。それがシロイヌナズナです。このような植物も存在することから、他殖性植物が自家不和合性を持つか持たないかは、その植物における種の多様性を失うリスクと、他殖条件を満たさない環境で生殖が行われないリスクとの兼ね合いで決まるのではないかと考えました。その植物にとって、どっちの危険度がより高いかによって自家不和合性か否かが決まるのではないかということです。
自己とは一体何者か?
講義の中で、渡辺先生が興味深いお話をされていたのでメモしておきます。
「不和合性についての研究は、雑種をつくるサイエンスであるのと同時に、自己とは一体何者であるのかというサイエンスでもある。」
なぜこのお話が印象に残っているのかと言いますと、私が先日読んだ鈴木祐氏による「無(最高の状態)」という本とのつながりを感じたからです。この本は、「自己とは一体何者であるのか?」という哲学的な問いを神経科学や脳科学の側面から掘り下げながら、自己がもたらす苦しみに対処していく方法について書かれた本です。この本の中では、自己についてこのように説明がされています。
「"わたし"とは生命の維持機能がもたらす明滅である」
文面だけ見るとなんのことやら...という感じですが、噛み砕くと「自己とは私たちの身を守るための防衛ツールにすぎないもので、無くなったり変わったりしない絶対の自分など存在しないのだ!」ということです。後半部分の内容はさておき、講義とのつながりを感じたのは前半部分です。自己というものが身を守るための道具だということを植物に置き換えて考えてみると、植物が奇想天外な特徴や仕組みを持っている理由は、各々に種の生存という目的が根本としてあるためであると考えることができます。植物や私たち人間が持つ一つ一つの特徴は、どんな形で生命維持の働きをしているのかをより詳しく調査したいと感じました。次回のブログも読んでいただけると嬉しいです。それではまた。
投稿者:青森県立青森東高等学校







