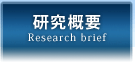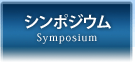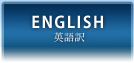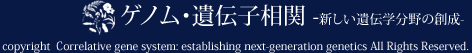文部科学省科学研究費補助金「新学術領域研究」
新学術領域|ゲノム・遺伝子相関
月別アーカイブ
計画研究班別アーカイブ
公募研究班別アーカイブ
旧公募研究班別アーカイブ
「研究経過報告」内を検索
【大阪教育大】鈴木班の記事を表示しています
科学研究費の申請書にも近年、実施が義務づけられている「国民との科学・技術対話」の推進。鈴木班でも、小中高への出前講義を通したアウトリーチ活動を広く展開し、国民へ科学・技術を還元します。
前々回が1月末まで、前回が昨年度のまとめでしたので、新年度4月から6月の第1四半期における研究分担者・渡辺のアウトリーチ活動をまとめておきます。詳しい内容は、研究室のHPに記してありますので、興味のある方は、ぜひ、以下のlinkをご覧ください。講義内容は、今回は小学校、高校、高校の先生方向けで、内容は植物の生殖に関わる講義、実験などです。
石川県立小松高等学校・特別講義・実験指導・文章表現指導(1, 2, 3, 4)
小松市立中海小学校・特別講義(1, 2)
福島県立磐城高等学校・特別講義・研究室訪問(1, 2)
和歌山市立名草小学校・特別講義
宮城県仙台第一高等学校・特別講義・研究室訪問(1, 2, 3)
石川県高等学校教育研究会生物部会研修会・特別講演
岩手県立釜石高等学校・文章表現指導
宮城県宮城第一高等学校・特別講義
仙台市立木町通小学校・特別講義
宮城県古川黎明高等学校・特別講義
仙台市立七北田小学校・特別講義
松山市立小野小学校・特別講義
愛媛県立松山南高等学校・特別講義
愛媛県立今治南高等学校・特別講義・実習
今治市立日高小学校・特別講義
香川県立観音寺第一高等学校・特別講義
埼玉県立浦和第一女子高等学校・実験実習
引き続き、社会貢献ができる領域であるように努力したいと思います。
わたなべしるす
研究面が評価され、新聞、テレビ報道につながることはこれまでも経験がありましたが、アウトリーチ活動で新聞報道はありましたが、テレビ取材を受けたのは、初めてのことでした。
5/11に、小松市立中海小学校・特別講義「花の不思議な世界--りんごの花からリンゴができるまで??--」ということで、受粉、受精、自家不和合性について、小学校5年生への講義を、北陸朝日放送の方で講義の最初から、最後まで取材頂き、当日の21時48分からのHABニューススカッシュに1minほどですが、講義風景、子供さんたちへの取材を織り交ぜてのニュースとなりました。テレビ取材が入っての講義はもちろん、初めて、ずいぶん緊張しましたが。。 今回は、ローカルニュースでしたが、次は、全国放送を目指して、精進したいと思いますので。是非、皆様にも見て頂きたいのですが、版権などあり、班会議など折を見て、見て頂くようにします。
今回は、ローカルニュースでしたが、次は、全国放送を目指して、精進したいと思いますので。是非、皆様にも見て頂きたいのですが、版権などあり、班会議など折を見て、見て頂くようにします。
わたなべしるす
PS. 翌5/12の北國新聞にも取り上げて頂きました。
大阪教育大学の鈴木です。
高大連携・SSHに関連して、4月2日(月)大阪教育大学柏原キャンパス・4月5日(木)同天王寺キャンパスにて、附属天王寺高校の生徒相手にシークエンス特別実習を行いました。
内容は、ゲノム・遺伝子に関連して、ホタルのミトコンドリア遺伝子の一部をPCR増幅し、それをダイレクトにシークエンスしたものを、インターネットで相同性検索にかけてハプロタイプを同定するもので、高校生のゲノム・遺伝子に関する理解が少しでも深まればと思い、実習・講義しました。附属天王寺高校の森中敏行先生には大変お世話になり、ありがとうございました。
科学研究費の申請書にも近年、実施が義務づけられている「国民との科学・技術対話」の推進。鈴木班でも、小中高への出前講義を通したアウトリーチ活動を広く展開し、国民へ科学・技術を還元します。
前々回が9月末まで、前回が1月末まででしたので、それ以降から、年度末の3月期末までの、研究分担者の渡辺のアウトリーチ活動をまとめておきます。詳しい内容は、研究室のHPに記してありますので、興味のある方は、ぜひ、以下のlinkをご覧ください。講義内容は、今回は高校で、内容は植物の生殖に関わる講義、実験などです。
愛媛県立今治南高等学校・特別講義・実習
宮城県宮城第一高等学校・特別講義・実験指導・研究室訪問(1, 2, 3, 4)
山形県立鶴岡南高等学校・特別講義・実験実習
この領域が発足して、今年度の実績は、アウトリーチ活動総数、73回。参加人数、4,914人。その中でレポートなどをいただき、その全員に手紙を返しましたが、その総数、2,384通。これ以外にも、mail、電話でのやりとりなどは、100回以上ありました。
来年度も引き続き、社会貢献ができる領域であるように努力したいと思います。
わたなべしるす
研究成果がPlant Cell Environ.に掲載されました。
今回の成果は、宮崎大・稲葉チームが統括し、鈴木班と寺内班がそれぞれの技術でサポートするという共同研究によるものです。研究材料はモデル生物でない「ザゼンソウ」という花器官が発熱するという特徴を持っています。この発熱分子メカニズムは他生物との比較から、核ゲノムと細胞質ゲノムの相互作用の結果であると考えられていますが、実態は不明です。この研究チームでは、以前から「寒冷地適応」、「生殖」、「細胞質・核ゲノムクロストーク」等をキーワードに共同研究を行い、形態的特徴などいくつかのことを明らかにしてきました。今回の論文発表では、発熱部位である生殖器官の遺伝子発現を網羅的に行い、発熱に係わる遺伝子を探索し、これからの発熱現象への分子基盤ができたと思っています。 The gene expression landscape of thermogenic skunk cabbage suggests critical roles for mitochondrial and vacuolar metabolic pathways in the regulation of thermogenesis.
The gene expression landscape of thermogenic skunk cabbage suggests critical roles for mitochondrial and vacuolar metabolic pathways in the regulation of thermogenesis.
Ito-Inaba, Y., Hida, Y., Matsumura, H., Masuko, H., Yazu, F., Terauchi, R., Watanabe, M., and Inaba, T.
Plant Cell Environ., 35: 554-566.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3040.2011.02435.x/abstract
この5年間で、分子メカニズムの一端が明らかにできるのではと思っています。
わたなべしるす
PS. 稲葉チーム、渡辺の研究室HPに関連記事があります。あわせてご覧ください。