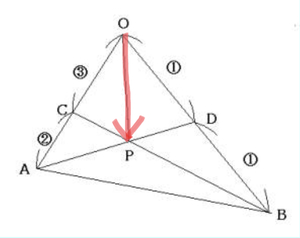 そういえば前回の量子アニーリングの講義で、大関先生が「理系の人こそ問題文を理解するために国語力が必要だ」とおっしゃっていましたね。このことにもつながってくると思うんです。「与えられた限られた時間の中で問題文と誘導文からどのような方法で問題を解かせようとしているのかを即座に読み解き、与えられた誘導文と文脈が合うように順序よく組み立てて説明する」という力が今後生きていく上で必要となってきているということです。こりゃまた大変な時代に生まれてきたもんだなぁ...。
では話を進路研修の下りまで戻します。ここでも言えるのは、理系の人には「コロナの感染が怖いから、行かない。行くとしても県内だけだ」という一辺倒な考えよりも、「コロナが落ち着いていたらここ、少し増加傾向ならここ、急増していたらここ」という「多辺倒」な考えが必要だということです。つまり、理系の人こそ突然の変化にも対応できるようにオールマイティーでなければならないということです。
なのでこれからは僕も、まずは問題を解くときに、「この問題にはこの解き方が一番に決まっている」と一辺倒に考えるのではなく、「今回はこの解き方で解けたけど、実はこの法則も使えるんじゃないか?」というように「多辺倒」に考えていこうと思います。
さあ、進路研修も終わったし、次は期末テストだ!(あぁ、岩手から帰ってこなきゃよかった...。課題どうしよ...。)
そういえば前回の量子アニーリングの講義で、大関先生が「理系の人こそ問題文を理解するために国語力が必要だ」とおっしゃっていましたね。このことにもつながってくると思うんです。「与えられた限られた時間の中で問題文と誘導文からどのような方法で問題を解かせようとしているのかを即座に読み解き、与えられた誘導文と文脈が合うように順序よく組み立てて説明する」という力が今後生きていく上で必要となってきているということです。こりゃまた大変な時代に生まれてきたもんだなぁ...。
では話を進路研修の下りまで戻します。ここでも言えるのは、理系の人には「コロナの感染が怖いから、行かない。行くとしても県内だけだ」という一辺倒な考えよりも、「コロナが落ち着いていたらここ、少し増加傾向ならここ、急増していたらここ」という「多辺倒」な考えが必要だということです。つまり、理系の人こそ突然の変化にも対応できるようにオールマイティーでなければならないということです。
なのでこれからは僕も、まずは問題を解くときに、「この問題にはこの解き方が一番に決まっている」と一辺倒に考えるのではなく、「今回はこの解き方で解けたけど、実はこの法則も使えるんじゃないか?」というように「多辺倒」に考えていこうと思います。
さあ、進路研修も終わったし、次は期末テストだ!(あぁ、岩手から帰ってこなきゃよかった...。課題どうしよ...。)
投稿者:山形県立鶴岡南高等学校







