雪の便りが聞かれる季節となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。仙台青陵中等教育学校4年只野佑之介です。先日青葉山キャンパスにクマが出没して話題になっていましたが、我が家でも半月ほど前、庭の柿の実が一晩で無くなっていました... 今年は森で木の実が不作だそうなので、飢えをしのごうと動物たちも必死になっているのかもしれませんね。
今回は、第三回と第四回の特別講義の感想をまとめて書かせていただきたいと思います。
<第三回特別講義>
①大関真之先生「量子アニーリングと未来の情報科学」
大関先生の講義では、量子アニーリングが、様々な問題を解決して社会を豊かにするためにどう使われているのかや、理科や数学の学習に対する姿勢、将来へのアドバイス等、様々なことを教えていただきました。私が最も驚いたのは、量子アニーリングを活用すれば「二次関数で世界を救う」ことができるという点です。大関先生は、組み合わせ最適化問題が物流・製造・農業・防災等の現代社会を支えているとおっしゃっていました。世の中において組み合わせが大切なのはなんとなく分かっていましたが、先生のお話を聞き、頭の中を整理することができました。そして、二次関数を用いればその問題をパズルのように解くことができると知り、今自分が学習していることが世界を救うことにつながるのだと気づくことができました。
また、「世の中から文章題を見つけ出す」ことが大切だという言葉が印象に残りました。AIをはじめとした科学技術の開発により、従来の人間の仕事の多くが機械に肩代わりされている今、私たち人間に求められているものは、論理的に物事を判断し、課題そのものに気づくことができる力だということです。人間にしかできない仕事を成し遂げるために、幅広い分野の知識を身につけ、思考力や課題を的確に見極める力を高めることができるよう、しっかり学んでいきたいと思いました。
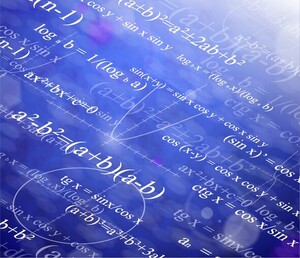
②堀井明先生「21世紀のがん医療~Precision Medicineと遺伝子医療~」
堀井先生の講義では、がんの発生の仕組みから、最先端の分子標的治療薬についてまで、詳しく教えていただきました。
がんは日本人の二人に一人がかかる身近な病気であるのにもかかわらず、その治療は身体的、精神的、経済的にもつらく厳しいものであると聞いています。ですから、医療技術の発展に伴い"one size fits all″型から‶personalized″型の治療ができるようになったことは、大きな進歩だと感じました。これまでは数が多い症例に合わせた治療を行っていたので、治療方法が合わない患者さんも少なからずいたと思います。細胞や臓器ではなく、遺伝子や分子を標的にした「分子標的治療薬」の開発により、個人に合わせた医療が展開され、よりきめ細かで一人ひとりに合った治療ができるようになったのは素晴らしいことだと思います。
しかし、‶personalized″型の医療が進んでいるといっても、個々の患者さんに合った治療薬を速やかに見つけることができなければ、苦しみから救うことはできません。ですから、がん遺伝子パネル検査の開発を進め、だれもが安価に利用できるようにすることで、迅速にクリティカルな治療を開始できるようになることが重要だと感じました。治療法の発達により、近い将来、がんがつらく苦しい病気でなくなることを強く願っています。
<第四回特別講義>
①滝澤博胤先生「化学反応の場を探る~マテリアル・デザインと新物質探索~」
滝澤先生の講義では、マイクロ波についてや、電子レンジ等の私たちが普段使っている物の仕組みについて詳しく知ることができ、大変勉強になりました。電子レンジはマイクロ波を用いて水分子を振動させて加熱するものだと認識していましたが、選択加熱・内部加熱・体積加熱・急速加熱といったマイクロ波の特徴を詳しく知ることができ、理解が深まりました。
また、マイクロ波の利用に限らず、化学反応のステージを変えることで、自然界の法則を超越して新しい物質を作ることができると学び、興味深く感じました。「ブレイクスルーは常に新物質・新材料から!」とスライドにもありましたが、永久磁石や超電導の開発を見てみると、確かに従来とは異なる物質を使用した時に、ブレイクスルーが起こっています。特に、硫化水素が超伝導体のブレイクスルーを起こしたことを知り、驚きました。いろいろな方法を用いて新たな材料を生み出す材料工学という分野は、とても創造的な学問だと感じました。
そして、大関先生の講義の感想にも書いたように、この講義でも、現在私たちが学習していることの大切さを実感することができました。動画で「新たな物質を作る」と聞き、どうやって物質同士を組み合わせるのか想像もつきませんでしたが、化学で習っている周期表にそのヒントが沢山散りばめられていると教えていただきました。「Chemistry=相性・調和によって引き出される効果」という言葉は、とても美しいと感じました。この言葉を忘れずに化学を学び、新しいハーモニーをつくり出せるようになれたらと思います。
②佐貫智行先生「次世代素粒子研究施設:国際リニアコライダー(ILC)計画」 佐貫先生の講義では、現在見つかっている素粒子についてその性質や動作まで詳しく解説してくださり、私の宇宙や素粒子に対する認識が変わりました。
まず驚いたのは、素粒子が現在17種類も見つかっており、それぞれに決まった役割があるということです。例えば、電子やアップクォーク、ダウンクォークは物質を作り、グルーオンは素粒子同士をくっつける役割を持っています。それぞれの素粒子が互いに違った役割を分担して、すべてのものを形作っているということに感動を覚えました。 また、宇宙の誕生や素粒子の謎に迫る研究についても、多くのことを学ばせていただきました。まず印象に残ったのは、「宇宙をつくる」という言葉です。宇宙の起源を知るために宇宙を見るのではなく宇宙をつくるという発想は、今まで考えたこともありませんでした。ILC国際研究所は、宇宙の誕生であるビッグバンを再現し、その謎を解き明かすための研究施設だそうです。地元に国際的な研究所ができ、将来そこから大発見が生まれるかもしれないと思うと胸が高鳴りました。
 <ミニ講義> 科学者の卵養成講座の2回をまたいで行われたミニ講義では、科学記事を読みこなすためのグループワークや、現在起きている環境問題についての討論・プレゼンテーションを行いました。はじめは上手くいくかどうか不安でしたが、グループの皆さんと活発に意見の共有・整理をすることができました。グループワークを通して強く思ったのは、異なる視点を持つ人と話すことで、意見をより深めることができるということです。討論を通して、アイデアをより一般化できたり、どんな人にも通じやすいように改善したりすることができたと思います。質の高い議論ができたのは、住む環境が違う人、違った経験や興味・関心を持っている人、自分にはないスキルを持った人など、ある意味タイプが違う人同士で集まることができたからだと感じました。いろいろな人の視点や考え方を吸収し、話し合い、共有できるのは、この講座ならではだと思います。科学者の卵としてこのような機会を活用させていただき、少しずつでも成長していきたいと思いました。
<ミニ講義> 科学者の卵養成講座の2回をまたいで行われたミニ講義では、科学記事を読みこなすためのグループワークや、現在起きている環境問題についての討論・プレゼンテーションを行いました。はじめは上手くいくかどうか不安でしたが、グループの皆さんと活発に意見の共有・整理をすることができました。グループワークを通して強く思ったのは、異なる視点を持つ人と話すことで、意見をより深めることができるということです。討論を通して、アイデアをより一般化できたり、どんな人にも通じやすいように改善したりすることができたと思います。質の高い議論ができたのは、住む環境が違う人、違った経験や興味・関心を持っている人、自分にはないスキルを持った人など、ある意味タイプが違う人同士で集まることができたからだと感じました。いろいろな人の視点や考え方を吸収し、話し合い、共有できるのは、この講座ならではだと思います。科学者の卵としてこのような機会を活用させていただき、少しずつでも成長していきたいと思いました。 追記:原因はわかりませんが、途中からこのページの文字が斜体になって公開されてしまうことがあるようです。申し訳ありません。
投稿者:仙台市立仙台青陵中等教育学校







