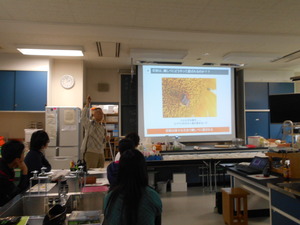お久しぶりです。M2の岡本です。
無事、M2になれました。今年度もよろしくお願いします。m(__)m
さて、もう1週間前になってしまいましたが、なべ研と菅野研合同でお花見をしました。
今年は暖冬でしかも4月にも関わらず、20℃近くの日が何日もあったので、
当日に桜がちゃんと残ってくれているかドキドキ、わくわく。
そんなドキドキをよそに気温はどんどん落ちていって、当日(11日)には最高気温が10℃に満たないほどに。さぶっ
セミナー室でぬくぬくと弁当を食べるという選択肢もありましたが、そこは「お花見」なので、外でやらないと意味がない!!
ってことで、菅野研の梶野とともに場所取りへ、Let's Go!!
何度もくじけそうになること(強風にブルーシートが遠くに飛ばされる、置石が重い・・・etc)がありましたが、
桜の木の下にブルーシートを置くことに成功。
置き終わったころには、ちょうどいい時間になっていたので、みんなをよんでいざ開始です。
去年の弁当も豪華だった記憶がありますが、今年も去年に負けず劣らず豪華!!
こんなに大きな有頭海老!!
今年のM1の女の子2人は写真に写るのと撮るのが好きらしく、何枚もカメラ目線をくれ、自分自身でも写真をパシャパシャ撮ってました。
とにかく元気。いいことです。
恒例の自己紹介をして(緊張してる張さん)、
今年は、就活でゆーたろーと菅野研の鈴村&佐藤がいなかったので、集合写真はまたの機会になりました。
全て片づけるまでがお花見です!!と言わんばかりにみんなで勢いよく片づけをして、今年のお花見は終わりました。
来年は暖かいところで。ぜひ。
P.S.
最近、学内にいるネコの写真を撮るのがマイブームになりつつある岡本ですが、
なにかの用事でプロ棟からスマホをいじりながら出てきたときに、
地面に何か茶色い物体がいる!!なんだーと近づいてみると、
君はヤモリ君じゃないか!!!久々に見ました。なんかいいことがありそうです。
ちなみに、イモリとヤモリの違い、イモリ両生類でヤモリが爬虫類ってこと以外にもわかりますか?
結構わからない人多いそうです。答えは内緒。
おしまい
M2 おかもと