雪が頻繁に降る2021年の冬。気温も氷点下の朝が多いような。ただ、降雪があっても、雪解けは1月頃よりも早いイメージ。地面は少しずつ春になっているのだろうと。そんな2月第3週。地震からの復旧に始まり、17日からは博士研究員の林さんが着任。よい方向になるように。と思っていた週末にかけて。
2/19(金):岩手県立盛岡第三高等学校・SRH発表会
コロナ禍を受けて、課題研究の口頭発表とポスター発表を2つに分けて。2.13の地震で仙台と一関間の新幹線がストップ。2/25から国公立大学入試試験もあるということへの影響でしょうか、前日の24日は速度制限などをかけながら、復旧されるとか。そんな状況を予測できたわけでなく、コロナ禍で拡散しないようにと言うことで、リモートでの参加をお願いしたのでしたが、リモート対策をお願いできていなければ、前日まで参加できるのか、頭を抱えた状態になったような。。。盛岡三高の先生方の迅速かつ的確な対応のおかげです。ありがとうございました。肝腎の発表会、午前中から14:00までの10課題について、リモートからでしたが、可能な限り質疑応答を。このような形での開催も十分可能なのだと。設定から当日の開催まで準備頂いた先生方に感謝です。ありがとうございました。
2/19(金):青森県立五所川原高等学校・特別講義「高校で課題研究が、大学・大学院での研究につながる」
14:00までの盛岡三高でのSRH発表会を終えて、急ぎ、五所川原高でのリモートでの出前講義。リモートのよさは、瞬時に移動ができるところ。講義のイントロは、2.13の地震から。青森・五所川原周辺はあまり揺れがなかったのか、東北新幹線が盛岡以南で止まっていることもあまり知られてないのは、少し残念。そんな世の中の変化に注意を払うこと、なぜ、そんなことが起きたのかにも気がつくきっかけになると。また、新幹線が止まっている状態でも、渡辺が講義をできたのは、先生方のリスクマネジメントのおかげだと。実験はもちろん、チャレンジも大事である一方で、しっかりとした実験計画を立てるというリスクマネジメントも大事なこと。あとから気がついて、忘れていた!!、というのはよくないと言うこと。そんなことをスタートに課題研究をなぜ行うのか、その重要性を様々な角度から。そんな課題研究の先には、自分自身の「キャリア形成」に繋げてほしいと。つまり、大学、社会人になっても、観察し、不思議に思って、考えることは大事なことですから。また、リスクマネジメントも忘れず、キャリア形成して下さいと。ありがとうございました。 前日には中村校長先生からmailを頂き、電話で情報交換。普段から自然を観察し、変化に気がつくこと。あらかじめ予測できることにはしっかり対応することなど、貴重な議論の時間でした。ありがとうございました。
前日には中村校長先生からmailを頂き、電話で情報交換。普段から自然を観察し、変化に気がつくこと。あらかじめ予測できることにはしっかり対応することなど、貴重な議論の時間でした。ありがとうございました。
2/20(土):福島県立福島高等学校・SSH生徒研究発表会・運営指導委員会
コロナ禍を踏まえて、宮城県からはリモートでの福島高校・SSH発表会、運営指導委員会に参加。さらに、新幹線は仙台と那須塩原間も23日まで2.13の地震で停止。福島高校も大きな被害を受けて、最初のformatを変更して、急ピッチの準備を頂いたとか。ただ、参加した限り、とてもよくできたシステムで、学校で発表を聞いて、質疑ができるのと変わらないレベル。大学も学ばないといけない状態のような・・・。研究発表会は、口頭発表、ポスター発表、ディベート決勝。ディベート決勝には適切な「エール」も。感動でした!!コロナ禍、震災被害からすぐの状態でしたが、充実したものでした。また、最後は、運営指導委員会。リモートからの座長もはじめてでしたが、おかげさまでスムーズに。あっという間の1日でした。ありがとうございました。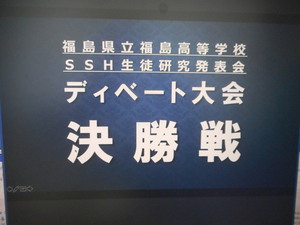
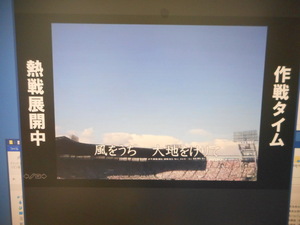 PS. 土曜日にもかかわらず、学内では何かの工事が。そこから聞こえる音がある種の警告音に聞こえて。。。2.13の地震後ということで、しばらく、音源が何なのかを探して、昼過ぎに発見。そんなものだとわかり、ほっとした訳ですが。周りに対して感度が上がっているのがよいことと解釈して。。。そんな週末でした。
PS. 土曜日にもかかわらず、学内では何かの工事が。そこから聞こえる音がある種の警告音に聞こえて。。。2.13の地震後ということで、しばらく、音源が何なのかを探して、昼過ぎに発見。そんなものだとわかり、ほっとした訳ですが。周りに対して感度が上がっているのがよいことと解釈して。。。そんな週末でした。
2/26(金):福島県立安積高等学校・SSH生徒研究発表会・運営指導委員会
気がついたら、3月3日。アウトリーチ活動があったのは、先週の26日の金曜日。色々なことが重なり、記事が書けないままで、5日も。予定の上では、今年度最後のアウトリーチ活動。コロナ禍を受けてのリモートでの参加。福島県立安積高等学校での生徒研究発表会、運営指導委員会。午前中のポスター発表には参加できずでしたが、午後からの口頭発表に。SSHという枠組みが始まった最初に参加した高校。その後、しばらく間を空けての今回のSSH。色々な苦労があるのだろうと。その当たりは、生徒研究発表会、運営指導委員会などでも。少しでも早く収束して、従来に近いactivityができればと。もちろん、リモートでのよいところは取り込むとして。。。ありがとうございました。
わたなべしるす
【リモートアウトリーチ活動】岩手県立盛岡第三高等学校・SRH発表会、青森県立五所川原高等学校・特別講義、福島県立福島高等学校・SSH発表会・運営指導委員会、福島県立安積高等学校・SSH生徒研究発表会・運営指導委員会(2/19, 20, 26追記)
2021年2月20日 (土)
新しいポスドクの林です
2021年2月18日 (木)
はじめまして、昨日からポスドクとして渡辺研でお世話になっている林真妃(はやしまき)です。ブログを書くことは人生初なので読みにくい文章になっているかと思いますが、簡単に自己紹介をさせていただきます。
私は金のシャチホコで有名(?)な愛知県名古屋市出身です。大学院から名古屋大の木下俊則教授の研究室で、シロイヌナズナを用いた気孔の研究をはじめて学位を取得しました。引き続き木下研で1年半ポスドクを勤め、その後にデンマークにあるコペンハーゲン大学のMichael Palmgren教授の研究室で、昨年末まで2年半の間ポスドクとして研究を行いました。
来年度から渡辺研で学振PDとして研究できることになり、コロナ禍で世界中が大変な状況の中ではありますが、昨年末に帰国しました。有難いことに採用前から研究をさせていただけるとのことで、昨日からお世話になっています。昨日は研究室で歓迎のケーキ会を開いていただきました。苺のミニパフェ、とても美味しかったです!ありがとうございます。
これまでは植物の環境応答や、植物細胞のイオン輸送について主に研究を行ってきました。これからはこれまでの経験を活かして、受粉時の雌雄間でのイオン輸送について解析し、アブラナ科の自家不和合性メカニズムの解明に役立てる研究ができればと思っています。
受精研究は私にとっては新しい分野なので不安もありますが、チャレンジできることに感謝をして、精一杯頑張っていきたいです。どうぞよろしくお願いします。
仙台の冬はコペンハーゲンより寒く感じて、驚いています。写真はコペンハーゲン大学の植物園に咲いている桜です。暖かい春が待ち遠しいです。
こちらの写真はコペンハーゲンより北にあるDyrehaven(鹿公園)と呼ばれる自然保護区域に行った時のものです(鹿が見づらくてすみません...)。真夏でとても暑かったですが、広大な敷地にある自然と鹿に癒されました。コロナが落ち着いたら、また訪れたいです。
ポスドク 林
【アウトリーチ活動】埼玉県県立熊谷西高等学校・SSH運営指導委員会、岩手県立一関第一高等学校・SSH運営指導委員会、香川県立観音寺第一高等学校・SSH発表会・運営指導委員会助言者、宮城県仙台第三高等学校・SSH運営指導委員会、仙台市立片平丁小学校・学校評議委員会(2/10, 12, 17追記)
2021年2月16日 (火)
研究室ではこの時期、学位審査。今年は2名の修士の学生が審査に。詳細は別記事にあるとおり。そんなことが重なり、気がついたら、3つのアウトリーチ活動の報告を失念。地震も重なったと言うことでご容赦を。
2/10(水):埼玉県県立熊谷西高等学校・SSH運営指導委員会
緊急事態宣言が発出されている埼玉県ということで、リモートでの熊谷西SSH運営指導委員会。今年度の実施内容、次年度に向けての計画を。その中身については、秘匿事項と言うことで、ご容赦を。コロナ禍ではありますが、リモートなどの活用で活路を見出せるのではと。。。
PS. 当日は、山形県立東桜学館高等学校の運営指導委員会も。ただ、学位審査と重なり、現地での開催となったことから、ご容赦を。。。
2/12(金):岩手県立一関第一高等学校・SSH運営指導委員会
水曜日の熊谷西高に続いて、岩手県立一関第一高等学校の運営指導委員会。東北地区と言うことで感染者も少ないですが、それでもリモート開催と言うことが、感染者を少なくすると言うことにつながっているのだろうと。多くのリモート開催のイベントにトライされていて。渡辺もリモートでの講義を行いました。今年いっぱいくらいはこの状態になるような。。。次年度もまた、講義ができればと思います。
2/12(金):香川県立観音寺第一高等学校・SSH発表会・運営指導委員会助言者
この日はいくつかの掛け持ち。観音寺一高SSH発表会での質問は現場での質問とは迫力が違う、それをどうすればよいのか。そんなことも実感。ここでの楽しみは数学での取り組み。質疑もいくつかでしたが、deepな議論もできました。運営指導委員会では、次年度以降を見据えて。。。詳細はご容赦を。ありがとうございました。
2/16(火):宮城県仙台第三高等学校・SSH運営指導委員会
運営指導委員会も、熊谷西、一関一、観音寺一に続いて、仙台三高で4校目。実施内容については、秘匿事項と言うことで。今年度の振り返り、次年度の計画、その先の将来計画の議論。取組をどうやって広げて、深化させるのか、学ぶところは多く、大学での教育研究にも活かすことにしないと。。。
2/17(水):仙台市立片平丁小学校・学校評議委員会
研究室がある片平キャンパスの近くにある、仙台市立片平丁小学校の学校評議委員を仰せつかり、**月に1回目があったのですが、2回目の開催。小学校での学習のスタートが大学でのまなびの基礎になるということを考えると、教育の継続の重要性を改めて、実感。今の小学生が大学院で学ぶ頃には、渡辺は退官。彼らに高等教育の場で関係することはないのかと思うと、残念ですが・・・。コロナ禍で実施が困難なことも多い中で、先生方の努力を垣間見た時間でした。ありがとうございました。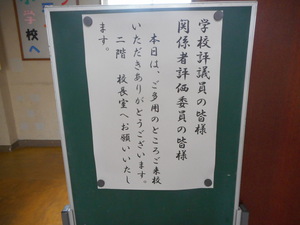
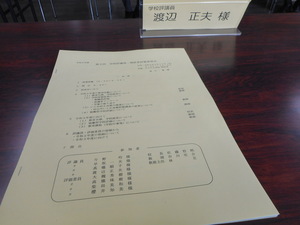
わたなべしるす
PS. 玄関先には春らしい花が。季節を先取りする「花もの」とはいえ、菜の花が開花しているとなると、春の交配シーズンが来るのだろうと。今年は大丈夫かと心配になるところです・・・。
【速報】2021年2月13日, 23時08分頃の震度5弱の地震からの復旧(2/15)
2021年2月15日 (月)
土曜日の夜中に、いきなり大きな揺れが。日曜日の朝、現場を確認して、唖然と。どうなるのかと思いました。また、3.11からの復旧と同じくらいと思ったのですが、電気、水道、ガスが通常であったことから、足の踏み場がなかった状態から、現場を確認しながら、15日の朝から、研究室のメンバーで復旧作業を。被害を受けたものも大きいですが、暫定的ですが、一見すれば、何となく、元に戻ったように見えます。もちろん、影響は大きいので、しばらくは不自由な側面もあるかもしれないですが。。。 朝から精力的に復旧作業をしてくれた研究室の皆さんに感謝です。ありがとうございました。
朝から精力的に復旧作業をしてくれた研究室の皆さんに感謝です。ありがとうございました。
わたなべしるす
【速報】2021年2月13日, 23時08分頃, 福島県沖(M7.3)地震に伴う影響(2/14)
2021年2月14日 (日)
このところ、コロナ禍のことを気にすることが多く、あと、1ヶ月弱で3.11から10年になろうという土曜日の夜中。大きな搖れが。。テレビをつけると、M7.3の地震で、仙台市は震度5弱。結構揺れたので、研究室の状況を心配しましたが。。。 3.11に近い状態の崩れ方。日曜日と言うこともあるので、片付けは月曜日以降で。人的被害はでてないですが、10年目の3.11を無事に迎えることができなかったのは。。。今回の災害に遭われた方に、お見舞い申し上げます。
3.11に近い状態の崩れ方。日曜日と言うこともあるので、片付けは月曜日以降で。人的被害はでてないですが、10年目の3.11を無事に迎えることができなかったのは。。。今回の災害に遭われた方に、お見舞い申し上げます。
わたなべしるす




