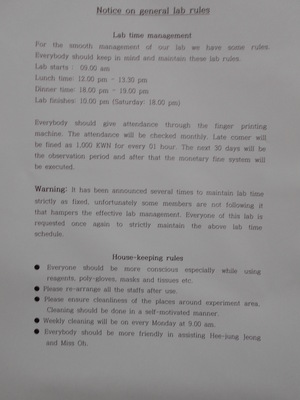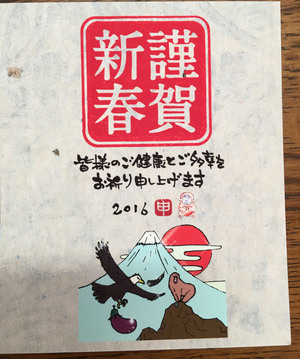お正月気分というか、今日は何日なのか、年始から海外出張があったりして。ただ、何曜日なのかだけは、Journalが出る日が毎週決まっているので、そんなこともあり、なんとか、曜日感覚だけは。いずれ、暖冬なのだけは事実で。困ったものです。。。そんな土曜日。片平キャンパスから2番目に近い高校。宮城県仙台第一高等学校のSSH生徒課題研究発表会の案内を頂き、お邪魔を。SSHの出前講義、科学者の卵養成講座の受講生などが数多く参加頂いており、なにより、宮城第一高等学校の時代から生物の小松原先生にはお世話になっており、。。
ここは、ちょうど、岡山県の金光学園高校と同じように文理関係なく、広く課題研究を。こちらの仙台第一高等学校の方が1, 2年生全体でやっているという意味では、さらに広いのではという気も。。。いずれ、体育館全体を使って、途中でポスターの張り替えまでする形で、100-200課題くらいあったのではないでしょうか。全体を見る時間はないので、これというトピックを探して。いくつか目にとまったり、これまで生物部などで、指導していたり、科学者の卵養成講座の受講生がどうしているかを。その当たりを拝見。
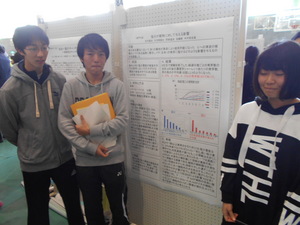 最初は、イネ発芽時の耐塩性。栽培イネでなくて、野生種であれば、塩水をかけても生育するイネがあるというのを。何でも、夜露として水分を外部に出すときに、塩水が出て行くとか。。。ただ、これは聞いた話。実物を見たことがないのですが。一方で、育種の結果、海水でも育つ栽培イネもあるとか。その当たりは、未確定情報なのですが。発表ではそんなことは触れていなかったですが、イネの形態学についてはもう少し学習した方が。イネ科の生長は普通の植物と異なり、地上部は葉鞘と葉身からできていて。出穂時に茎の生長が起きる。ちょっと不思議な仕掛けのもの。また、胚乳で初期生育が起きることも。渡辺は農学部農学科だったので、そんなことを知っている。そうかもしれないですが、課題研究でやるなら、そのイネ科の基本は理解しておいてほしいなと。
最初は、イネ発芽時の耐塩性。栽培イネでなくて、野生種であれば、塩水をかけても生育するイネがあるというのを。何でも、夜露として水分を外部に出すときに、塩水が出て行くとか。。。ただ、これは聞いた話。実物を見たことがないのですが。一方で、育種の結果、海水でも育つ栽培イネもあるとか。その当たりは、未確定情報なのですが。発表ではそんなことは触れていなかったですが、イネの形態学についてはもう少し学習した方が。イネ科の生長は普通の植物と異なり、地上部は葉鞘と葉身からできていて。出穂時に茎の生長が起きる。ちょっと不思議な仕掛けのもの。また、胚乳で初期生育が起きることも。渡辺は農学部農学科だったので、そんなことを知っている。そうかもしれないですが、課題研究でやるなら、そのイネ科の基本は理解しておいてほしいなと。
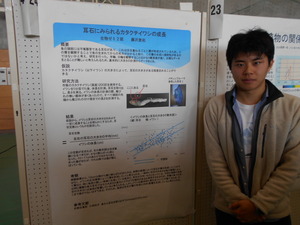 次に見つけたのは、魚の成長と耳石との相関。なるほどと思った反面、例えば、雌雄の耳石で違いがないのか、また、雌雄での違いはないのかなど。魚が専門でないので、イネほど細かなことはかけないですが、もう少し工夫をしたら、おもしろくなるのではと。遺伝子組み換えのナタネが移動などの関係で野外にあるというのは、これまでも育種上、問題になっていたわけです。それに着目して。3.11の津波との関係。もう一工夫がほしいなと。。。
次に見つけたのは、魚の成長と耳石との相関。なるほどと思った反面、例えば、雌雄の耳石で違いがないのか、また、雌雄での違いはないのかなど。魚が専門でないので、イネほど細かなことはかけないですが、もう少し工夫をしたら、おもしろくなるのではと。遺伝子組み換えのナタネが移動などの関係で野外にあるというのは、これまでも育種上、問題になっていたわけです。それに着目して。3.11の津波との関係。もう一工夫がほしいなと。。。
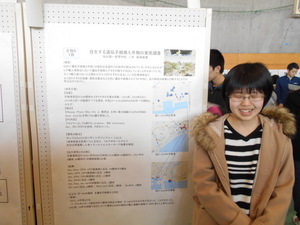 あと、プレゼンの仕方の問題も。今の生徒さんたちは、パソコン、携帯端末を使っているはず。その時、わからないときは、Google先生にというのをよく聞きます。その割に、プレゼンでグラフをExcelで書かせたとき、dotの大きさが大きすぎたら。。。重なっていくつの点があるのか。それは見せ方としては、重要な問題。その当たりも工夫しないと。せっかく普段は、Google先生にお世話になっているのに。。。
あと、プレゼンの仕方の問題も。今の生徒さんたちは、パソコン、携帯端末を使っているはず。その時、わからないときは、Google先生にというのをよく聞きます。その割に、プレゼンでグラフをExcelで書かせたとき、dotの大きさが大きすぎたら。。。重なっていくつの点があるのか。それは見せ方としては、重要な問題。その当たりも工夫しないと。せっかく普段は、Google先生にお世話になっているのに。。。
 高校生が数学的な観点とは言え、麻雀を考えているのは。。。子供の頃、夏休みなど、友だちが集まってやっていたのを、ふと思い出して。色々な仮定をして、ある場面でどうすればよいか。確かに数学の問題かもしれないです。しかしながら、やっているのは人間。表情に出したり、よい牌パイだったのに、そうでない顔をするヒトも。その逆も。そうしたことを確率で扱うのは。。。。わざと遠回しをして、あるいは、自分以外の3人との駆け引きの部分もあるわけです。その駆け引きがある意味で醍醐味。そういえば、将棋の終盤の羽生マジック。これはたぶん、あり得ないと思う一手で、何を考えているのか戸惑わされている間に、負けになっている。麻雀ではそんなに時間がないですが、それでもある種の決断と流れを読むこと。これは、サイエンスでも大事なこと。どちらの実験を先にするかによって、色々なことがちがってきたりします。麻雀好きで数学的に考えるのはよいことですが、人間がやっているということをどう考えるのか。そのことを考える方が、おもしろいような。
高校生が数学的な観点とは言え、麻雀を考えているのは。。。子供の頃、夏休みなど、友だちが集まってやっていたのを、ふと思い出して。色々な仮定をして、ある場面でどうすればよいか。確かに数学の問題かもしれないです。しかしながら、やっているのは人間。表情に出したり、よい牌パイだったのに、そうでない顔をするヒトも。その逆も。そうしたことを確率で扱うのは。。。。わざと遠回しをして、あるいは、自分以外の3人との駆け引きの部分もあるわけです。その駆け引きがある意味で醍醐味。そういえば、将棋の終盤の羽生マジック。これはたぶん、あり得ないと思う一手で、何を考えているのか戸惑わされている間に、負けになっている。麻雀ではそんなに時間がないですが、それでもある種の決断と流れを読むこと。これは、サイエンスでも大事なこと。どちらの実験を先にするかによって、色々なことがちがってきたりします。麻雀好きで数学的に考えるのはよいことですが、人間がやっているということをどう考えるのか。そのことを考える方が、おもしろいような。
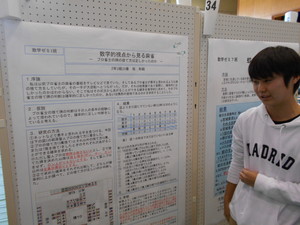 文系の課題もあり、「愛国心」というのも。そういえば、来週には、リオ五輪の予選を兼ねたサッカー男子アジア地区最終予選AFC U23選手権。そんな時、日本の国旗が振られたり。あるいは、国体など入場式では、来賓のところで、「かしら~~~みぎ」といって、帽子を取り、というもあります。そういえば、去年の3月に科学者の卵養成講座の関係で、リバーサイドの高校へ。その時には、全ての教室に星条旗が。。。先日の韓国訪問の時にも、セミナー室には、韓国国旗の「太極旗」が。日本では、祝日に国旗掲揚されるくらいで。。。どうも日本では愛国心を語ると。。。という面があるようですが、グローバルには、国旗掲揚をすることは、普通の事象のような気がするのですが。。。その当たりは少し考えてほしいなと。
文系の課題もあり、「愛国心」というのも。そういえば、来週には、リオ五輪の予選を兼ねたサッカー男子アジア地区最終予選AFC U23選手権。そんな時、日本の国旗が振られたり。あるいは、国体など入場式では、来賓のところで、「かしら~~~みぎ」といって、帽子を取り、というもあります。そういえば、去年の3月に科学者の卵養成講座の関係で、リバーサイドの高校へ。その時には、全ての教室に星条旗が。。。先日の韓国訪問の時にも、セミナー室には、韓国国旗の「太極旗」が。日本では、祝日に国旗掲揚されるくらいで。。。どうも日本では愛国心を語ると。。。という面があるようですが、グローバルには、国旗掲揚をすることは、普通の事象のような気がするのですが。。。その当たりは少し考えてほしいなと。
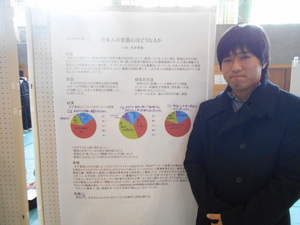 順番的には最後出なかったのですが、渡辺の高校時代には、一番得意だった、数学の問題。零で割り算をするという問題。数学的には、基本あり得ません。禁則だったような。ただ、議論をして、無限小、無限大という観点で考えると、なるほどと。すっかり議論に夢中になり、他の課題を見る時間も終わってしまって。論理的に破綻をしないように物事を考えること、それは、やっぱり大事なのだと、考え直させてもらいました。ありがとうございました。おもしろかったです。
順番的には最後出なかったのですが、渡辺の高校時代には、一番得意だった、数学の問題。零で割り算をするという問題。数学的には、基本あり得ません。禁則だったような。ただ、議論をして、無限小、無限大という観点で考えると、なるほどと。すっかり議論に夢中になり、他の課題を見る時間も終わってしまって。論理的に破綻をしないように物事を考えること、それは、やっぱり大事なのだと、考え直させてもらいました。ありがとうございました。おもしろかったです。
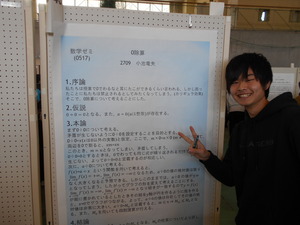 発表会のあと、それぞれの分野ごとに反省会。「生物」でお世話になったのですが、小松原先生がケガをされていることもあり、代わりに渡辺が。。。代わりになるほどのことは語れないのですが、論理的に考え、その思考力を活かして、文章力を磨くこと。結構難しいかもしれないですが、渡辺が大学1年生向けに行っている展開ゼミでは、20回近い記事を書くことで、しっかりした論理的な文章力をつけた方も。同世代です。大学生だからと言わず、しっかり文章力を磨いて下さい。その例として、渡辺がよくHPに書いている3 wordの関係なさそうなことでstoryを作る。発想力と何をどの様に関連づけるか。ちなみに、今日は生徒さんから、3 wordを提案してもらい、「a、愛、キノコ」。。。さすがにすぐには頭を抱えたので、生徒さんに振って、2名の方にこたえてもらいましたが。。。難しいようでした。渡辺の解答。それは、ここでは内緒と言うことで。。。最後、どの様なオチをつけるのか。それは話として重要なので。。。覚えておいて下さい。このあと、もう1人の生物の先生である佐藤先生から、お言葉を。ありがとうございました。
発表会のあと、それぞれの分野ごとに反省会。「生物」でお世話になったのですが、小松原先生がケガをされていることもあり、代わりに渡辺が。。。代わりになるほどのことは語れないのですが、論理的に考え、その思考力を活かして、文章力を磨くこと。結構難しいかもしれないですが、渡辺が大学1年生向けに行っている展開ゼミでは、20回近い記事を書くことで、しっかりした論理的な文章力をつけた方も。同世代です。大学生だからと言わず、しっかり文章力を磨いて下さい。その例として、渡辺がよくHPに書いている3 wordの関係なさそうなことでstoryを作る。発想力と何をどの様に関連づけるか。ちなみに、今日は生徒さんから、3 wordを提案してもらい、「a、愛、キノコ」。。。さすがにすぐには頭を抱えたので、生徒さんに振って、2名の方にこたえてもらいましたが。。。難しいようでした。渡辺の解答。それは、ここでは内緒と言うことで。。。最後、どの様なオチをつけるのか。それは話として重要なので。。。覚えておいて下さい。このあと、もう1人の生物の先生である佐藤先生から、お言葉を。ありがとうございました。
 最後になりましたが、生物の小松原先生、佐藤先生、金先生、ありがとうございました。近い場所です。また、折を見て、伺います。
最後になりましたが、生物の小松原先生、佐藤先生、金先生、ありがとうございました。近い場所です。また、折を見て、伺います。
わたなべ拝
PS. 今日の発表会にあわせて、石川県立小松高等学校の寺岸先生と喜作先生が来仙。寺岸先生が発表会のあと、渡辺の研究室に。3hrほどだったでしょうか。昨今の教育事情について、deepな議論を頂きました。ありがとうございました。今月末には、北陸遠征。楽しみにしておりますので。