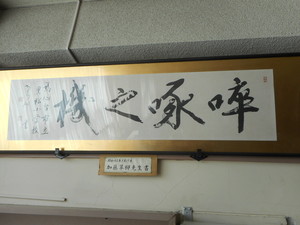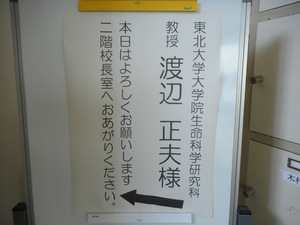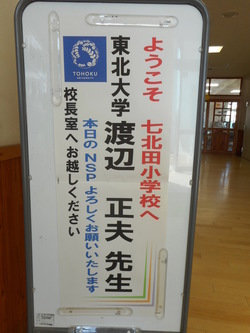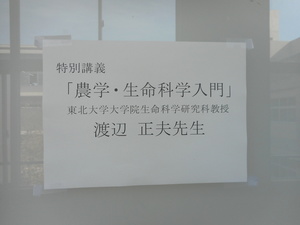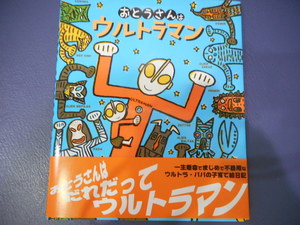1日の寒暖差が身にしみる季節になってきました。
技術職員の伊藤です。
寒暖差に身体がついて行かず体調を崩しやすい時期です。 加えて、台風19号の被害に遭われ今も大変な状況にいる方々も大勢おられると思います。
仙台でも夜中に何度も緊急速報のメールが鳴り、避難勧告が出た地域の学生さんが研究室に避難したりと緊張した1日でしたが、片平キャンパスは大した被害もなく、当研究室のスタッフ、学生さん達も皆、無事でした。
今回の台風で、雨が強くなり、自宅近くのマンホールから水が溢れてきている様子を見ながら、こんな暗闇の中、避難指示が出た場合、自分自身がうまく避難できるかとても不安になりました。
ましてや小さい子供やお年寄りがいる家庭などを考えると、非常に難しいのだろうなと。
普段からの意識と備え、訓練などが重要である事を再認識しつつも、、、ニュースで被害を目の当たりにすると不安が大きくなる日々です。
今は被害に遭われた方々が1日も早く日常生活に戻れる事をお祈りしております。