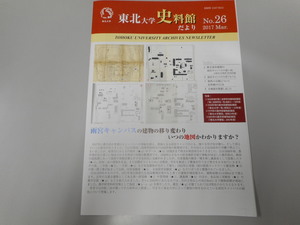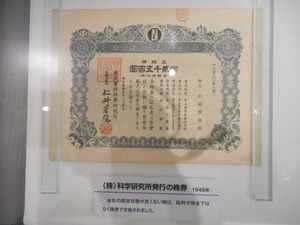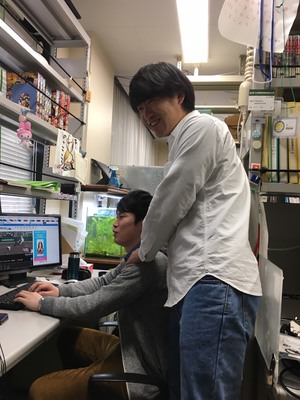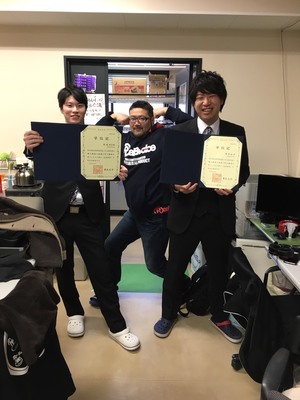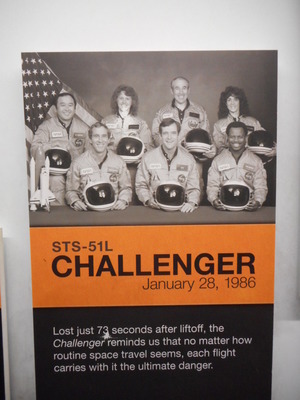どうも、今年からM1としてお世話になる乳井優樹です。
名字の読みは「におい」です。乳井のルーツは青森県ですが、読みはにゅういの方ばかりで、においは少ない(というかいない?)そうです。
珍しいと言うか、もはや変な名字ですがよろしくお願いします。
出身は「元・人口日本一の村」で有名な岩手県滝沢『市』です。村ではなく市です。(ここ大事)チャグチャグ馬コという祭りのような何かが行われる、田園風景の広がるのどかな村市です。
↑チャグチャグ馬コの風景。いやぁのどかですね~笑
このような自然豊かなところで育ってきたわけではありますが、植物をろくに育てたことがありません。
学部時代は化学系だったため、植物関係に関してど素人な僕はこれからいろいろと苦労しそうです・・・
鼻炎持ちなので、花粉症になったらもう大変ですね
さて、プロフィールに書きましたが今年はオシャレなBAR探しをしたいですね。
というのも、結構お酒を飲むのが好きで、最近ウィスキーにはまってるんですよ。
全然詳しくないので勉強中です。
いろいろと本を読んでみると、どうやらBAR巡りをすると美味しいウィスキーに出会えるらしい。
特にオシャレなBARのマスターは色々知っているらしい。
というわけでダンディーなマスターのいるおしゃれなBARを知っている方は、ご一報ください。
学部時代は毎日をぐだぐだ自分のペースで過ごしていたわけですが、大学院生となった今は研究に打ち込んで頑張りたいと思います。まずは生活習慣を取り戻すことからですかね。