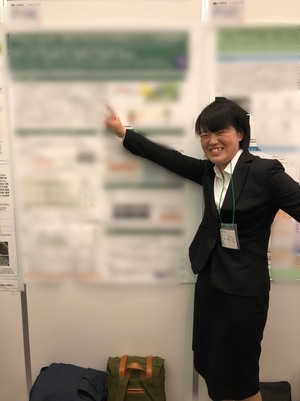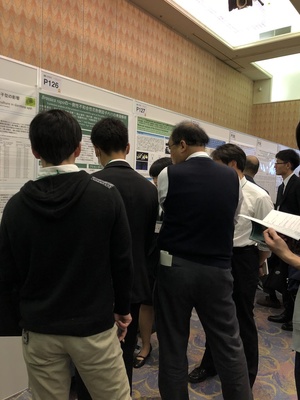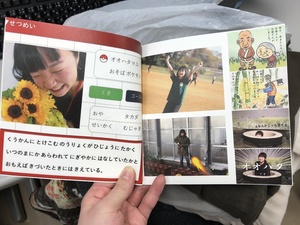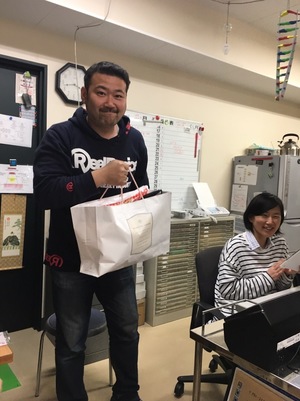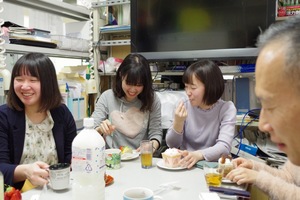はじめまして。新M1の小川萌菜です。
埼玉県産科学者の卵(自称)。岩手で抱卵。
4年間の盛岡生活で暖かさへの閾値が下がりに下がったこの私。
仙台の気候に心躍ります。
4月頭に桜咲いてる!すごい!さすが仙台!と思ったら今年は全国的に早いそうで。
盛岡名物(?)GW花見はどうなるのだろうと思ったり思わなかったり。
好きなものはお酒。
一緒に日本酒を飲みに行ってくれる人を常時募集しています。
やりたいことはお菓子作り。
バターと小麦粉と砂糖のかたまりに夢を見ます。
じつはメンバー紹介のサムネイルのタルトも自作だったり。
いつか研究室にも持ってこられたらいいなと思います。
あとは登山もしたいですね。
山が好きです。
どなたか宮城のいい山を紹介してください。
初ブログでなにも写真がないのも寂しいので大学時代に岩手山から撮った景色でも。
あまり写真を撮る習慣がないので今後増やしていきたい所存です...。
菜の花萌える3月生まれ、その名の通り見事に菜の花の研究に携わります。
研究室のみなさん、ぜひともよろしくお願いします!