週末から今日、明日くらいでしょうか。東北、北陸地方で大雨の予報。雨雲の雨が強いところが山形から宮城に移動中。午後にかけては、注意が必要な感じでは。
そんな週明けの月曜日。科学者の卵養成講座の昨年度末の海外研修でご一緒した宮城教育大・渡辺尚先生からのリクエスト。以下のように、「化学」系ですが、Intel ISEF(The Intel International Science and Engineering Fair)という、世界最高峰の生徒による研究の国際大会というか、たぶん、主に、高校生がおもしろい研究をした内容を発表し、競い合うもの。渡辺尚先生も前職の時代に、たぶん、2回ほど、高校生を連れて、このイベントに参加し、参加した高校生は世界的な賞を受賞したと言うことを伺ったことがあるような。。。その高校生は、科学者の卵養成講座の受講生でもありました。渡辺は小学校くらいは自由研究をした覚えがありますが、それ以降は。。。大学に入って、研究室に配属なって、研究を始めたわけで。。。よき指導者に恵まれるというのは、いつの時代も同じかと。。。ふと、そんなことを。 その渡辺尚先生から、下記のようなイベントを8月11日(金)に行うというお知らせを頂きましたので、渡辺の所からもご紹介を。今年から、8月11日(金)は、山の日という旗日に。渡辺は夏休みの宿題が終わりそうになくて、参加できそうにないのですが、国内でもトップクラスの指導者の先生方から実験、講演を聴けるチャンスは、なかなかないものです。是非、参加してみてはどうでしょうか。
その渡辺尚先生から、下記のようなイベントを8月11日(金)に行うというお知らせを頂きましたので、渡辺の所からもご紹介を。今年から、8月11日(金)は、山の日という旗日に。渡辺は夏休みの宿題が終わりそうになくて、参加できそうにないのですが、国内でもトップクラスの指導者の先生方から実験、講演を聴けるチャンスは、なかなかないものです。是非、参加してみてはどうでしょうか。
わたなべしるす
****************************************
以下、http://chemeduc.miyakyo-u.ac.jp/ からの情報の転載と一部改変
化学への招待~楽しいみんなの実験室~
(ISEF(世界最高峰の学生研究の国際大会)で入賞以上の生徒研究を指導した日本最高峰の課題研究指導者の先生方による魅力あるワクワク体験実験)
日時:平成29年8月11日(金) 10:00~16:00
会場:宮城教育大学 理科学生実験棟(宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149)
(仙台市地下鉄東西線「青葉山駅」下車 徒歩10分) 【講師】
【講師】
ISEF2016 グランドアワード2等 指導者 谷藤尚貴 准教授(米子工業高等専門学校)
ISEF2015 グランドアワード3等 指導者 菅原佑介 教諭(仙台第三高等学校)
【日程・内容】実験ワークショップ,招待講演,シンポジウム
《実験》
谷藤准教授 ISEF2016で入賞した機能性膜を利用した新電池(実験1) 10:00~12:00
菅原教諭 ISEF2015で入賞した虹色に輝く銅箔の実験(実験2) 14:00~16:00
《招待講演》
谷藤准教授『2年連続のISEF参加と生徒研究』 12:30~12:45
菅原教諭『教材を活かした研究のヒント』 12:45~13:00
《シンポジウム》
『講演者を囲んで課題研究の指導に関するノウハウと生徒の心得』13:00~13:30
座長:渡辺尚 宮城教育大学 准教授(ISEF2014/2015 連続受賞指導者)
【対象】
実験:中学生、高校生
講演:中学生、高校生、大学生、大学院生、一般(教員)
定員:実験 谷藤准教授 30名, 菅原教諭 30名, 講演(シンポジウム) 50名(先着順)
【参加費】 無料
【申込方法】 以下の項目を記載し、お問合せ先に電子メール・FAXのいずれかで、7月28日(金)までに送信ください。ご参加の可否と詳細は電子メール等にてご連絡いたします。下記内容は個人情報として扱います。
1. お名前(ふりがな)と性別, 2. 一般・学生の別(中高校生は学年)
3.ご希望のプログラム(実験1・講演とシンポジウム・実験2(複数選択可)
4. 学校名または勤務先, 5. 住所と電話番号
6. メールアドレス(必須), FAX 番号(任意)
【お問合せ】
〒980-0485 仙台市青葉区荒巻字青葉149
宮城教育大学 理科教育講座 「化学への招待」事務局
担当 渡辺 尚・笠井 香代子
TEL:(022)214-3429(笠井), 3423(渡辺)
FAX:(022)214-3429, E-mail:chemeduc@ml.miyakyo-u.ac.jp
<募集要項> pdf file
<ポスター> pdf file
<参加申込書> Word file, pdf file
ここまで。
****************************************
【お知らせ】化学への招待~楽しいみんなの実験室~, 8月11日(金)実施(7/24)
2017年7月24日 (月)
【広報誌掲載】2016年のNature Plantsに掲載された論文の記事が、本学広報誌「まなびの杜」に掲載(7/10)
2017年7月10日 (月)
北部九州の豪雨。少し落ち着いたのかも知れないですが、激甚災害に指定され、1日でも早い復旧、復興を祈るばかりです。また、こうした局地的な豪雨の関係でしょうか。鳥取ではアワヨトウが大発生とか。。。早めの対応をしないと、さらに被害が拡大するのでは。。。何とか、もう少し日本全体に均一な雨が降ってほしいと。仙台は、きょうも30oCを超えるような気温になりそうですので。もちろん、東日本を中心に猛暑が続いているわけですが。。。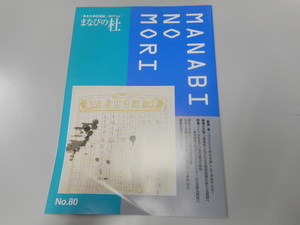 そんな中。学内の広報誌「まなびの杜」というものがあり、本学の研究、教育、学生の活動などを広報する冊子が、年に4回、発行されています。その中に「Line-up of Leading-edge Research 最新の研究ラインナップ」というセクションがあり、昨年の12月から今年の3月にかけて、大学のHPなどで広報した中から、これはという広報のセレクションに、渡辺の研究室での研究が選ばれました。12月26日にお知らせした、Nature Plants誌に発表した「対立遺伝子間での複雑な優劣性関係の解明」というものになります。HPだけでなく、こうした冊子体でも取り上げて頂けるのは、ありがたいことで。「まなびの杜」のwebsiteから読むことができますので、お時間の許す方、是非に。。これを励みに、さらに、教育研究を展開したいと思います。ありがとうございました。
そんな中。学内の広報誌「まなびの杜」というものがあり、本学の研究、教育、学生の活動などを広報する冊子が、年に4回、発行されています。その中に「Line-up of Leading-edge Research 最新の研究ラインナップ」というセクションがあり、昨年の12月から今年の3月にかけて、大学のHPなどで広報した中から、これはという広報のセレクションに、渡辺の研究室での研究が選ばれました。12月26日にお知らせした、Nature Plants誌に発表した「対立遺伝子間での複雑な優劣性関係の解明」というものになります。HPだけでなく、こうした冊子体でも取り上げて頂けるのは、ありがたいことで。「まなびの杜」のwebsiteから読むことができますので、お時間の許す方、是非に。。これを励みに、さらに、教育研究を展開したいと思います。ありがとうございました。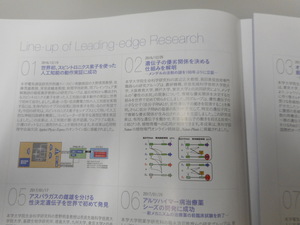
わたなべしるす
【新聞掲載】Nature Plantsに掲載された論文の記事が、毎日新聞・科学面に掲載(7/6)
2017年7月 6日 (木)
先月の27日に「自家不和合性遺伝子の「遺伝子重複」が、離れた地域間での生殖を妨げる仕組みを世界初で証明」ということが「Nature Plants」に掲載されたことをお知らせしました。その後、Nature Plantsの7月号に綴られ、1つの論文でなくて、冊子体ではないですが、今年の7月号にまとまった形になりました。発見したのは、昨日でした。 で、今朝の毎日新聞・科学面に「交配妨げる遺伝子の仕組み解明」ということで、今回の論文の内容が記事として掲載されました。あわせて、毎日新聞社のweb上でも「サイエンス」のコーナーに、同一のタイトルで、記事が掲載されております。新聞の仕組みをきちんと理解してないこちらがよくないのですが、いわゆる、東京版に掲載と言うことで、全国でどれくらいの方が見て頂けるのか、気になっていたのですが、web上に掲載というのは、とてもありがたい広報となりました。
で、今朝の毎日新聞・科学面に「交配妨げる遺伝子の仕組み解明」ということで、今回の論文の内容が記事として掲載されました。あわせて、毎日新聞社のweb上でも「サイエンス」のコーナーに、同一のタイトルで、記事が掲載されております。新聞の仕組みをきちんと理解してないこちらがよくないのですが、いわゆる、東京版に掲載と言うことで、全国でどれくらいの方が見て頂けるのか、気になっていたのですが、web上に掲載というのは、とてもありがたい広報となりました。
さらに研鑽して、よりよい研究成果をより分かりやすく広報したいと思います。ありがとうございました。
わたなべしるす
PS. 論文が掲載されたという記事の最後に書いておいたのですが、少し目立たないこともあり、独立した記事として。。。ということで。あれ?と思った方、お許しください。
【受講者募集のご案内】TEA's English 2017年度夏季集中プログラム(7/5)
2017年7月 5日 (水)
学内のグローバルラーニングセンターというのがあり、その中のいくつかのセクションというか、プログラムのようなものがあり、渡辺の展開ゼミは「TGLプログラム」に参画しています。また、別のセクションである「東北大学イングリッシュアカデミー(TEA)」からのお知らせも、ここから発信していたと。展開ゼミ期間中であれば、展開ゼミの中から、情報発信するのですが。。。春先にも、TEAからのお知らせを掲載したかと。 グローバルラーニングセンターとは、上記のようなコラボと思っていたのですが、とある方から。「入学前海外研修」というのがあり、その中に「科学者の卵養成講座」というのがあると。。。かなりびっくりでした。こんなところでつながっているとは。。。恐るべし。世の中の狭さ。。。
グローバルラーニングセンターとは、上記のようなコラボと思っていたのですが、とある方から。「入学前海外研修」というのがあり、その中に「科学者の卵養成講座」というのがあると。。。かなりびっくりでした。こんなところでつながっているとは。。。恐るべし。世の中の狭さ。。。
というわけで、グローバルラーニングセンター「TEA's English事務局」から「TEA's English 2017年度夏季集中プログラム」が来ておりました。興味のある方は、チャレンジしてみて下さい。渡辺は英語の論文を読むくらいで、。。。これでは、英語は上達しそうにないのですが。。。今週もUC Riversideから外国のお客様が。。。セミナーも。。頭を抱えそうです。。。
わたなべしるす
以下、頂いた文面を転載。
****************************************
Tohoku University English Academy(TEA) TEA's English事務局でございます。
2017年度夏季TEA's English集中プログラム受講者募集のご案内を差し上げております。本プログラムでは、アカデミック英語力を身につける講座に加えて、英語研究論文執筆講座やTOEFL iBT対策講座などを開講予定となっております。ぜひ、学生の皆様へご案内をいただけますよう、ご助力を賜れましたら幸いでございます。
TEA's Englishプログラムは、2015年に開始以来、のべ1000名以上の東北大学学部生および大学院生が受講し、大変好評をいただいている課外英語学習プログラムでございます。(※授業料無料、教材費のみ別途必要)
以下、2017年度夏季集中プログラムの開講予定講座でございます。
① Academic 1(中級レベル)/2(上級レベル)
大学・大学院への留学に必要な英語力を総合的に伸ばしたい学生向け
② Academic General Writing
英語で研究論文を書くスキルを基礎からしっかり身につけたい学生向け
③ Academic Science Writing
英語で理系の研究論文を書くためのより専門的なスキルを身につけたい学生向け
※大学院生および学部3年生以上対象
④ TOEFL iBT対策講座
TOEFL iBTのスコア向上を目指す学生向け
以下の日程にて募集説明会を実施いたします。この度、初めて青葉山キャンパスにて説明会を開催いたしますので、多くの学生の説明会参加をお待ちしております。
【日時および場所】
2017年7月7日(金) 18:30~19:30 川内北キャンパス 講義棟A棟 A200
2017年7月14日(金) 16:30~17:30 青葉山キャンパス 中央棟2階大会議室
教職員の方々の説明会見学も可能でございます。
※お席は学生優先となります。
詳細は、以下グローバルラーニングセンターのホームページをご確認くださいませ。
http://www.insc.tohoku.ac.jp/japanese/global/tea/teas-english/
なお、過去の受講生からは、受講後アンケートにて以下のようなお声をいただいております。
「英語のディスカッションなどこの講座でしかできない経験を積むことができた」、「正しい引用の仕方や英語での論文構成を学ぶことができた」、「インタラクティブな授業スタイルで実用的なトレーニングができた」
2016年度春季集中プログラムの受講後のアンケートでは、回答者(62名)の96.8%がプログラム全体の満足度について「とても満足」または「満足」と回答するなど、評価の高いプログラムとなっております。
****************************************
転載ここまで。
【お知らせ】オープンキャンパス(7/25-26)に伴う研究室公開について(6/26)
2017年6月26日 (月)
仙台も梅雨入りしたとはいえ、かなりの日差しと気温も30oC近く。本当に空梅雨になるのか。3ヶ月予報を見ても、7月になると、雨が多いらしい。ただ、8, 9月は高温になるとか。。。9月の高温はアブラナの栽培には、。。あれこれとあった諸事情ももう少しでclearできるのでは。。。というか、今週の出前講義などと週末の大学院入試を対応しないと。。。大学院入試は、研究室の学生さんたちの頑張りもあり、来年度の学生さんの目標値まで達成できそうかなと。。。いずれ、確定するまでは、安心しないように。 今年で7年目になりますが、オープンキャンパスと連動した研究室公開。これまでもずいぶん多くの高校生が見学に来てくれました。渡辺が学生の頃には、オープンキャンパスは、もちろんなくて、農学部の助手時代にもそんなことはなくて。岩手大・農学部に異動したあとにも、なかったような。。。仙台にもどった2005年以降は、大学院だけでしたので。。。いずれ、多くの高校生が来るというのは、あちこちから。大学のオープンキャンパスの案内を見ると、青葉山、川内、星陵地区になるかと。片平キャンパスでは、公開されていないかと。ただ、その分、研究室の中まで公開することはできますので。ここだけですが。よかったら、是非、お立ち寄り下さい。なにより、仙台市地下鉄東西線を利用すれば、川内、青葉山キャンパスの帰り道に、という方も時間も読めて、行動しやすいのでは。その途中にある「青葉通一番町駅」から渡辺の研究室がある片平キャンパスまで徒歩で10min程度。平地ですし。学校全体での行動というのであれば、少したいへんかもしれないですが、それでも、昔よりは、時間を読みながら、行動できると思います。もちろん、個人で参加の方は、地下鉄を利用すれば、いくつかのキャンパスをと言うのも可能と思います。
今年で7年目になりますが、オープンキャンパスと連動した研究室公開。これまでもずいぶん多くの高校生が見学に来てくれました。渡辺が学生の頃には、オープンキャンパスは、もちろんなくて、農学部の助手時代にもそんなことはなくて。岩手大・農学部に異動したあとにも、なかったような。。。仙台にもどった2005年以降は、大学院だけでしたので。。。いずれ、多くの高校生が来るというのは、あちこちから。大学のオープンキャンパスの案内を見ると、青葉山、川内、星陵地区になるかと。片平キャンパスでは、公開されていないかと。ただ、その分、研究室の中まで公開することはできますので。ここだけですが。よかったら、是非、お立ち寄り下さい。なにより、仙台市地下鉄東西線を利用すれば、川内、青葉山キャンパスの帰り道に、という方も時間も読めて、行動しやすいのでは。その途中にある「青葉通一番町駅」から渡辺の研究室がある片平キャンパスまで徒歩で10min程度。平地ですし。学校全体での行動というのであれば、少したいへんかもしれないですが、それでも、昔よりは、時間を読みながら、行動できると思います。もちろん、個人で参加の方は、地下鉄を利用すれば、いくつかのキャンパスをと言うのも可能と思います。
で、オープンキャンパスは、7月末の7/25(火)-26(水)。この間、基本、渡辺は研究室におります。研究室までの道順は、渡辺のHPにありますし、あらかじめ、いつ頃研究室を訪問というのであれば、準備をしてお待ちしております。ここ数年、2~3の高校から高校生が見学にいらしています。研究室を見てみることで、実際にこんなところで、研究をしているという実感が芽生えるのではと思います。これまでの出前講義、科学者の卵養成講座など、お目にかかったことのある方。是非、お立ち寄り下さい。お待ちしております。もちろん、事前申し込みなしでもwelcomeですので。
わたなべしるす

