いつから始まったのか、こちらがきちんと把握できてないのですが、学内には、Tohoku University English Academy(TEA) TEA's English事務局というのがあり、英語力向上のサポートをしてくれています。こうしたお知らせを行うのも、後期に実施予定の1年生向けの展開ゼミを実施している関係で、案内が来たのだろうと。展開ゼミ実施中であれば、その枠内でお願いするのですが、今回は通常のお知らせ枠からの広報と言うことで。 渡辺は留学経験もなく、最長の海外出張はたぶん、2 weeks程度。。。なので、グローバルに適応できているかと言えば。。かなり難があるのですが。サイエンスを行う上では、英語は不可欠なので、何となく読んで書いて、しゃべっているという程度ですが。いずれ、母国語の日本語力をつけるには、是非、渡辺の展開ゼミを受講してみて下さい。去年の実施例を見ると分かると思います。あと、英語力という方は、このプログラムでしょうか。
渡辺は留学経験もなく、最長の海外出張はたぶん、2 weeks程度。。。なので、グローバルに適応できているかと言えば。。かなり難があるのですが。サイエンスを行う上では、英語は不可欠なので、何となく読んで書いて、しゃべっているという程度ですが。いずれ、母国語の日本語力をつけるには、是非、渡辺の展開ゼミを受講してみて下さい。去年の実施例を見ると分かると思います。あと、英語力という方は、このプログラムでしょうか。
というわけで、学内の「TEA's English事務局」から「TEA's English 2017年度前期学期内プログラム受講者募集のご案内」が来ておりました。興味のある方は、チャレンジしてみて下さい。
わたなべしるす
以下、頂いた文面を転載。
****************************************
Tohoku University English Academy(TEA) TEA's English事務局でございます。2017年度前期学期内プログラム受講者募集のご案内のためメールを差し上げております。新年度を迎えご多用の折、大変恐れ入りますが本プログラムを学生の皆様へご案内をいただけますよう、ご助力を賜れましたら幸いでございます。
TEA's Englishプログラムは、2015年に開始以来、のべ800名以上の東北大学学部生および大学院生が受講し、大変好評をいただいている課題英語学習プログラムでございます。
※2016年度後期学期内プログラム受講後アンケートにおける満足度95.0%(回答者数80人)
海外の大学・大学院への留学や研究、および国際社会での活躍を見据えアカデミックな英語を身につけたい学生を対象に、全米最大の留学・英語教育機関であるELSの指導メソッドを利用し、東北大学生専用のプログラムをご提供しております。
※授業料無料、教材費のみ別途必要
また、本年度より本プログラム受講生には、受講前後に無料でTOEFL iBT公式オンライン模試を受験いただける機会を設けております。受講前後における英語能力やその伸長の度合いの把握、プログラム後の継続学習の計画の作成、及びTOEFL iBTスコア向上のために受験を推奨しております。
※定員あり
以下の日程にて募集説明会を実施いたします。
【日時】
①2017年4月12日(水) 18:30~19:30
②2017年4月14日(金) 18:30~19:30
③2017年4月18日(火) 12:10~12:50
【場所】
①および② 川内北キャンパス 講義棟B棟 B101教室
③ 川内北キャンパス 講義棟B棟 B104教室
教職員の方々の説明会見学も可能でございます。
※お席は学生優先となります。
詳細は、以下グローバルラーニングセンターのホームページをご確認くださいませ。
http://www.insc.tohoku.ac.jp/japanese/application/14482/
過去の受講生からは、受講後アンケートにて以下のようなお声をいただいております。
「自分でも驚くほど、英語力が伸びたと自信を持って言えるようになった」
「英語によるエッセイ執筆やプレゼンテーションが出来るようになった」
また、受講後にTOEFL ITPのスコアが60点向上したという報告をくれた学生もおりました。
一人でも多くの学生の参加をお待ち申し上げております。何卒ご協力よろしくお願い申し上げます。
★無料英語アドバイジング実施中!
http://www.insc.tohoku.ac.jp/japanese/global/advising/advising-english/
****************************************
転載ここまで。
【受講者募集のご案内】TEA's English 2017年度前期学期内プログラム受講者募集のご案内(4/7)
2017年4月 7日 (金)
【お知らせ】展開ゼミ「秋冬野菜を盆栽として育ててみよう」が東北大学グローバルリーダー養成プログラム、平成29年度指定科目に(4/4)
2017年4月 4日 (火)
展開ゼミ「秋冬野菜を盆栽として育ててみよう」を開講して、今年で4年目。その前の年には、基礎ゼミとして「野菜・果物を盆栽として育ててみよう」を。HPを使っての双方向でのコミュニケーション力であったり、1粒の種子から出発して、野菜の収穫まで。簡単そうに見えて、実は、大変な作業というか、講義なのですが。それによって、最後までがんばる力、文章力は養成されるかと。そんなことと思われるかも知れないですが、社会に出れば、とても大事なポイント。。のはず。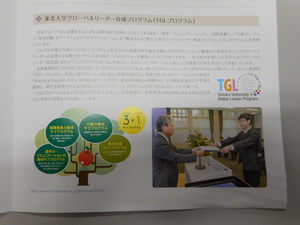 開講以来、本学で行っている「東北大学グローバルリーダー養成プログラム(TGL)」の「指定科目」に選定(このlinkのpdfの#86が渡辺の講義の所)され、渡辺の展開ゼミは、「行動力養成サブプログラム」に分類されています。グローバルな人材というのは、何か。。。定義が難しいですが、渡辺が該当するかと言えば。。。まず、日本語でのコミュニケーションであれば、OK。英語は。。。気合いが入らないと、かなりの難あり。ただ、気合いが入れば、というのは、先日の高校生のイベントでの海外出張の最終日に。。言語とはそのくらいかと。あと期待しているのは、AIの発達で迅速な同時通訳が。先週もとあるイベントで、同時通訳と英語が流れる中、英語であれば、他のことを考えながら、聞くことはかなり難しいですが、日本語であれば、というか、母国語であれば。。。かなり容易なことが一目瞭然。あと、異文化を理解する、これも結構難しいこと。自他を客観的に認識するというような表現があり、それはまさに、研究対象の「自家不和合性」、そのものだと。。。もちろん、多細胞生物であれば、細胞間のコミュニケーションもあるはずで。。。自他という観点かどうかは別として。。。行動力は「気合いと根性」。最後までそれを成し遂げるという強い信念があれば。きっと、できるのだと。。。その3つが養成されて、海外で研鑽すると。。。ただ、海外に出ると、360o全方位に注意力がないと。。。それくらい、日本国は安全なことを行ってみると、肌身で感じます。
開講以来、本学で行っている「東北大学グローバルリーダー養成プログラム(TGL)」の「指定科目」に選定(このlinkのpdfの#86が渡辺の講義の所)され、渡辺の展開ゼミは、「行動力養成サブプログラム」に分類されています。グローバルな人材というのは、何か。。。定義が難しいですが、渡辺が該当するかと言えば。。。まず、日本語でのコミュニケーションであれば、OK。英語は。。。気合いが入らないと、かなりの難あり。ただ、気合いが入れば、というのは、先日の高校生のイベントでの海外出張の最終日に。。言語とはそのくらいかと。あと期待しているのは、AIの発達で迅速な同時通訳が。先週もとあるイベントで、同時通訳と英語が流れる中、英語であれば、他のことを考えながら、聞くことはかなり難しいですが、日本語であれば、というか、母国語であれば。。。かなり容易なことが一目瞭然。あと、異文化を理解する、これも結構難しいこと。自他を客観的に認識するというような表現があり、それはまさに、研究対象の「自家不和合性」、そのものだと。。。もちろん、多細胞生物であれば、細胞間のコミュニケーションもあるはずで。。。自他という観点かどうかは別として。。。行動力は「気合いと根性」。最後までそれを成し遂げるという強い信念があれば。きっと、できるのだと。。。その3つが養成されて、海外で研鑽すると。。。ただ、海外に出ると、360o全方位に注意力がないと。。。それくらい、日本国は安全なことを行ってみると、肌身で感じます。 というような、このプログラムを推奨しているのか、怪しげに見えるかもしれないですが、何でもやってみること。渡辺が学生の頃には、こうした組み分けもなくて、取りたい講義を自由気ままに。なので、教養の講義で覚えているのは「経済学」、「統計学」くらいでしょうか。印象にあるのは。あとは、有機化学で追試があったり。クラス全体だったか、農学部全体だったか。いずれ、川内での講義にはあまりよいイメージがないのですが、。。今は、キャンパスもきれいになって。。。渡辺の講義は、片平キャンパスで行いますが。。。
というような、このプログラムを推奨しているのか、怪しげに見えるかもしれないですが、何でもやってみること。渡辺が学生の頃には、こうした組み分けもなくて、取りたい講義を自由気ままに。なので、教養の講義で覚えているのは「経済学」、「統計学」くらいでしょうか。印象にあるのは。あとは、有機化学で追試があったり。クラス全体だったか、農学部全体だったか。いずれ、川内での講義にはあまりよいイメージがないのですが、。。今は、キャンパスもきれいになって。。。渡辺の講義は、片平キャンパスで行いますが。。。
ということで、グローバルに活躍したいと思う方。チャレンジしてみてはどうでしょうか。本題の展開ゼミ「秋冬野菜を盆栽として育ててみよう」については、別記事でお知らせします。少しばかりお時間を。。。
わたなべしるす
【お知らせ】平成29年度入試説明会・オープンラボ(仙台開催; 5/20(土), 東京会場; 5/13(土))に実施、続報と研究科HPからの申し込み開始(4/4, 5/11追記)
2017年4月 4日 (火)
明日、4/5は本学の入学式。渡辺が学生の頃は、入学式を行わない唯一の国立大学でした。たしか。。。ものの本によると、1970-1990年くらいまで、入学式がなかったとか。渡辺はちなみに、1984年入学だったので。ほぼ、なかった時代の真ん中から後半。当時の学籍番号は、教養部2年間の学籍番号(59A235だったような。。)と、学部3, 4年時のは、違っていたような。学部の時の学籍番号は記憶にすらありません。。。で、入学式がなかったのは、学○運×の影響とか。もちろん、当時は、そんなことも知るよしもなく。。。全学規模で行ったのは、いつか覚えていませんが、最初に復活させようとしたのは、農学部。最初の頃は、あれこれと、もめていたような。。。関係ない場所から、見ていただけですが、どっちもがんばるなと。。。。。渡辺の時代、入学式がなく、オリエンテーションをやっただけで。担任の教官もいたような気がしますが、最初の挨拶だけだったような。そのあと、何かでお世話になることもなくて。。。講義の取り方などを説明してくれたのは、同じ農学部の先輩方。ありがたいことでした。また、川内でのオリエンテーションの後日だったでしょうか。農学部農学科の7つの研究室見学もして頂いたような。。。いずれ、変則な時代でしたが、縦の繋がりもできて、よかった時代だったような。。。 前置きが長くなりましたが、12月の半ば頃に、5月に開催される大学院の入試説明会、オープンラボについて、お知らせしましたが、研究科のHPからの申し込みができる状態ではありませんでした。ようやく準備が整い、申し込みができます。
前置きが長くなりましたが、12月の半ば頃に、5月に開催される大学院の入試説明会、オープンラボについて、お知らせしましたが、研究科のHPからの申し込みができる状態ではありませんでした。ようやく準備が整い、申し込みができます。
仙台開催; 5/20(土)--http://www.lifesci.tohoku.ac.jp/admission/detail---id-47157.html
東京会場; 5/13(土)--http://www.lifesci.tohoku.ac.jp/admission/detail---id-47154.html
今年度は、これまでのような電子入力でなくて、申込内容を教務係に送ると言うことです。気をつけて下さい。渡辺の所を希望する方は、「植物生殖遺伝分野」として下さい。もちろん、まだ、悩んでいる方は、希望分野の所を空欄でもOKです。ちょっと、ここがおもしろそうかなと言うのを、あらかじめ、HPで見てというのもありですから。なお、教務係に送る内容は、
********************************************
1. 参加希望会場
東京・仙台・秋田・弘前
(参加したい会場を残し、残りは消してください)
2. 氏名
3. 所属大学・学部・指導教員等
4. 学年
5. 希望分野
・第一希望分野
・その他の希望分野(あれば・・・)
********************************************
学部の1, 2, 3年生で、研究室に配属されてない場合は、大学名、学部名だけで、OKです。仙台会場、東京会場のどちらにも参加するという方は、そのように、事務に知らせて下さい。今年は、桜の開花も少しおそめとか。5月の半ばの仙台は、よい季節です。お待ちしております。 念のため、先日のHPに記載した記事を一部、掲載しておきます。記事を記した当時は、東京会場の場所などが記されてなかったですが、確定しましたので、改めて、下記に記しておきます。
念のため、先日のHPに記載した記事を一部、掲載しておきます。記事を記した当時は、東京会場の場所などが記されてなかったですが、確定しましたので、改めて、下記に記しておきます。
では、たくさんの研究室の方々の来訪をお待ちしております。
わたなべしるす
********************************************
以下、一部、重複での掲載
1. 仙台開催
<入試説明会>
【日時】平成29年5月20日(土) 10:00~(予定)
【場所】片平キャンパス 生命科学プロジェクト総合研究棟1F 講義室
入試説明会の前半は、大学院の概要、奨学金、講義などの学務的なこと。先輩院生の普段の生活。後半は、各分野のポスターのところで説明会。平行して、各分野の持ち時間3min程度のshort talkも。渡辺研究室でも、研究内容、何を目指しているのか、他研究室との違いなどをお話しできるかと。。。ぜひ、いらしてください。
それに引き続き、研究室に移動して頂き、
<オープンラボ>
【日時】平成29年5月20日(土) 14:00~19:00(予定)
【場所】片平キャンパス 生命科学研究科本館 3F 303号室
研究室の様子、実験設備、大学院生などとの語らいの時間を設定します。一昨年から好評である、研究室見学の方々に、渡辺研のイベントである「ケーキ会」を楽しみながら、語らいの時間を設けるようにします。渡辺は、アルコールがだめなので、labではケーキ会がほぼ月一で開催と言うことになっており、1つの体験イベントとして。と思っておりますので。お待ちしております。どこのケーキなのか。それもお楽しみに。。。 2. 東京開催
2. 東京開催
<入試説明会>
【日時】平成29年5月13日(土) 13:30~15:30(予定)
【場所】フクラシア品川(高輪口) (6階) (https://www.fukuracia.jp/shinagawa2/)
研究科の概略と入試の説明。そのあと、希望する教員との面談。渡辺の研究室を希望する方がいらっしゃれば、東京会場にも伺うと言うことに。去年は、広報委員会委員長職を仰せつかっていたので、必ず、東京にも顔を出したのですが、東京会場を希望される方、また、お知らせしますので、申込をお願いすることになるかと。なお、東京会場には、「仙台の銘菓」をと思っています。仙台の銘菓???、お楽しみに。
昨年度からの継承で、仙台開催が土曜日の1日のみの開催に。もし、東京開催、仙台開催のどちらの日程にも都合が合わない方。是非、mailでご一報下さい。これまでも、そうした方に合わせて、別日程で研究室見学を設定していましたので、次年度も同様に行いたいと思いますので。 渡辺は元々は農学部の出身で、学部生、大学院生、助手の時代を東北大農学部で。そのあと、助教授の時代が、岩手大農学部で。2005年4月から、今のポジションに。今は、生命科学研究科と言いますが、渡辺のポジションをさかのぼると、1939年8月に設置された附属農学研究所になります。渡辺が学部生、大学院生の頃もありました。その後の改組で、全国共同利用施設・遺伝生態研究センターとなり、現在に至るというわけです。こうして、3つの異なる場所で研究を展開してきました。その間に重要視したこと。それは、研究室に閉じこもることなく、広く外の研究室と共同研究を行うこと。渡辺が学部生として、卒論実験を始めた1987年当時は、かなり珍しかったように思います。おまけに、学部生の実験のメインは、理学部生物・動物発生学・竹内教授の元で抗体作製実験を行い、その抗原などの精製には、東京大農学部・生物有機化学・磯貝助教授の所にも学部生なのに、数回伺って。。。外に出ると、知らないことも多いですが、その分、学ぶことも多いです。いずれも、その道のプロ、餅は餅屋と言うことですから。そんなで、岩手大時代、仙台に戻ってからも、できるだけ、多くの研究室と共同研究を展開できたことで、学生さんたちにも、色々な研究室のよいところを吸収してもらえたのでは。。。とじることなく、できるだけ、外とコラボすることが、学生時代を終えたあとの学生さんの色々な刺激になったり、色々な事へのチャレンジ精神を要請できているのかなと思っています。いずれ、そんな研究室です。
渡辺は元々は農学部の出身で、学部生、大学院生、助手の時代を東北大農学部で。そのあと、助教授の時代が、岩手大農学部で。2005年4月から、今のポジションに。今は、生命科学研究科と言いますが、渡辺のポジションをさかのぼると、1939年8月に設置された附属農学研究所になります。渡辺が学部生、大学院生の頃もありました。その後の改組で、全国共同利用施設・遺伝生態研究センターとなり、現在に至るというわけです。こうして、3つの異なる場所で研究を展開してきました。その間に重要視したこと。それは、研究室に閉じこもることなく、広く外の研究室と共同研究を行うこと。渡辺が学部生として、卒論実験を始めた1987年当時は、かなり珍しかったように思います。おまけに、学部生の実験のメインは、理学部生物・動物発生学・竹内教授の元で抗体作製実験を行い、その抗原などの精製には、東京大農学部・生物有機化学・磯貝助教授の所にも学部生なのに、数回伺って。。。外に出ると、知らないことも多いですが、その分、学ぶことも多いです。いずれも、その道のプロ、餅は餅屋と言うことですから。そんなで、岩手大時代、仙台に戻ってからも、できるだけ、多くの研究室と共同研究を展開できたことで、学生さんたちにも、色々な研究室のよいところを吸収してもらえたのでは。。。とじることなく、できるだけ、外とコラボすることが、学生時代を終えたあとの学生さんの色々な刺激になったり、色々な事へのチャレンジ精神を要請できているのかなと思っています。いずれ、そんな研究室です。 最後になりますが、研究面で渡辺の研究室が目指すのは、世界トップ水準・世界トップをgetする野望を抱き、達成すること。それが、人間を成長させる原動力になるのだと。。。そんな世界トップクラスという野望を渡辺研究室で達成してみませんか。あと、もう1つの研究室のアドバンテージ。それは、研究室がある片平キャンパスという場所が、仙台駅から徒歩15minと言うこと。来年の3月には、雨宮キャンパスにあった、農学部も青葉山新キャンパスへ。渡辺がいた頃の、町中にあると言うアドバンテージがなくなり。。。また、工学部、理学部、薬学部も青葉山に。と考えると、片平キャンパスで学べる利点は、地下鉄などを利用しなくても、自転車で、研究室まで来ることができると。いかがでしょうか。そんな立地条件。ということで、より多くの皆様をお目にかかれるのを楽しみにしています。もちろん、受験の学年である学部4年生だけでなく、学部の1~3年生、あるいは、高校生でも、見学をwelcomeですから。。。。
最後になりますが、研究面で渡辺の研究室が目指すのは、世界トップ水準・世界トップをgetする野望を抱き、達成すること。それが、人間を成長させる原動力になるのだと。。。そんな世界トップクラスという野望を渡辺研究室で達成してみませんか。あと、もう1つの研究室のアドバンテージ。それは、研究室がある片平キャンパスという場所が、仙台駅から徒歩15minと言うこと。来年の3月には、雨宮キャンパスにあった、農学部も青葉山新キャンパスへ。渡辺がいた頃の、町中にあると言うアドバンテージがなくなり。。。また、工学部、理学部、薬学部も青葉山に。と考えると、片平キャンパスで学べる利点は、地下鉄などを利用しなくても、自転車で、研究室まで来ることができると。いかがでしょうか。そんな立地条件。ということで、より多くの皆様をお目にかかれるのを楽しみにしています。もちろん、受験の学年である学部4年生だけでなく、学部の1~3年生、あるいは、高校生でも、見学をwelcomeですから。。。。
********************************************
【お知らせ】NHKおはよう日本・首都圏「くらしり」驚き! 春野菜の新常識、という番組で菜の花の紹介、4月1日(土)に放送(3/31)
2017年3月31日 (金)
今日で2016年度が終わり、ということは、今年は25%が終わったと言うこと。。。何ができたのか。あと、10hrほどあるので、もう少し片付けられるものを片付けて。。。2016年度の積み残しを少なくして、2017年度には新しいこととして。。。 そんな金曜日、2回目の「プレミアムフライデー」なのでしょうか。といっても何かできるわけでもないし。。。そんな時、NHKおはよう日本・首都圏「くらしり」の番組作成から問い合わせが。。。内容は「驚き! 春野菜の新常識」に関わるもの。タイトルは、HPで発見。首都圏に限定されているので、渡辺は見ることができません。首都圏に該当される地区から見ておられる方。お時間が許せば、明日の朝、7:30-8:00の「くらしり」で、料理研究家の浜内千波さんが、春野菜の新常識を紹介するとか。その時のちょっとした知恵袋でしょうか。参考意見として、お電話を頂き。。。どんな番組になるのか。。。ちょっと明日の朝、首都圏でテレビを見るのは難しそうなので、。。linkのあるHPで記事が上がれば、また、改めて、ご紹介を。というか、渡辺も何とか手に入れて、見てみたいと思いますので。。。多分、渡辺の名前は出ないと思うのですが。。。見て頂く方、その当たりを見て頂けると、うれしいですね。。
そんな金曜日、2回目の「プレミアムフライデー」なのでしょうか。といっても何かできるわけでもないし。。。そんな時、NHKおはよう日本・首都圏「くらしり」の番組作成から問い合わせが。。。内容は「驚き! 春野菜の新常識」に関わるもの。タイトルは、HPで発見。首都圏に限定されているので、渡辺は見ることができません。首都圏に該当される地区から見ておられる方。お時間が許せば、明日の朝、7:30-8:00の「くらしり」で、料理研究家の浜内千波さんが、春野菜の新常識を紹介するとか。その時のちょっとした知恵袋でしょうか。参考意見として、お電話を頂き。。。どんな番組になるのか。。。ちょっと明日の朝、首都圏でテレビを見るのは難しそうなので、。。linkのあるHPで記事が上がれば、また、改めて、ご紹介を。というか、渡辺も何とか手に入れて、見てみたいと思いますので。。。多分、渡辺の名前は出ないと思うのですが。。。見て頂く方、その当たりを見て頂けると、うれしいですね。。
という年度末最後の日のお知らせでした。
わたなべしるす
PS. この記事を書いている間に、今日で定年になる先生がご挨拶に。農学部の時代から実験をするための論文であったり、日々の活動の後ろ姿を拝見して、。。。そんな多くのことを学ばせて頂きました。ありがとうございました。
【お知らせ】東北大学附属図書館報 木這子(KIBOKO)に「大学生のレポート作成入門:図書館を活用したスタディスキル」の講義紹介(3/17)
2017年3月17日 (金)
3月上旬まであちこちに出張があり、月半ば頃まで体力回復と言うことか、たまった仕事を片付けるためか、いずれ、labでの書き物を。。。久しぶりの鹿児島出張で。以前は、コアSSHのダイコンコンソーシアムの運営指導委員なるものを仰せつかっていたので、年に2回ほど、鹿児島へ。早い春を感じたり、暑い夏だったり、。。いずれ、気候が変われば、植生も変化し、脳みそに違う刺激をもらって。。。仙台も今週初めの積雪が青葉山キャンパスには残っているようですが、さすがに、片平キャンパスは、そんなことはなくて。。。片平と青葉山で気温差が数oCは違うような。。。青葉山キャンパスと言えば、雨宮キャンパスにあった農学部も研究室などの引っ越しが終わり、圃場の土壌、つまり、表面の作土を削って、山の上のキャンパスに客土するとか。。。。戦後に、今の場所に農学部ができてからたくさんの作付けをして、作物の栽培も安定していたわけで。。。それを支えた「土壌」も引っ越しとは。。。そこまでして。。。というのは、雨宮キャンパスで11年ほどの学生、教員生活をしたからだと思うのですが。。。 その雨宮キャンパスにあった附属図書館も、もちろん、青葉山へ。図書と言うよりも雑誌のcopyにだけ行っていた時代。今のように、pdfをdownloadしたら、論文が読める時代でもなくて。。。いずれ、どの様に新しい情報を収集するのか、大型計算機センターと呼ばれる汎用型計算機に研究室のパソコン端末からつないで。さらに、大阪大学大型計算機センターのBIOSISというのだったと思います。key wordを入れて、色々な情報を集めていたような。。。今は、そんなことをしなくても、netで様々な検索ができる時代に。便利になったのは、もちろんよいことですが、targetしてpdfをdownloadするため、本当なら、興味はないけど、ページをめくっていて、その図版がかっこよくて、これは使えるとか、論文タイトルだけからでは、分からないような意外な論文を見つけるきっかけになったり。。。デジタルはデジタルのよさ。一方で、アナログもないと、実は、色々なものに対する感性を失うのではないかと、少々危惧しているわけですが。。。
その雨宮キャンパスにあった附属図書館も、もちろん、青葉山へ。図書と言うよりも雑誌のcopyにだけ行っていた時代。今のように、pdfをdownloadしたら、論文が読める時代でもなくて。。。いずれ、どの様に新しい情報を収集するのか、大型計算機センターと呼ばれる汎用型計算機に研究室のパソコン端末からつないで。さらに、大阪大学大型計算機センターのBIOSISというのだったと思います。key wordを入れて、色々な情報を集めていたような。。。今は、そんなことをしなくても、netで様々な検索ができる時代に。便利になったのは、もちろんよいことですが、targetしてpdfをdownloadするため、本当なら、興味はないけど、ページをめくっていて、その図版がかっこよくて、これは使えるとか、論文タイトルだけからでは、分からないような意外な論文を見つけるきっかけになったり。。。デジタルはデジタルのよさ。一方で、アナログもないと、実は、色々なものに対する感性を失うのではないかと、少々危惧しているわけですが。。。
そんな図書館とのつながりは、1, 2年の教養部生(昔は、そのように呼んでいました。)の時代は、試験前に利用するくらい。3年生でレポートを書くために、農学関係の図書を探したり。4年生以降は、新着雑誌、古くなった論文を綴ったもの(今であれば、雑誌のHPのアーカイブになるわけで)から、必要な論文をcopyするくらい。そのうち、pdfをdownloadできるようになったら、図書館に行くこともほとんどなくて。。。そんな折りに、以前、附属図書館本館の副館長をされていた医学部・柳澤教授に、1年生向けの講義をお願いしたいと。。。今年で5-7年目でないかなと。。。何度か、講義タイトルは変更されましたが、現在は「大学生のレポート作成入門:図書館を活用したスタディスキル」。その講義の紹介が、附属図書館が発行している「東北大学附属図書館報 木這子(KIBOKO)」(Vol.42, No.1 2017)で、取り上げられ、全体のおおよその構成が。。詳細は、このlink先が次年度のものに、近日中に変更されると思いますので。。。渡辺は2コマを使って「自然科学における論文作成の実際と文献利用」と言うことで、論文の執筆のための情報収集、論文を書くときに考えること(IFとか、open accessとか)、論文の書き方にも色々な発想があること、さらには、論文が公開されたら、どの様に評価されるのか。など、できるだけ、現代、これからの自然科学系の研究をする上でのリーダーとして必要と思えるような素養をできるだけ。。。もちろん、目指せ、top journalと言うことで、学生時代に指導してくれていた助手の先生に言われた「目指せNature!!」の心についても。 1年生始まったばかりの火曜日の5コマ目。渡辺なら、遊びたい盛りなので、パス。。。だったと思います。もし、こんな講義があれば。もちろん、渡辺の時代には、大学の教員の誰も入学前に知っている方はいませんでした。今は、そんなこともない時代。おもしろいと思う講義だけを聴いて、単位は必要ないという戦略も。そう、忘れていました、論文を書くためには、戦略が必要であると、そんなことも、お話しします。全ての講義を聴いて単位をgetするのも1つ、そうでなくて、これはおもしろそう、これは聴いたら、こんなことに活かせるなど、。。。そんなことを考えながら、受講をする方、トライしてみて下さい。渡辺のHPに過去記事もありますので。。。細かな講義日程は、また、改めてと言うことで。。。
1年生始まったばかりの火曜日の5コマ目。渡辺なら、遊びたい盛りなので、パス。。。だったと思います。もし、こんな講義があれば。もちろん、渡辺の時代には、大学の教員の誰も入学前に知っている方はいませんでした。今は、そんなこともない時代。おもしろいと思う講義だけを聴いて、単位は必要ないという戦略も。そう、忘れていました、論文を書くためには、戦略が必要であると、そんなことも、お話しします。全ての講義を聴いて単位をgetするのも1つ、そうでなくて、これはおもしろそう、これは聴いたら、こんなことに活かせるなど、。。。そんなことを考えながら、受講をする方、トライしてみて下さい。渡辺のHPに過去記事もありますので。。。細かな講義日程は、また、改めてと言うことで。。。
今回の「木這子(KIBOKO)」を読んで、なるほどと思った方、あれ??と思った方、ええーーー!!と思った方、色々だと。そんな何かを感じる感性を大事にしてもらえたら。。。それがよい論文を書く、研究をする第一歩ですから。。。
わたなべしるす
PS. 図書館のHPも少しずつ充実するとか。。。そんな情報が分かったところで、また、お知らせします。このHPから。その当たりは、少しお時間を。。。
PS.のPS. 来週は、科学者の卵養成講座の関係で海外出張。その関係で、昨日、木曜日に卒業式の繰り上げ版。いつだったかも行ったことがあるような。。。詳細は、また、学生さんから、記事が上がると思いますので。渡辺は最初だけいて、そのあとは、青葉山で会議で。。。。

