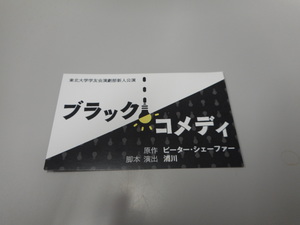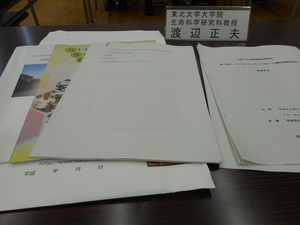こんにちは、工藤です。
最近暑いですね。ようやく夏が来ました。
熱中症等で体調を崩しやすい時期でもあるので、気を付けていきたいものです。
さてさて、今日は旧遺生研ソフトボール大会がありました。
院生会の大会時に岡本が書いてましたが、最初に計画していた日は天候が悪く延期となってしまいました。
しかし、第二予定日の今日はとても天候がよく最高のソフトボール日和でした!!
一回戦目は地圏
守備位置と打順は以下の通り
1 左 深沢
2 遊 高田
3 一 佐藤
4 投 工藤
5 二 鈴村
6 三 張
7 中 辺本
8 右 梶野
補 近藤(助っ人)
こっちの作戦としては深沢くんのやる気を出させた後に2~4番である程度点を取っておく感じでした。(適当)
試合直前に打順と守備位置を決めるというぐだぐだっぷりに適当さがにじみ出てますね。
あとお気づきの方もいるかもしれませんが、チームの主砲の体育会系コンビ岡本と祐太郎がいません。
いったいどうやって点を取るのだろう
結果的には、
深沢 アウト
高田 フライ(惜しかった)
佐藤 ヒット
工藤 ヒット
鈴村 アウト
案の定1点も取れませんでした。
その後、相手には1回に2点取られました。
次の相手の打順どうしようと考えていたら、
なんと!
なんと!!
張さんが2ベース打ちました!!!
張さんありがとう!!!
しかも女性陣もヒットを打ちなんとか1点取ることができました!!!
後攻は相手に5点取られて終戦かと思いきや
こちらの攻めで終わらせてくれることに。先攻でよかった...
審判がとてもやさしい。ぼくのボールもだいたいストライクにしてくれました。
相手の女性陣もボール球3回あっても必ず1度はバットを振ってくれた。みんなやさしい
そして最終回
今までがなんだったのかというくらいボコボコ点が取れました。
誰が何点取ったかはうろ覚えですが、高田さんと佐藤君と張さんが2ベースヒットを打ってくれて
女性陣もヒットを打ってくれて、打順も一周回って良い流れで進んでいきました。
6-7であと少しというとこで、ついに我らの最終兵器鈴村が登場
彼はこれまでの大会で幾度となく窮地を(ジャンケンで)救ってくれた救世主です。
今回も救ってくれ...と祈っているとボールがバットにジャストミート!!
僕と鈴村のボールがゴロにならずに打球が飛んでいったのを見たのは久しぶりです。
一瞬チームに希望の光が見えましたがショートに取られて試合終了。
結局6-7で負けてしまいました。とても惜しかったです。
今回は裏トーナメントがあったので、連戦で2回戦へ突入
2回戦目 宇宙
守備位置と打順は以下の通り
1 左 深沢
2 遊 高田
3 一 佐藤
4 投 工藤
5 二 鈴村
6 三 張
7 中 辺本
8 右 梶野
補 近藤(助っ人)
変わってませんね。
日差しが強く、皆疲れていました。
結果的には0-7で負けで、試合内容は特に言うことも無いくらいボコボコ。
1回で7点取られて5点ルールなんで消えたのかという思いでした。
そんなこんなで旧遺生研のソフトボール大会が終わりました。
写真が少ないのは選手全員が試合に出てて写真を撮る人がいなかったからですorz
やっぱ岡本と祐太郎は研究室に必要な存在だと再確認することができた大会でした。
M1クドウ
おまけ
参加賞いただきました
このあと辺本さんにバトンタッチします!!