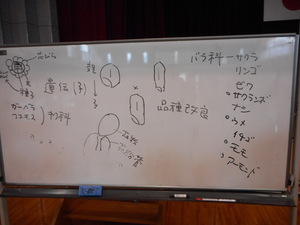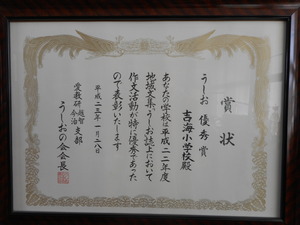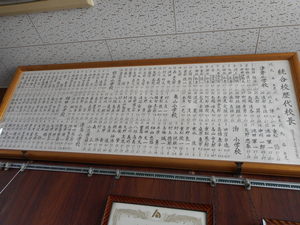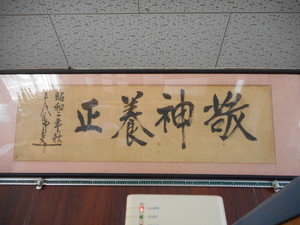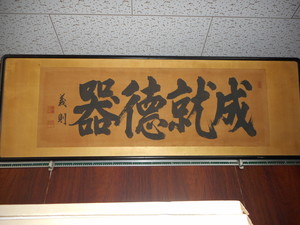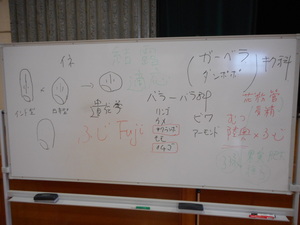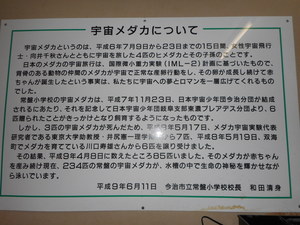こんにちは~今日の私のお昼はカレーでした。
ちなみにM2の岡本さんのお昼はグリーンカレーです。示し合わせたようにカレーでした。
さすが岡本ズ。運命共同体ですね(By まゆちゃん)
さて、今日から夏っぽくなりました仙台です。私も今日から半袖です。
意地でも七分袖って思っていたのですが、暑さには負けました。
そんな今日でしたが!いいこともありました。それはこれです。
 いえーい!まゆちゃんめっちゃいい笑顔。
いえーい!まゆちゃんめっちゃいい笑顔。
さくらんぼに引き続き、渡辺研は果物シーズンですね。なべさんありがとうございます。
 どこを食べても甘くておいしいメロンでした。
どこを食べても甘くておいしいメロンでした。
おいしかったのでバシャバシャ写真を皆で撮っていました。
こうすると、私が前回に引き続き、お菓子の記事しか書いてないような気がするので・・・
違うんですよ。たまたまなんですけど、お菓子ばっかりになってしまって。
なべ研お菓子ネタには困らないほどお菓子が常備されているので(幸せ)
なので!この間、バシャバシャ写真を撮ったことをお話ししたいと思います。
実は、私水族館が大好きなんです。
だから、この研究室に来る前になべもとさんが仙台うみの杜水族館で撮った写真を見た時、
「絶対ここに行きたい」と強く思ったんです。
そんな時、丁度2016年7月1日で開業一周年を迎える仙台うみの杜水族館でナイトモクテリウムというイベントがありまして、行ってきました~!ど~ん!

参加者はMock(真似事の、にせもの)とCocktail(カクテル)という単語が合わさったMocktailという新しいノンアルコールカクテルを片手に、館内を観ることが出来ます。
そして館内は、カラフルな照明を用いた演出、大水槽前のテーブルには各モクテルにちなんだカラーの水槽を展示やクラゲのカクテルなど、普段とは異なった大人の雰囲気でとても楽しく観ることができました。
 アザラシもMocktailに興味津々でした。そして、私が一番撮りたかった写真はこれです
アザラシもMocktailに興味津々でした。そして、私が一番撮りたかった写真はこれです
 そう!大水槽前でドーンと!撮ってみたかったのです。撮ってくださった方、本当にありがとうございました。大満足です。
そう!大水槽前でドーンと!撮ってみたかったのです。撮ってくださった方、本当にありがとうございました。大満足です。
仙台に来てまだまだ日が浅いですが着々と探索できている気がします。また何かしらのイベントがあればぜひ参加したいですね!
おわり
M1 岡本(美)