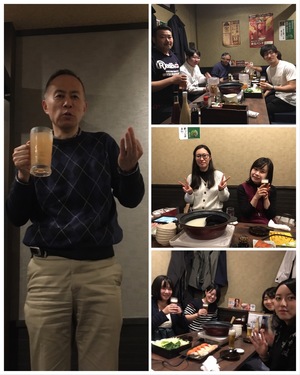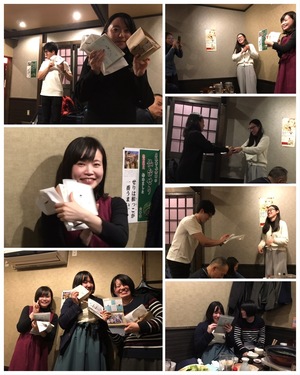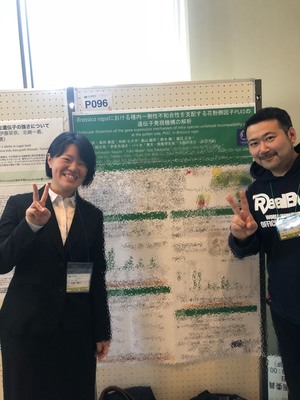なべさんは追いコンの次の日から、近年恒例になっている、アメリカ・リバーサイド出張に行かれていました(科学者の卵養成講座の関係で)。
渡米前は、だいぶ体調が悪そうだったなべさんですが、本日無事に帰国され、スタッフ・学生一同ほっとしてます。今回もたくさんお土産をもってかえって買ってきてくださいました、ありがとうございます!
まずは、ギラデリ・チョコレート・カンパニーのダークチョコ詰め合わせ。
中にはこんな感じのチョコがたくさん入っています。
そんなに苦くなく、甘すぎず、すっきりとしたくちどけでした。
最近、カカオポリフェノールが認知症の予防に良いという話も聞きかじります、せっせと取らなくては。。。
ギラデリ(Ghirardelli)はアメリカの老舗チョコレート店、元祖はイタリア系の方だそうです。
サンフランシスコにギラデリ・スクエアというチョコレート工場を改装したショッピングモールがあり、カフェで巨大なパフェをガッツリ堪能できるようです。アメリカ版の白い恋人パーク、みたいなものでしょうか。行ってみたいですね。
また、佐藤先生から、とのことで、イースター限定のロリポップ詰め合わせ。いつもありがとうございます!
See's candiesというと、カリカリした食感のPeanut Brittleを想像してしまいます(ピーナツをカリカリしたキャラメルで包んだもの、カロリー爆弾ですがおいしい、背徳のお菓子です)。
こちらもカリカリしたものを想像していましたが・・・。
ガチの棒付きアメ(ロリポップ)でした。いろいろな味がありますが、こちらはバタースカッチ味。不二家チェルシーが好きな方なら、絶対好きな味だと思います。美味しくて、かなり長持ちします(30分以上舐められます)。かじると銀歯が取れそうな気がしますので、ひとりで黙々と食べたいですね。
イースターは磔刑に処されたのち3日で蘇ったとされる、イエスキリストの復活祭としてキリスト教圏で重要なお祭りです。日本ではあまりなじみないお祭りですが、最近、ハロウィン同様、ポピュラーになってきましたね。イースターは春分の日以降、最初の満月から数えて最初の日曜日、という不定祝日になっており、今年は4月21日になっているようです。キリスト教圏では、家族でご馳走を食べたり、その前後はお休みになる重要な祭日です。
子供たちが卵を使った遊びをするのがクリスマスと違う特徴で、ゆで卵や卵型のチョコレートやお菓子にデコレーションしたいイースターエッグを探す遊びをしたり、イースターバニーを飾ったりします(生命のはじまりである卵も、多産なうさぎも、豊穣のシンボルですから、復活祭には重要なんだと思われ)。だからイースターというと、卵のお菓子やウサギのお菓子がじゃんじゃん店頭に並ぶわけなんですね。
さて、「イースター」という名称はゲルマン神話の春の女神「オスタラ」から来ているとされており、オスタラは太陽の上る東を表すと。ま、ぶっちゃけ、世界的にあちこちにある、春分過ぎて日が長くなったぜ!もうすぐ種まきの季節だぜイエーイ、という祭りがキリスト教圏に習合されているのかと思われます。日本での春彼岸みたいなものかと。
我々の時代のお彼岸というと、おじいおばあが孫や親類縁者の子供たちにお菓子をじゃんじゃん振りまいてくれたものでした(親は苦笑いでしたが、我々はほくほくしたものです)。国は違えど、子供たちにお菓子を与えたい、食べさせたい、喜ばせたい、という気持ちは一緒なのではないか、などと思ったりしますね。
そんなこんなの復活祭スペシャルお菓子ですが、お菓子の力でなべさんの体調もイエスキリストの如く復活してくれるといいなあ、と思う昼下がりでした。
まだまだ忙しい年度末ですが、皆さんも体調気を付けていきましょう!
マスコ