きょう、12月8日は、農事など雑事をしまう日(事納め)とか。年末までにまだまだやることがありすぎる。少しずつ片付けないと。。。ただ、農学部で学んでいても、こんなことは、。。知らなかった方が、悪いのだが。。。。歴史に目を向けると、色々なことが起きている。へーと思うこと、そんなこともあったと言うこと。いろいろ。そんな歴史に目を向ける理由は、また、年末までのどこかで。いつもの調子なのですが。。。ただ、歯ブラシの交換日、というのも。ちゃんと歯磨きをしないと。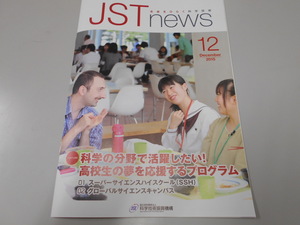 お知らせを受けたのは、昨日だったのですが、何とも時間がなくて。。。教育プログラムでお世話になっているJST。以前は、SSHの何かの特集で掲載されたこともあるのですが、「JST news 未来をひらく科学技術」の12月号に、02. 心ときめかす!未来の科学者たち グローバルサイエンスキャンパスへ、と題して、特集記事が。SSHのことは知られていても、GSCの単語は、なにそれ??ということがほとんど。略語でなくて、グローバルサイエンスキャンパスといっても、知らないことが多いのでは。名前すら。。。Googleで、略語で入れると、1 page目には出てきますが、。。。。もう少し戦略的な工夫が必要なのでしょうか。自前のHPでないので。何ともし難いのですが、。。。そうそう、東北大のGSCは、飛翔型「未来の科学者の卵養成講座」、是非、一度、HPをご覧下さい。初めての方は。ぜひぜひに。
お知らせを受けたのは、昨日だったのですが、何とも時間がなくて。。。教育プログラムでお世話になっているJST。以前は、SSHの何かの特集で掲載されたこともあるのですが、「JST news 未来をひらく科学技術」の12月号に、02. 心ときめかす!未来の科学者たち グローバルサイエンスキャンパスへ、と題して、特集記事が。SSHのことは知られていても、GSCの単語は、なにそれ??ということがほとんど。略語でなくて、グローバルサイエンスキャンパスといっても、知らないことが多いのでは。名前すら。。。Googleで、略語で入れると、1 page目には出てきますが、。。。。もう少し戦略的な工夫が必要なのでしょうか。自前のHPでないので。何ともし難いのですが、。。。そうそう、東北大のGSCは、飛翔型「未来の科学者の卵養成講座」、是非、一度、HPをご覧下さい。初めての方は。ぜひぜひに。
記事の集合写真は、東北大の青葉山キャンパス。というか、工学部。渡辺はこの写真の頃、出張で。どこへだったか。すでに記憶の彼方。安藤先生を始め、多くの受講生が取材を受けたようです。渡辺が担当していた受講生のところが終わったら、出張でぬけてしまったので。いずれ、好評だったですが、渡辺のコメントは少しばかり。。。いつもの餅は餅屋のようなことをしゃべったはずですが、洗練された言葉になっているようです。お時間の許す方、是非、ご一読頂ければ、幸甚です。 このたまごで育った受講生とどこかで共同研究ができるまで、何とか、まともな研究者人生を送らないといけない、それも渡辺の使命なのだと。。。そんなことを思いながらの。。。12月8日、「・・―・・ ・・・」。。。。でした。
このたまごで育った受講生とどこかで共同研究ができるまで、何とか、まともな研究者人生を送らないといけない、それも渡辺の使命なのだと。。。そんなことを思いながらの。。。12月8日、「・・―・・ ・・・」。。。。でした。
わたなべしるす
PS. 掲載のことを教えて頂いたのは、SSHでお世話になっている福島高校の橋爪先生。ありがとうございました。危うく。。。でした。
PS.のPS. ある年の12月8日には、凶弾に倒れた方が。。。と、とある新聞に。あれからそんなに時間がたつのだと。。。年は、何とかである。。。
【新聞・雑誌掲載】「JST news 未来をひらく科学技術」に飛翔型「科学者の卵養成講座」の特集記事掲載(12/8)
2015年12月 8日 (火)
【お知らせ】展開ゼミの10月5日、19:00現在の申し込み状況(10/5)
2015年10月 5日 (月)
渡辺の展開ゼミも今週がはじめとなります。先週金曜日の夕方に、あと3名で枠がいっぱいになるというお知らせをしました。今日の夕方までに、2名の申込があり、結果、18:40現在、19名です。ありがとうございました。9月30日の記事、9月2日の記事を参考にして、来週のオリエンテーションに遅れないようにして下さい。
ですので、展開ゼミに参加できる枠はあと1名となりました。また、人数が大きく変化したら、お知らせします。
わたなべしるす
【お知らせ】展開ゼミの10月2日、16:50現在の申し込み状況(10/2)
2015年10月 2日 (金)
昨日の22:00にもHPに記事を書きましたが、渡辺が行う展開ゼミへの申し込みが夜中にも1名あり、16:50現在、17名となっております。ありがとうございました。 ですので、あと3名の応募を先着で受け付けます。一昨日の記事、先月の記事を参考にして、来週のオリエンテーションに遅れないようにして下さい。
ですので、あと3名の応募を先着で受け付けます。一昨日の記事、先月の記事を参考にして、来週のオリエンテーションに遅れないようにして下さい。
申し込みの学部は多様性に富んでいて、文系、理系、ほぼ半数という状況です。昨年度よりも記事を書くのが、便利に改良しましたし、できるだけ、外に開いた講義にしたいと思いますので。どうやら、このままの数字で、来週を迎えるのか、その当たりがはっきりしません。また、人数が大きく変化したら、お知らせします。
わたなべしるす
PS. 渡辺が出前講義をやっている関係で、申し込みをしてくれた方々も。ありがたいことです。再会を楽しみにして。。。もちろん、新しい受講生の方も。。。お待ちしております。
【お知らせ】展開ゼミの10月1日、22:00現在の申し込み状況(10/1, 22:10追記)
2015年10月 1日 (木)
今日の夕方にもHPに記事を書きましたが、興味を持っている方からのmailであったり、直接の申し込みのmailを夕方から夜にかけてずいぶん頂きました。ありがとうございました。
おかげさまで、本日、22:00現在、15名の申し込みとなりました。ですので、あと5名の応募を先着で受け付けます。昨日の記事、先月の記事を参考にして、来週のオリエンテーションに遅れないようにして下さい。
 講義形式がどの様なものか。。。。悩ましくて、HPにもかけないのですが、知っている方はいるはずです。考えてみて下さい。去年もこの展開ゼミをやっていますし、同様の基礎ゼミも。ということは。。。縦の繋がりを大事にして下さい。この情報時代を生き抜くためにも。。。
講義形式がどの様なものか。。。。悩ましくて、HPにもかけないのですが、知っている方はいるはずです。考えてみて下さい。去年もこの展開ゼミをやっていますし、同様の基礎ゼミも。ということは。。。縦の繋がりを大事にして下さい。この情報時代を生き抜くためにも。。。
また、人数が大きく変化したら、お知らせします。
わたなべしるす
PS. この記事をuploadしているとき、また、1名の応募が。。。。あと、4名です。明日には、満席になる可能性が。興味のある方、お急ぎください。
【お知らせ】学部講義・展開ゼミの10月1日、15:10現在の申し込み状況(10/1)
2015年10月 1日 (木)
昨日も夕方に展開ゼミの申し込み状況のお知らせをしましたが、後期が始まったからでしょうか。昨日から4名の申し込みをいただき、現時点で、12名です。一気に4名増えたのもあり、週明けでなくて、HPに記載しました。なお、今まで申し込んでくれ、返事を受け取っている方は、受講可能です。お待ちしております。
 ですので、あと8名の応募を先着で受け付けます。前回記事、前々回の記事を参考にして、来週のオリエンテーションに遅れないようにして下さい。
ですので、あと8名の応募を先着で受け付けます。前回記事、前々回の記事を参考にして、来週のオリエンテーションに遅れないようにして下さい。
週末にも応募が多くなるときは、随時、ここからお知らせします。どうしようかと思っている方は、このHPを注視してださい。、
わたなべしるす

