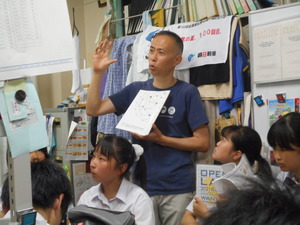通常、天気は西から東へと変化する。なので、情報を見ていると、左から右へとなる。週末に通過した台風12号は東から西へ。記録を取り始めてから初めてのことだとか。偏西風があることを考えると、極めて不思議な現象であった。このことと関係があるのか、台風の風は反時計回りに吹き出しているので、西から東への移動の方が威力は大きいような。。。物理を厳密に理解してないので、感覚の世界であるが。。。こんな不思議な進路になったことを予想できたのも、ある種の計算機のおかげ。コンピューターといえばよいのだろうか。プロ野球などのdata解析等で、その技巧は遺憾なく発揮されている。さらには、スポーツ全般にもらしい。そんなコンピューターというかAIというか、そんなものと動物が交流できるというのは、そこまでAIが近づいたと言うことなのか。いずれ、痛恨の極みとならないように、こうした技術をfollowしておかないと。。。
 大学に入った頃、植物に遺伝子導入などと言うことは、想像もできなかった。そのうち、できるようになってきたが、研究材料のアブラナ科植物ではやっぱり困難を極める。一方で、遺伝子組み換え作物(GMO)の社会からの風当たりは強い。そんなで、究極の奥義ともいえる「遺伝子編集」がどう扱われるのか、日本と欧州で主導権争いというのか、方向性の違いなのか。いずれ、農作物を扱うものとしては、研究からその先の実際のものへの応用という点では、判断がどの様になるのか、気になるところである。いずれ、新しい技術に果敢に挑戦することが大事なのであろうが。。。遠き将来を見すえて。。。
大学に入った頃、植物に遺伝子導入などと言うことは、想像もできなかった。そのうち、できるようになってきたが、研究材料のアブラナ科植物ではやっぱり困難を極める。一方で、遺伝子組み換え作物(GMO)の社会からの風当たりは強い。そんなで、究極の奥義ともいえる「遺伝子編集」がどう扱われるのか、日本と欧州で主導権争いというのか、方向性の違いなのか。いずれ、農作物を扱うものとしては、研究からその先の実際のものへの応用という点では、判断がどの様になるのか、気になるところである。いずれ、新しい技術に果敢に挑戦することが大事なのであろうが。。。遠き将来を見すえて。。。
台風12号の話をしたが、農業への打撃は今回も甚大である。季節ものと言うこともあるが、やり直しがきかないというか、。。収穫前の秋の果樹農園。ナシ、ブドウ当たりであろうか、どうなるか、心配なところがある。被害が最小限であったことを祈るばかりである。そんなものを改善することにつながるのであろうか。通常の作物でなくて、藻類からタンパク質、ビタミン類を摂取すると。。。運営のしようによっては、威力は絶大であろう。この藻類農園の運営にもAIとの融合はできるであろう。ただ、本当の主導権を握るためには、さらなる柔軟性のある異分野の「技巧」が必要になると思う。それが何なのか、それを探すことが要諦なのであろう。そんなことよりも大事なこと。7月になってからだろうか。仙台でまともに雨が降っていない。街路樹もかなり厳しそうである。出穂期に当たるこの時期、水田にも水が必要に。。。雨乞いでもしないといけないのではないだろうか。。。台風のような威力はなくてよいが、それなりの降水があることを祈りつつ、7月を終わることにする。というか、残されている宿題を片付けないと。夏休みが。。。やばくなりそうである。

わたなべしるす
PS. 紙面を飾っている写真。ここ数日での頂き物。ありがとうございました。ごちそうになります。明日はまた、猛暑日になるという仙台。脳みそを一服させる清涼剤になるかと。。。ありがとうございました。
PS.のPS. 7月31日, 17時42分頃, 福島県沖(M5.4)の地震がありました。久しぶりの仙台市青葉区が震度3という搖れでしたが、研究室内外で、特に被害はありませんでした。30minほど前まで、オープンキャンパスの帰り道に、昨年度の重点コース受講生だった後藤さんが研究室に来てくれていました。写真を撮り忘れて、。。失敗、反省。