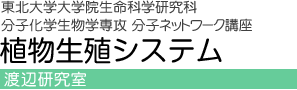【お知らせ・緊急告知】2025年度「中級アカデミック・ライティング」、10/6(月)の5コマ目でスタート(9/29)
2025年9月29日 (月)
教養の講義を担当しているのは、「学問論演習」とこの「カレントトピックス」である「中級アカデミック・ライティング」。正式名称は「中級アカデミック・ライティング-現代的課題に関する文献講読とレポート作成-」。講義は月曜日の5コマ目という絶対的に不利な講義枠。とはいえ、文章を書くことを身につけるのは、大学人として必須の事象。大変かもしれないですが、是非、チャレンジを期待しています。
 15回の講義を渡辺を含めた4名の教員が担当し、渡辺は10/20, 27の2回のみを担当します。自然科学系の科学論文がどのように書かれているのか、図書館が有する膨大なdatabaseを利用して、文献を調査する、そんなことを講義・実習します。2回目の実習はdatabaseに詳しい図書館の方が検索実習を担当してくれます。その道のプロが講義・実習するので、絶対的に不利な講義枠ですが、いかがでしょうか。
15回の講義を渡辺を含めた4名の教員が担当し、渡辺は10/20, 27の2回のみを担当します。自然科学系の科学論文がどのように書かれているのか、図書館が有する膨大なdatabaseを利用して、文献を調査する、そんなことを講義・実習します。2回目の実習はdatabaseに詳しい図書館の方が検索実習を担当してくれます。その道のプロが講義・実習するので、絶対的に不利な講義枠ですが、いかがでしょうか。
それ以外の3名の先生方から、人文社会科学系の研究論文、実際の論文執筆に対する考え方などの講義があります。加えて、提出したレポートに教員がコメントし、多様な角度から示唆・コメントをくれる希な講義です。5コマ目で他にもこれという講義と重なる等あるかも知れないですが、しっかりした文章力を養成することは、一生の宝物。是非、受講を検討してみてください。渡辺の講義は10/20, 27の2回。お目にかかるのを楽しみにしています。
(講義の詳細は、以下の画像をクリックしてください、東北大学図書館のHPが開きます)

わたなべしるす
【お知らせ】第14回学生懸賞論文募集(クミアイ化学工業)(9/3)
2025年9月 3日 (水)
仙台の昨日の最高気温は、37.4oCという最高気温の記録更新。今日は少し涼しいですが、33.0oC。40年くらい前に仙台に来たときには考えられない酷暑。今年のコメの作柄もこの高温でよくないのではと気になるところ。もちろん、それに連動した新米の値段も。地球環境の極端な変化にも耐えるような仕組み、品種、肥培管理などが必要となるのだろうと。

そんな折、今の農業を考える一助になるようなお知らせを頂きました。クミアイ化学工業による「第14回学生懸賞論文募集」。
(1) 応募資格は、大学、大学院、農業大学校、短期大学、専門学校、に在籍する学生(グループによる共同執筆も可)。
(2) 論文のテーマは、『食料と農業の未来』―持続可能な社会を実現させるために―。(食料や農業に関連した題材を取り上げ、自由に論じてください。)
(3) 文字数は、4,000字以上10,000字以内。渡辺の展開ゼミ、学問論演習を履修した方にはそれほど厳しくない文字数。
(4) 詳細な募集要項はこちらから。
この暑さはこの秋も続くようで秋作の野菜などの収穫にも影響が出ることは必至。是非、農業、食糧をこの機会に考えて見てはいかがでしょうか。〆切は10/31(金)の当日消印有効。もちろん、mailでの送信も可。特別賞はなんと「お米一年分!!」。是非、チャレンジを。

わたなべしるす
【お知らせ】2025年度 生命科学研究科 秋の説明会; 9/20(土)に対面で実施(9/3)
2025年9月 3日 (水)
春にも実施しましたが、「生命科学研究科 説明会」の秋versionを9/20(土)に実施します。次年度から渡辺の研究室で大学院生をやりたい方を募集します。それに伴う説明会は、
【日時】2025年9月20日(土) 10:00~17:00 (受付開始 9:30~)
全体説明 10:00~
対面でのポスター紹介 11:00~12:30
オープンラボ 14:00~17:00
(12:30~14:00は移動、お昼休憩)
【参加登録】
説明会は一応、事前登録制ですので、下記フォームより参加登録を行ってください。(登録〆切 9月18日(木) 17:00)
参加申し込みフォーム はここから。
【全体説明会場】
東北大学片平キャンパス 生命科学プロジェクト総合研究棟
(片平キャンパスD-4)
という形式で行います。

春5月と同じようにオープンラボでは、生命科学研究科本館3Fの303室で、ケーキ、お茶などを用意してお待ちしております。研究室の雰囲気、学生さんとの議論などもできるようにしております。是非、お立ち寄りください。
わたなべしるす