
大学院をメインに受け持っていると、来年からのメンバーがどうなるのか、大学院の入試が終わらないと、確定しないところがあります。昨今の少子化、大学院重点化などで、受験生の確保が大変になっています。
その意味で、今年はtotal 4名の新しい博士課程前期の学生が、来年の4月から来てくれることが確定しました。何よりうれしい限りです。4月には、labも新しいところに引っ越し、心機一転でありますし、その意味では、新入生にも良い環境で仕事をしてもらえると思っています。お待ちしております。
あとは、スタッフの方がどれだけきちんとサポートして、よりよい人材として社会に貢献できるような形で、リリースすると言うことがこちらの責務であり、その意味では、植物ではありますが、生殖という形質を扱っており、よりよい形質をもった後代を以下に残すかと言うこと、これはまさに、同じことなのかもしれません。できるだけのことをしたいと思います。とともに、新入生が来ることを楽しみにしております。
わたなべしるす


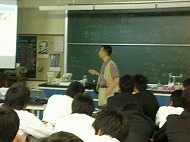 沖縄県立八重山高校で、自家不和合性、生殖の不思議、品種改良などをテーマに講義を行ってきました。今回の沖縄、それも最南端の高校での出前講義を設定していただいたのは、生命学研究科のサイエンスエンジェル(SA)の学生さんのおかげです。まず、最初にその方々に感謝します。
沖縄県立八重山高校で、自家不和合性、生殖の不思議、品種改良などをテーマに講義を行ってきました。今回の沖縄、それも最南端の高校での出前講義を設定していただいたのは、生命学研究科のサイエンスエンジェル(SA)の学生さんのおかげです。まず、最初にその方々に感謝します。 仙台市教育委員会との提携で、今日は「鹿野小学校」で「出前授業」でした。国道286号線沿いにあり、何かで通るとよく見かけることはありましたが、講義で伺うのははじめてでした。1, 2校時が授業の時間でした。先週の吉成小学校同様に、リンゴをモデルとした、受粉、受精、自家不和合性、果実の成熟など、小学校5年生には少し難しい課題ではありましたが、一生懸命講義を聴いてくれて、質問ももらいました。朝早くの講義と言うこともあり、後半になるほど、生徒たちのエンジンもかかってきて、最後のリンゴの観察では、食い入るように見ていたのが印象的でした。
仙台市教育委員会との提携で、今日は「鹿野小学校」で「出前授業」でした。国道286号線沿いにあり、何かで通るとよく見かけることはありましたが、講義で伺うのははじめてでした。1, 2校時が授業の時間でした。先週の吉成小学校同様に、リンゴをモデルとした、受粉、受精、自家不和合性、果実の成熟など、小学校5年生には少し難しい課題ではありましたが、一生懸命講義を聴いてくれて、質問ももらいました。朝早くの講義と言うこともあり、後半になるほど、生徒たちのエンジンもかかってきて、最後のリンゴの観察では、食い入るように見ていたのが印象的でした。
 今年も仙台市教育委員会と東北大学との間で提携されている「出前授業」の季節になりました。今年の最初は、吉成小学校でした。農学部で助手をしたり、岩手大の助教授の頃、隣の南吉成に、東北インテリジェントコスモス関連企業の「採種技術研究所」があり、そこの所長を指導教官であり、恩師である東北大名誉教授の「日向博士」がされていたこともあり、近くには伺うことはありましたが、この場所に小学校があったのは、最近知りました。
今年も仙台市教育委員会と東北大学との間で提携されている「出前授業」の季節になりました。今年の最初は、吉成小学校でした。農学部で助手をしたり、岩手大の助教授の頃、隣の南吉成に、東北インテリジェントコスモス関連企業の「採種技術研究所」があり、そこの所長を指導教官であり、恩師である東北大名誉教授の「日向博士」がされていたこともあり、近くには伺うことはありましたが、この場所に小学校があったのは、最近知りました。