 SSH九州地区発信の「ダイコン多様性研究コンソーシアム」(機関校:鹿児島県立錦江湾高校)の指導委員を務めることから、参加校が一堂に会し、研究プロジェクトの発表、評価、指導などを8月に続いて行いました。
SSH九州地区発信の「ダイコン多様性研究コンソーシアム」(機関校:鹿児島県立錦江湾高校)の指導委員を務めることから、参加校が一堂に会し、研究プロジェクトの発表、評価、指導などを8月に続いて行いました。
https://www.ige.tohoku.ac.jp/prg/watanabe/diary/2009/08/19185306.php
https://www.ige.tohoku.ac.jp/prg/watanabe/news/2009/10/17152658.php
昨今の新型インフルエンザの影響でしょうか、いくつかの参加できない高校もありましたほとんどの高校が参加され、発表・意見交換ができたのは、有意義でした。
何より、8月から開始し、4ヶ月という間で興味深いdataを出していた高校生たちの研究に対する真摯な態度は、われわれも見習わないといけないと痛感しました。特筆すべき点は、農業高校との連携で、市場価値があると思えるような「ダイコン」が栽培され、低温処理を施し、開花させ、交配を試みたり、植物体に「動かす」というストレスを与えているような実験など、基本的であったり、おもしろい発想で研究をされているのは、興味深いものでした。
実験・研究をするというと、どうしても「遺伝子」、「生物活性」など、今のはやりのようなことに目がいきがちですが、それも大事ですが、生物学の基本はやはり、形態観察だと思います。野生型と変異体の違い、品種間の差異がどこにあるのか、ということを「観察する目」を持つことは、これから研究者を目指す若い人たちには重要だと思います。ぜひ、このダイコン研究を通して、そうした観察眼を身につけてください。
1年ごとの申請・採択という厳しい枠のようですが、ぜひ、来年以降もこのコンソーシアムが展開され、さらなる発展を見ることをできるのを楽しみにしております。
わたなべしるす



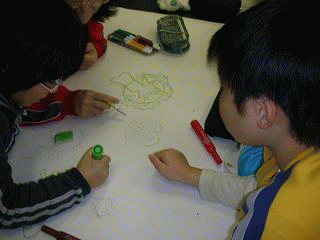 東北大と仙台市教育委員会の連携による出前講義が発展し、今年は川平小学校の科学工作クラブの研究指導を2回行いました。1回目は、10/21のキャベツとブロッコリーが同じ種(Brassica oleracea)である、という講義で、
東北大と仙台市教育委員会の連携による出前講義が発展し、今年は川平小学校の科学工作クラブの研究指導を2回行いました。1回目は、10/21のキャベツとブロッコリーが同じ種(Brassica oleracea)である、という講義で、 SSHの関係で福島高校に伺うのは、4回目となりました。今回は、渡辺以外に、分野の異なる大学、研究所の「博士」という学位を持っている3名の講師が、どのようにして、学位を取り、研究者となったかという「キャリア教育」が行われ、講師として呼ばれました。他の2名の講師としては、電気・電子・プラズマという分野を研究されている、東北大学大学院工学研究科の安藤教授、海底堆積物・地球化学・南極観測というキーワードが当てはまる海洋研究開発機構の原田リーダーでした。渡辺が植物、遺伝、多様性ということなので、講師陣もきわめてheteroで、3hrを超える講義と討論会でしたが、あっという間に終わったのでした。
SSHの関係で福島高校に伺うのは、4回目となりました。今回は、渡辺以外に、分野の異なる大学、研究所の「博士」という学位を持っている3名の講師が、どのようにして、学位を取り、研究者となったかという「キャリア教育」が行われ、講師として呼ばれました。他の2名の講師としては、電気・電子・プラズマという分野を研究されている、東北大学大学院工学研究科の安藤教授、海底堆積物・地球化学・南極観測というキーワードが当てはまる海洋研究開発機構の原田リーダーでした。渡辺が植物、遺伝、多様性ということなので、講師陣もきわめてheteroで、3hrを超える講義と討論会でしたが、あっという間に終わったのでした。 「科学者の卵」での講義がきっかけとなり、「キャリア教育」を外部で行うことになりました。昨日の福島高校に続いて、連続の講義です。科学者の卵での講義の前に、SSHプログラムを行っている和歌山県立日高高校での講義から数えて、8回目となり、受講生も、1,000名を超えました。
「科学者の卵」での講義がきっかけとなり、「キャリア教育」を外部で行うことになりました。昨日の福島高校に続いて、連続の講義です。科学者の卵での講義の前に、SSHプログラムを行っている和歌山県立日高高校での講義から数えて、8回目となり、受講生も、1,000名を超えました。