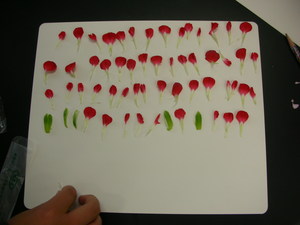出前講義を行っていると、研究として何をするのがよいのか、大学、研究室を選ぶときなどについて、質問を受けることがある。そんなときに、研究をやるのであれば、世界トップ、つまり、新しいことをやることと答える。ただ、何を持って新しいと評価するのか、いつまでも新規なことというのは、難しい。ただ、植物科学の研究者であれば、Nature, Cell, Scienceというtop journalを目指すことであろうと。。。ただ、最近は、h-indexなどの個人評価などの方法もあるが、これを説明することは難しい。。。
では、新しいこと、そうでないことを評価しないといけなくなるこれから、評価をする側、される側、考えさせられる。日本人は新しいことを評価することが、苦手なのかもしれない。今までのことを追従することは簡単であろう。何も言わないで、あうんというのが、日本人というのも関係しているのであろう。
そうでなく誰に何を言われても、これだから、こうした評価をするべきであるという、何らかの基準があると、こうした混迷期の評価に耐えるものができるような気がするが、すぐにはできないのかもしれない。ただ、そうはいってられないで、すぐにも評価しないといけないものもたくさんある。そんなことを常に気にしながら、日々、自分を反省し、新しいことを目指して、教育研究を行い、そして、その基盤にはどのような評価を受けても高であると言えるような毎日を送ることが大切なのであろうと、感じる今日この頃である。
わたなべしるす

では、新しいこと、そうでないことを評価しないといけなくなるこれから、評価をする側、される側、考えさせられる。日本人は新しいことを評価することが、苦手なのかもしれない。今までのことを追従することは簡単であろう。何も言わないで、あうんというのが、日本人というのも関係しているのであろう。
そうでなく誰に何を言われても、これだから、こうした評価をするべきであるという、何らかの基準があると、こうした混迷期の評価に耐えるものができるような気がするが、すぐにはできないのかもしれない。ただ、そうはいってられないで、すぐにも評価しないといけないものもたくさんある。そんなことを常に気にしながら、日々、自分を反省し、新しいことを目指して、教育研究を行い、そして、その基盤にはどのような評価を受けても高であると言えるような毎日を送ることが大切なのであろうと、感じる今日この頃である。
わたなべしるす