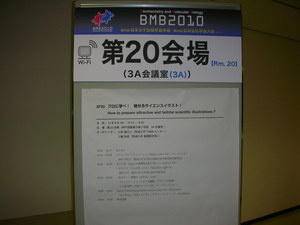8/18-20で開催された、コアSSH「ダイコン多様性研究」の今年度の研究成果の発表会があり、その発表会に伴い、今後の方向性などを検討する、運営指導委員会も開催されました。ちょうど訪問中が鹿児島でも今年一番の寒さらしく、。。。特に、寒いと感じたのは、室内。北日本であれば、二重サッシ、暖房は十分にされているのですが、温暖な鹿児島では、暖房は不十分。そういえば、自分が高校まで過ごした、四国・今治でも同じことだったような。そんな寒さも吹っ飛ばすような高校生のレベルの高いポスタープレゼンテーションと討論会でした。
注目すべき点は、数多くありました。まず、夏のプレゼンから研究がずいぶん進んでいたこと。さらに、多くの高校で、現物のプレゼンがあったこと。つまり、ダイコン、そのものがあったことです。実際に食したいと思えるような質の高いものを提示していたのは、やはり連携校である、農業高校の生徒さん。さすがだと思いました。普通高校の生徒さんでも立派に育てている高校もあり、最後はダイコンをどこまで観察し、愛情を注いでいるかという点なのかもしれません。また、これまでいろいろなところで話をしてきた、繰り返し実験、統計処理の重要性を理解して、プレゼンテーションができている高校もありました。ぜひ、他の高校でも、お願いします。それから、日々の活動がわかるように、コンソーシアムのHPが用意されているのですが、そこにuploadしたり、それに対してコメントしたり。こうした交流が、将来の研究で大いに役立つことだろうと。
 もちろん、いくつか気になる点も。重厚な研究をしているのですが、きちんと説明をしたいということで、プレゼンの原稿を読んでいるところもありました。せっかくですから、ぜひ、原稿を覚えるくらい練習をして、その場での応対をすることをと思います。また、これは多くの高校でそうですが、表と図のプレゼンには大きな違いがあります。表の場合には、表の上に、表1. *****というような説明を入れるということ。それに対して、図の場合には、図の下に、図1. *****という説明を入れることが約束事です。ぜひ、覚えて、次のプレゼンに活かしてください。
もちろん、いくつか気になる点も。重厚な研究をしているのですが、きちんと説明をしたいということで、プレゼンの原稿を読んでいるところもありました。せっかくですから、ぜひ、原稿を覚えるくらい練習をして、その場での応対をすることをと思います。また、これは多くの高校でそうですが、表と図のプレゼンには大きな違いがあります。表の場合には、表の上に、表1. *****というような説明を入れるということ。それに対して、図の場合には、図の下に、図1. *****という説明を入れることが約束事です。ぜひ、覚えて、次のプレゼンに活かしてください。
会議の最後には、1hr程度の高校生と運営指導委員との討論・質疑の時間があり、多くの質問があったことは、よいことだったと。
今回の表彰を励みにして、また、継続できるように、さらなる発展したものを、来年の夏の会議でみれることを楽しみにしています。運営でお世話になった、幹事校・錦江湾高校・讃岐先生をはじめとする多くの方々にお礼申し上げます。ありがとうございました。
わたなべしるす
PS. 来春には、仙台で植物生理学会の高校生発表会もあります。今回のプレゼンの中から、多くの発表が参加頂けることを楽しみにしております。

注目すべき点は、数多くありました。まず、夏のプレゼンから研究がずいぶん進んでいたこと。さらに、多くの高校で、現物のプレゼンがあったこと。つまり、ダイコン、そのものがあったことです。実際に食したいと思えるような質の高いものを提示していたのは、やはり連携校である、農業高校の生徒さん。さすがだと思いました。普通高校の生徒さんでも立派に育てている高校もあり、最後はダイコンをどこまで観察し、愛情を注いでいるかという点なのかもしれません。また、これまでいろいろなところで話をしてきた、繰り返し実験、統計処理の重要性を理解して、プレゼンテーションができている高校もありました。ぜひ、他の高校でも、お願いします。それから、日々の活動がわかるように、コンソーシアムのHPが用意されているのですが、そこにuploadしたり、それに対してコメントしたり。こうした交流が、将来の研究で大いに役立つことだろうと。
 もちろん、いくつか気になる点も。重厚な研究をしているのですが、きちんと説明をしたいということで、プレゼンの原稿を読んでいるところもありました。せっかくですから、ぜひ、原稿を覚えるくらい練習をして、その場での応対をすることをと思います。また、これは多くの高校でそうですが、表と図のプレゼンには大きな違いがあります。表の場合には、表の上に、表1. *****というような説明を入れるということ。それに対して、図の場合には、図の下に、図1. *****という説明を入れることが約束事です。ぜひ、覚えて、次のプレゼンに活かしてください。
もちろん、いくつか気になる点も。重厚な研究をしているのですが、きちんと説明をしたいということで、プレゼンの原稿を読んでいるところもありました。せっかくですから、ぜひ、原稿を覚えるくらい練習をして、その場での応対をすることをと思います。また、これは多くの高校でそうですが、表と図のプレゼンには大きな違いがあります。表の場合には、表の上に、表1. *****というような説明を入れるということ。それに対して、図の場合には、図の下に、図1. *****という説明を入れることが約束事です。ぜひ、覚えて、次のプレゼンに活かしてください。会議の最後には、1hr程度の高校生と運営指導委員との討論・質疑の時間があり、多くの質問があったことは、よいことだったと。
今回の表彰を励みにして、また、継続できるように、さらなる発展したものを、来年の夏の会議でみれることを楽しみにしています。運営でお世話になった、幹事校・錦江湾高校・讃岐先生をはじめとする多くの方々にお礼申し上げます。ありがとうございました。
わたなべしるす
PS. 来春には、仙台で植物生理学会の高校生発表会もあります。今回のプレゼンの中から、多くの発表が参加頂けることを楽しみにしております。