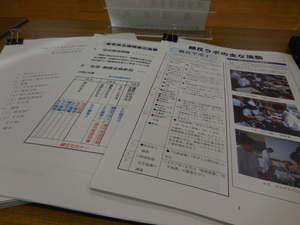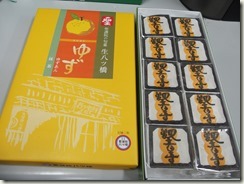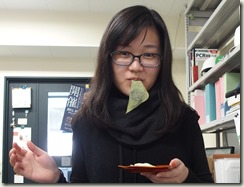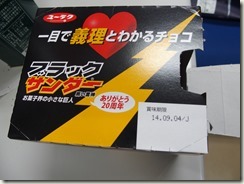降っては溶け、溶けては降りを繰り返し、、、
道路沿いの雪は一向になくなりませんね。
技術補佐員の伊藤です。
さて、毎日通勤している片平キャンパスですが、ほとんどの時間を研究室で過ごしていて、
自分の職場を除いてはキャンパス内の何処に何があるか全く把握していません。
しかし最近外に出る機会があって、その最中におもしろい物を発見しました!
それは歴史的な建物の側に立つ一本の木でした。

ツバメやカラスの巣は見た事があるけれど、木に綺麗な穴があけてあるのを見るのは初めて。
コツコツと叩く音に気づいて近寄った瞬間、黒い陰が飛び去り、、、
はじめて穴の存在に気がつきました。

Googleしてみたところ、キツツキ科キツツキ目のコゲラではないかと。
バードウォッチングには全く興味がないけれど、ちょっと得した気分。
今度は穴だけでなく、住人も激写してやる!と心に誓うのでした。
そして色々と調べているうちに「きつつき」が「啄木鳥」と変換される事に気づきました。
啄木って、、、石川啄木?と思ったけれど、字の通り「木を啄む(ついばむ)鳥」
という意味らしいです。
でも、きつつきが石川啄木と全く無関係という訳でもないようです。
啄木がこのペンネームを使い始めた頃のエッセイに
「窓前の幽林坎々として四季啄木鳥の樹杪を敲く音を絶たず閑静高古の響、真に親しむべし...」
という一節があり、体を壊して自宅療養中だった啄木は、
きつつきが木を叩く音をとても気に入っていたみたいです。
でも、本当はもっとふか~い意味があって、、、
彼が生きた時代の「自由にものを言えない閉塞感が漂う世の中」
と「自然破壊を進める人々」に憤りを感じ、歌を歌う事で
世の中に警鐘を鳴らす存在でありたいという願いが込められているのだそうです。
自分をきつつきになぞらえて、カンカンと(木を)叩く音は
自分が発する『警鐘』だと考えていたのです。
あ~、なんて深い。
学生の頃、物悲しい詩をただただ暗記させられるだけだった
嫌な記憶が一気に吹き飛ぶ感じです。
見回せば深い話がたくさん転がっていそうな片平キャンパス。
暇を見つけて、もっと散策してみようという気持ちになりました。
いとう