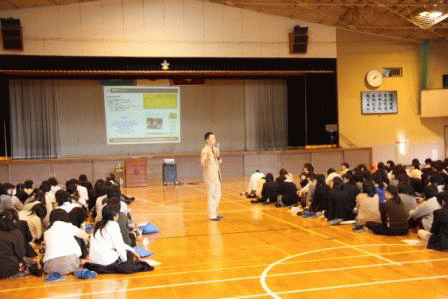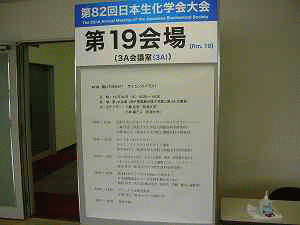
第82回 日本生化学会大会 フォーラム「磨いて活かせ! サイエンスイラスト」に招待講演を依頼され、「ポンチ絵をかえれば、あなたの教育・研究・研究費が変わる!---サイエンスデザイナーによる劇的ビフォー・アフター!---」というタイトルでお話をしてきました。
オーガナイザーをされた筑波大・三輪先生、小林先生は、筑波大ならではという、生命科学系と芸術系の融合をされ、様々な生命現象を芸術系の学生さんたちに、講義の一環として、「サイエンスイラスト」を書くことをされておられました。とてもおもしろい試みであると共に、新しい雇用が創出されるのではと思いました。ポンチ絵を気軽に描いてくれる人材の。とても楽しみです。
渡辺の方は、岩手大にいた当時から、ポンチ絵、ポスターなどを作製してもらってきた現状をお話しして、それがどれだけインパクトがあるか、体験を交えてお話ししました。かなり大きな会場でしたが、立ち見が出るほどの聴衆がいたことは、うれしい限りでした。他の皆様方のこれからの研究・教育活動にお役に立てればと思います。
筑波大の田中先生は、ポンチ絵を作製する芸術の立場でお話し頂き、共立出版の飯田先生は、日本語での執筆の際の注意点、京都大の平賀先生は、ご自身で最初から最後まで一冊の本を作られたことなど、多くの経験、鍵となるポイントを伺えたことは、これからのポンチ絵作りなどに役に立ちそうです。
この経験を生かして、論文を少しでもよいJournalに投稿し、科研費などを獲得できればと思います。最後になりましたが、このような場をいただきました、筑波大・三輪先生、小林先生に感謝申し上げます。ありがとうございました。
わたなべしるす。
PS. 新神戸の駅で柵があるホームを見つけました。東北新幹線では、結構majorですが、こんなところにもと思いつつ。