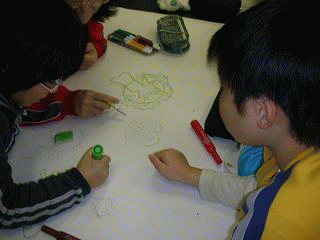 東北大と仙台市教育委員会の連携による出前講義が発展し、今年は川平小学校の科学工作クラブの研究指導を2回行いました。1回目は、10/21のキャベツとブロッコリーが同じ種(Brassica oleracea)である、という講義で、
東北大と仙台市教育委員会の連携による出前講義が発展し、今年は川平小学校の科学工作クラブの研究指導を2回行いました。1回目は、10/21のキャベツとブロッコリーが同じ種(Brassica oleracea)である、という講義で、
https://www.ige.tohoku.ac.jp/prg/watanabe/diary/2009/10/21152147.php
その2回目の指導が今日でした。今日は、栽培・観察を続けている植物を見ていることも重要ですが、それに加えて、実際に雑種を作るとどんなものができるのか、ということについて、8つの班に分かれて、新しい雑種植物の想像図を書いて、みんなで議論をしてもらいました。
最初に、キャベツとブロッコリーの横断面がどうなっているのか、普段どれくらい観察しているかを書いてもらいました。きちんと絵を描くことができた人は、真ん中に茎があって、そこから葉っぱが出ているのをうまく書いていました。毎日の食生活での観察の賜物だと思いました。そのあと、班ごとに雑種植物の想像図を書いてもらいましたが、7つの班は、キャベツの中にブロッコリーができる、あるいは、キャベツの真ん中からブロッコリーが葉っぱをかき分けて出てくるというものを書いてくれました。ブロッコリーの茎とキャベツの茎が同じ起源であり、お花は、茎の先端に咲くと言うことをよく理解しているのだなと、感動しました。これも指導をされている先生方があればこそと思った次第です。
春には、ぜひ、新しい雑種を作るべく、交配をできればと思いますし、継続的に連携ができればと思います。最後になりましたが、渡辺がキャベツとブロッコリーを持っていくことを忘れていたのですが、きちんとそれをカバー頂いた、加藤先生にはお礼申し上げます。ありがとうございました。
わたなべしるす
PS. 今年の仙台市内の小学校との連携は、これで最後ですが、12/25に仙台市教育委員会主催の発表会があり、七北田小学校とのこれまでの取組について、発表します。そのときに、これまで講義でお世話になった先生方にお会いできるのを楽しみにしております。




 SSH九州地区発信の「ダイコン多様性研究コンソーシアム」(機関校:鹿児島県立錦江湾高校)の指導委員を務めることから、参加校が一堂に会し、研究プロジェクトの発表、評価、指導などを8月に続いて行いました。
SSH九州地区発信の「ダイコン多様性研究コンソーシアム」(機関校:鹿児島県立錦江湾高校)の指導委員を務めることから、参加校が一堂に会し、研究プロジェクトの発表、評価、指導などを8月に続いて行いました。
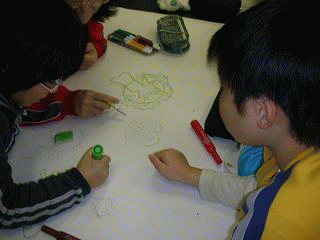 東北大と仙台市教育委員会の連携による出前講義が発展し、今年は川平小学校の科学工作クラブの研究指導を2回行いました。1回目は、10/21のキャベツとブロッコリーが同じ種(Brassica oleracea)である、という講義で、
東北大と仙台市教育委員会の連携による出前講義が発展し、今年は川平小学校の科学工作クラブの研究指導を2回行いました。1回目は、10/21のキャベツとブロッコリーが同じ種(Brassica oleracea)である、という講義で、