 今年も残すところ、あと、1週間程度。まだ、ずいぶんとやり残したことがたくさんあるように思えてしょうがありません。研究、教育、。。。。いろいろなことがあった反省は、大晦日まで残すことにして。。。
今年も残すところ、あと、1週間程度。まだ、ずいぶんとやり残したことがたくさんあるように思えてしょうがありません。研究、教育、。。。。いろいろなことがあった反省は、大晦日まで残すことにして。。。植物・作物を扱っていると、その旬の時期を言うのを「花」を通して、それとなく理解することができます。もちろん、昨今の周年栽培により、本当の「旬」というのがいつなのか分からなくなったようなもののあります。われわれの扱っているアブラナ科植物・作物は、基本、冬から春だと思います。もちろん、1年中、キャベツ、ブロッコリー、ダイコンなどは、食べることができます。東北であれば、今は「リンゴ」なのかもしれないですし、西日本では「ミカン・柑橘」が旬でしょう。ずいぶんと、品種も増えてきました。特に、柑橘系は。
そんな中でも、「イチゴ」は、旬と収穫量が最大というのが半年近くずれている果物かもしれません(講義では、イチゴは、野菜に分類されると聞いたような。。)。イチゴと言えば、クリスマスケーキのパーツになってしまい、今、この時期が生産量は最大とか。しかしながら、子供頃、露地にあったのを食べたのは、4-5月だったような。食文化の変化がこの様なことを起こしているのかもしれないですが、植物・作物を扱っている1人としては、少し違和感を感じ得ません。。。。そういえば、今年もたくさんの方々に、「旬」の頂き物をしました。ありがとうございました。その一部の写真しか掲載できておりませんが、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。
今年の仕事は、今年のうちに。何とかしないと、と思う、今日のこの頃でした。
わたなべしるす



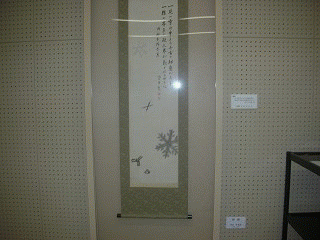 昨日の石川県SSH生徒研究発表会・コメンテーターに引き続き、小松高校でSSHを対象にして、「自家不和合性」の講義を行うとともに、ダイコンコンソーシアム研究指導を行いました。
昨日の石川県SSH生徒研究発表会・コメンテーターに引き続き、小松高校でSSHを対象にして、「自家不和合性」の講義を行うとともに、ダイコンコンソーシアム研究指導を行いました。  ダイコンコンソーシアム研究指導のつながりで、石川県小松高校で講義をしたり、研究指導を行ったのは、10/30でした。その際は、キャリア教育を1, 2年生対象に行ったり、ダイコンなど、生物関係の研究について議論をしたり、今後後の方向性を検討したりと、よい刺激を受けました。
ダイコンコンソーシアム研究指導のつながりで、石川県小松高校で講義をしたり、研究指導を行ったのは、10/30でした。その際は、キャリア教育を1, 2年生対象に行ったり、ダイコンなど、生物関係の研究について議論をしたり、今後後の方向性を検討したりと、よい刺激を受けました。