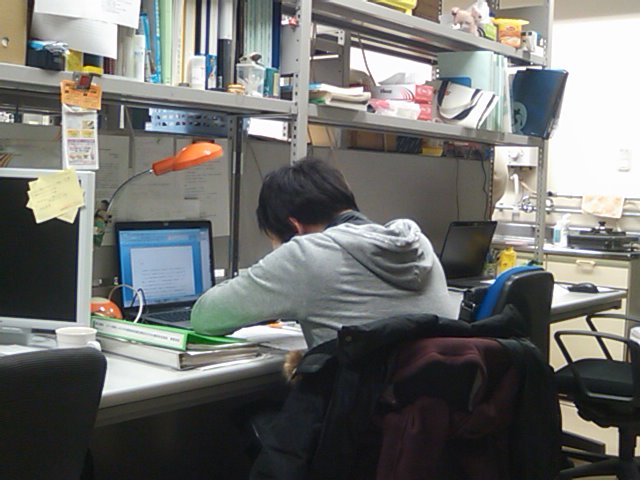学会の方は、扱う材料が、動植物、微生物などDNAがあれば、何でもということもあり、研究材料を対象にしたもの、技術開発、現象に注目したものなど。。。いわゆる次世代シークエンサーが出たこともあり、minor cropでもwhole genome sequenceが可能になったことも、世界観が変わるのかもしれません。
 また、世界各国からの参加はもちろんですが、あちこちで、中国語を聞くことが多く、日本人が外に出なくなって、というのと、linkしているようなことも感じました。また、外国の方は誰にでも話しかけてくることも。。。。食事をしていても、Tableがあいていれば、座ってくるし、話しかけてくるのには困りました。
また、世界各国からの参加はもちろんですが、あちこちで、中国語を聞くことが多く、日本人が外に出なくなって、というのと、linkしているようなことも感じました。また、外国の方は誰にでも話しかけてくることも。。。。食事をしていても、Tableがあいていれば、座ってくるし、話しかけてくるのには困りました。渡辺のセッションは、こちらの時間では、明日の夕方、そちらの時間では、明日の昼頃ですが、そのことは、また折を見て。
わたなべしるす
PS. 同じセッションで、昨年、Natureを共同執筆した、清水さんがその内容などを合わせてお話ししてくれました。