朝、起きてテレビをつけてびっくりしたのは、W杯の途中経過。何が起きたのか。あちこちで議論しているようですが、こちらは、それを見る間もなく。流れというか、勢いというか、一度、傾けたときに、難しいのだなと。。。。と言うことと、やっぱり台風の進路。中心気圧は970ヘクトパスカルまで上がり、最大瞬間風速も45m/sになったのもあって、一時よりは、かなり弱まったものの。。。仙台を通過するのが、金曜日の夕方から夜にかけて。速度は余り変化してないようなので。いずれ、各地で風、雨が尋常でないので。。。今週は気にならない日がなさそうです。。。。
 さて、岩手県立盛岡第三高等学校のSSHも今年度が4年目。5年計画の教育プログラムですので、次の5年に向けて考える時期かと。。。そんなことを委員長の高木先生から。確かに、今年あたりからきちんと考えるのが、重要だと思います。是非、次期プログラムにスムーズにつながるように、サポートできればと思います。4年目と言うことは、1年生から3年生まで受講した生徒さんが大学生に。そんなこともあり、SSHクラス卒業生への聞き取り調査結果が出ていました。SNSのようなもの(LINE)で、SSHクラスがつながっていることから、アンケートを投げたようですが、responseがよい生徒さんは速いが、なかなかないという生徒さんも多いようで。回答そのものはとてもpositiveでよい試みだと思いました。ただ、回収率が余りよくなかったのは、科学者の卵養成講座でも頭を抱えているところ。。。何度も調査をしたり、方法論を変えてアンケートをしたというのも、重要ではないかと。科学者の卵養成講座も修了生で、大学生になった方がを「ひよこ」と呼んで、活動を手伝ってくれていますし、受講生、修了生の両方に刺激的になるのではと思いますので。
さて、岩手県立盛岡第三高等学校のSSHも今年度が4年目。5年計画の教育プログラムですので、次の5年に向けて考える時期かと。。。そんなことを委員長の高木先生から。確かに、今年あたりからきちんと考えるのが、重要だと思います。是非、次期プログラムにスムーズにつながるように、サポートできればと思います。4年目と言うことは、1年生から3年生まで受講した生徒さんが大学生に。そんなこともあり、SSHクラス卒業生への聞き取り調査結果が出ていました。SNSのようなもの(LINE)で、SSHクラスがつながっていることから、アンケートを投げたようですが、responseがよい生徒さんは速いが、なかなかないという生徒さんも多いようで。回答そのものはとてもpositiveでよい試みだと思いました。ただ、回収率が余りよくなかったのは、科学者の卵養成講座でも頭を抱えているところ。。。何度も調査をしたり、方法論を変えてアンケートをしたというのも、重要ではないかと。科学者の卵養成講座も修了生で、大学生になった方がを「ひよこ」と呼んで、活動を手伝ってくれていますし、受講生、修了生の両方に刺激的になるのではと思いますので。
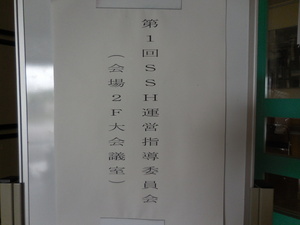 評価の問題。生徒自身が自己評価はこれまでも実施していて。。。では、教員側から生徒を評価したときに、教員間の評価の誤差というか、差異というか。その当たりは大学の同じ教科を担当する教員間でも問題のはずですが。。。そうしたことが議論になったことは。。。と言うか、大学も考えないといけないのだと。また、教員サイドからの評価としては、例えば、それぞれの評価項目の目標値を決めて、それに対して、どのレベルまで達成しているかなど、評価方法を工夫することが大事なのだろうと。。。さらに、大きな問題として、高大連携・接続の問題。高大連携、高大接続というのは、そもそもどの様な定義なのか。これでずいぶんとdeepな議論でした。東北大でも前期、後期の一部の講義を高校に公開し、渡辺が後期に行う「展開ゼミ」でも、宮城第一高等学校の2名の生徒さんが受講してくれます。東北大に入学できれば、単位認定をすると言う仕組みで、他の大学にもある訳です。ただ、それだけでは足りないようで、とあるHP上では、「高大連携としては、キャリア教育などの講義を通じて高校から大学へスムーズにつながるように」と言うことのようです。一方、「高大接続は、高校と大学の教員が共同して講義を行う」と言う定義のようです(会議中のメモが間違ってなければ。。。)。これが公式なものか、そうでないのか。。。明確にSSHを統括されている側で回答が示されないと、どうにも動きにくいところがあると思えてきました。その当たりに関する妙案と言うより、その立場から回答(解答)が示されないものかと。。。
評価の問題。生徒自身が自己評価はこれまでも実施していて。。。では、教員側から生徒を評価したときに、教員間の評価の誤差というか、差異というか。その当たりは大学の同じ教科を担当する教員間でも問題のはずですが。。。そうしたことが議論になったことは。。。と言うか、大学も考えないといけないのだと。また、教員サイドからの評価としては、例えば、それぞれの評価項目の目標値を決めて、それに対して、どのレベルまで達成しているかなど、評価方法を工夫することが大事なのだろうと。。。さらに、大きな問題として、高大連携・接続の問題。高大連携、高大接続というのは、そもそもどの様な定義なのか。これでずいぶんとdeepな議論でした。東北大でも前期、後期の一部の講義を高校に公開し、渡辺が後期に行う「展開ゼミ」でも、宮城第一高等学校の2名の生徒さんが受講してくれます。東北大に入学できれば、単位認定をすると言う仕組みで、他の大学にもある訳です。ただ、それだけでは足りないようで、とあるHP上では、「高大連携としては、キャリア教育などの講義を通じて高校から大学へスムーズにつながるように」と言うことのようです。一方、「高大接続は、高校と大学の教員が共同して講義を行う」と言う定義のようです(会議中のメモが間違ってなければ。。。)。これが公式なものか、そうでないのか。。。明確にSSHを統括されている側で回答が示されないと、どうにも動きにくいところがあると思えてきました。その当たりに関する妙案と言うより、その立場から回答(解答)が示されないものかと。。。
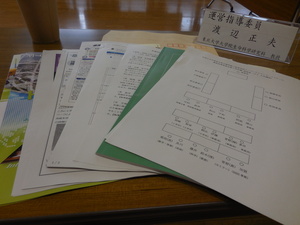 最後の議論は、今年度の活動状況と今後の方針。予算が厳しい折と言うことがありましたので、おもしろい試みとして、SSH活動を使われている学校もあると言うことを。どこかと言うことについては、。。また、何かの折りに。なるほど思えるようなと言うか、考えてみればと言うような。。。最後になりましたが、今回の運営指導委員会でお世話になりました県教委・中村指導主事、岩井高校教育課長、和山校長先生をはじめとするSSH関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。今年度も秋に出前講義でうかがえればと思いますし、さらなる発展を祈念しております。今後ともよろしくお願いいたします。
最後の議論は、今年度の活動状況と今後の方針。予算が厳しい折と言うことがありましたので、おもしろい試みとして、SSH活動を使われている学校もあると言うことを。どこかと言うことについては、。。また、何かの折りに。なるほど思えるようなと言うか、考えてみればと言うような。。。最後になりましたが、今回の運営指導委員会でお世話になりました県教委・中村指導主事、岩井高校教育課長、和山校長先生をはじめとするSSH関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。今年度も秋に出前講義でうかがえればと思いますし、さらなる発展を祈念しております。今後ともよろしくお願いいたします。
わたなべしるす
PS. 岩手大での打合せの途中で、科学者の卵養成講座の修了生である「ひよこ」の方にお目にかかり。。。。。農学部でがんばっておられるのを聞いて、。。頼もしい限りです。打合せの食事会をご一緒したりして、相変わらず、activeに活動されているのを伺い、お願いを忘れたのですが、今年度からの「飛翔型科学者の卵養成講座」もサポート頂ければと。。。また、秋にも出前講義で盛岡に来ることになるかと。。。その時に、また、お目にかかることができれば。。。さらなる進化を期待しつつ。。。。

 さて、岩手県立盛岡第三高等学校のSSHも今年度が4年目。5年計画の教育プログラムですので、次の5年に向けて考える時期かと。。。そんなことを委員長の高木先生から。確かに、今年あたりからきちんと考えるのが、重要だと思います。是非、次期プログラムにスムーズにつながるように、サポートできればと思います。4年目と言うことは、1年生から3年生まで受講した生徒さんが大学生に。そんなこともあり、SSHクラス卒業生への聞き取り調査結果が出ていました。SNSのようなもの(LINE)で、SSHクラスがつながっていることから、アンケートを投げたようですが、responseがよい生徒さんは速いが、なかなかないという生徒さんも多いようで。回答そのものはとてもpositiveでよい試みだと思いました。ただ、回収率が余りよくなかったのは、科学者の卵養成講座でも頭を抱えているところ。。。何度も調査をしたり、方法論を変えてアンケートをしたというのも、重要ではないかと。科学者の卵養成講座も修了生で、大学生になった方がを「ひよこ」と呼んで、活動を手伝ってくれていますし、受講生、修了生の両方に刺激的になるのではと思いますので。
さて、岩手県立盛岡第三高等学校のSSHも今年度が4年目。5年計画の教育プログラムですので、次の5年に向けて考える時期かと。。。そんなことを委員長の高木先生から。確かに、今年あたりからきちんと考えるのが、重要だと思います。是非、次期プログラムにスムーズにつながるように、サポートできればと思います。4年目と言うことは、1年生から3年生まで受講した生徒さんが大学生に。そんなこともあり、SSHクラス卒業生への聞き取り調査結果が出ていました。SNSのようなもの(LINE)で、SSHクラスがつながっていることから、アンケートを投げたようですが、responseがよい生徒さんは速いが、なかなかないという生徒さんも多いようで。回答そのものはとてもpositiveでよい試みだと思いました。ただ、回収率が余りよくなかったのは、科学者の卵養成講座でも頭を抱えているところ。。。何度も調査をしたり、方法論を変えてアンケートをしたというのも、重要ではないかと。科学者の卵養成講座も修了生で、大学生になった方がを「ひよこ」と呼んで、活動を手伝ってくれていますし、受講生、修了生の両方に刺激的になるのではと思いますので。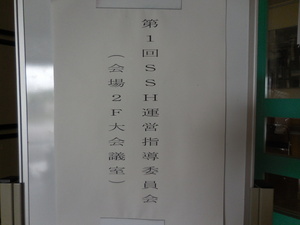 評価の問題。生徒自身が自己評価はこれまでも実施していて。。。では、教員側から生徒を評価したときに、教員間の評価の誤差というか、差異というか。その当たりは大学の同じ教科を担当する教員間でも問題のはずですが。。。そうしたことが議論になったことは。。。と言うか、大学も考えないといけないのだと。また、教員サイドからの評価としては、例えば、それぞれの評価項目の目標値を決めて、それに対して、どのレベルまで達成しているかなど、評価方法を工夫することが大事なのだろうと。。。さらに、大きな問題として、高大連携・接続の問題。高大連携、高大接続というのは、そもそもどの様な定義なのか。これでずいぶんとdeepな議論でした。東北大でも前期、後期の一部の講義を高校に公開し、渡辺が後期に行う「展開ゼミ」でも、宮城第一高等学校の2名の生徒さんが受講してくれます。東北大に入学できれば、単位認定をすると言う仕組みで、他の大学にもある訳です。ただ、それだけでは足りないようで、とあるHP上では、「高大連携としては、キャリア教育などの講義を通じて高校から大学へスムーズにつながるように」と言うことのようです。一方、「高大接続は、高校と大学の教員が共同して講義を行う」と言う定義のようです(会議中のメモが間違ってなければ。。。)。これが公式なものか、そうでないのか。。。明確にSSHを統括されている側で回答が示されないと、どうにも動きにくいところがあると思えてきました。その当たりに関する妙案と言うより、その立場から回答(解答)が示されないものかと。。。
評価の問題。生徒自身が自己評価はこれまでも実施していて。。。では、教員側から生徒を評価したときに、教員間の評価の誤差というか、差異というか。その当たりは大学の同じ教科を担当する教員間でも問題のはずですが。。。そうしたことが議論になったことは。。。と言うか、大学も考えないといけないのだと。また、教員サイドからの評価としては、例えば、それぞれの評価項目の目標値を決めて、それに対して、どのレベルまで達成しているかなど、評価方法を工夫することが大事なのだろうと。。。さらに、大きな問題として、高大連携・接続の問題。高大連携、高大接続というのは、そもそもどの様な定義なのか。これでずいぶんとdeepな議論でした。東北大でも前期、後期の一部の講義を高校に公開し、渡辺が後期に行う「展開ゼミ」でも、宮城第一高等学校の2名の生徒さんが受講してくれます。東北大に入学できれば、単位認定をすると言う仕組みで、他の大学にもある訳です。ただ、それだけでは足りないようで、とあるHP上では、「高大連携としては、キャリア教育などの講義を通じて高校から大学へスムーズにつながるように」と言うことのようです。一方、「高大接続は、高校と大学の教員が共同して講義を行う」と言う定義のようです(会議中のメモが間違ってなければ。。。)。これが公式なものか、そうでないのか。。。明確にSSHを統括されている側で回答が示されないと、どうにも動きにくいところがあると思えてきました。その当たりに関する妙案と言うより、その立場から回答(解答)が示されないものかと。。。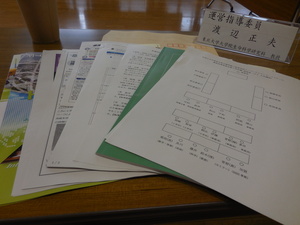 最後の議論は、今年度の活動状況と今後の方針。予算が厳しい折と言うことがありましたので、おもしろい試みとして、SSH活動を使われている学校もあると言うことを。どこかと言うことについては、。。また、何かの折りに。なるほど思えるようなと言うか、考えてみればと言うような。。。最後になりましたが、今回の運営指導委員会でお世話になりました県教委・中村指導主事、岩井高校教育課長、和山校長先生をはじめとするSSH関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。今年度も秋に出前講義でうかがえればと思いますし、さらなる発展を祈念しております。今後ともよろしくお願いいたします。
最後の議論は、今年度の活動状況と今後の方針。予算が厳しい折と言うことがありましたので、おもしろい試みとして、SSH活動を使われている学校もあると言うことを。どこかと言うことについては、。。また、何かの折りに。なるほど思えるようなと言うか、考えてみればと言うような。。。最後になりましたが、今回の運営指導委員会でお世話になりました県教委・中村指導主事、岩井高校教育課長、和山校長先生をはじめとするSSH関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。今年度も秋に出前講義でうかがえればと思いますし、さらなる発展を祈念しております。今後ともよろしくお願いいたします。わたなべしるす
PS. 岩手大での打合せの途中で、科学者の卵養成講座の修了生である「ひよこ」の方にお目にかかり。。。。。農学部でがんばっておられるのを聞いて、。。頼もしい限りです。打合せの食事会をご一緒したりして、相変わらず、activeに活動されているのを伺い、お願いを忘れたのですが、今年度からの「飛翔型科学者の卵養成講座」もサポート頂ければと。。。また、秋にも出前講義で盛岡に来ることになるかと。。。その時に、また、お目にかかることができれば。。。さらなる進化を期待しつつ。。。。















