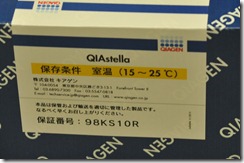初めて献血をしたのは、学部の1, 2年の時。水産の友達に誘われて、学内にいた献血車で。幼稚園の頃までは、月一で熱を出しては、小児科にいって、注射をした。そのおかげか、今でも苦手である。不思議と献血は、何故か続いて、100回を超えている。ただ、検査と採血の時に針を刺すときには、歯を食いしばって、気合で我慢する。針を刺す前に、刺すことを言ってもらって、刺すところを見ることもできない。聞くところによると、リラックスしている方がいたくないらしいが。。。いつも、採血をしてくれる看護師さんに不思議がられ、大丈夫かと言われるが、続けている。100回というのも、1回を除いて、200ml献血である。申し訳ないと思うが。。助手の頃だろうか、400ml献血はどうですかと言われて、気が向かなかったのだが、はいと。。ところが、300mlを超えた頃から、変な感じで、400mlの採血が終わったら、かなり。。そのまま、ソファーに横なって、。。血圧も下がり。1hrほど、横になっていた。針を刺すことは気合と根性でがんばれても、この400mlはこたえた。。。進められたとはいえ、決断は自分なので、自己責任と言えば、そうなのかもしれない。身長・体重的には十分なのであろうが、それ以降は、この経験から、どんなにすすめられたり、お願いされても、無理と。。。あと、成分献血も。科学力の推移を集めて、血液を分けるのであろうが、一度外に出たものが戻る。。。。。これも無理であった。あと、時間がかかることも。時間だけは、お金で買えないと言うことも要因なのかもしれない。
 こんなに血を見ることが苦手なこともあって、生き物の中でも、植物・作物を扱っている。もちろん、植物の様々な部分を集めて、解析する。植物の側からすれば、もちろん、我慢しているとかでなくて、いたいのかもしれないが、現時点の科学力ではその声が聞こえないことも幸いしている。ところが、卒論実験で行ったのは、マウスを利用した抗体作成と特異性の調査。最初はあり得ないと思った。。。1 week考えても。。。でも、教授に説得され。。というか、最後は自己責任なのだろう。やることにした。マウスに免疫するというが、腹腔内に抗原を注射する。。。注射が嫌いな自分が。。。どう考えてもあり得ない(マウスをいじめている気持ちになったのかもしれない。。。。)。まず、きちんとマウスを押さえることができず、何度も持ち直し。。。注射をする手元も震える。。。そのたびに、実験を教えてくれていた先輩が、「びしっ」と、指導。実験の都合上、解剖したことも。。。。(頭の中では、すべてあり得ないと思っていても、これが卒論だと思って、。。気合で。。)。クリーンベンチの操作もあり、ピペット、ピンセット、解剖道具の手元の先がクリーンベンチから少しでも出ると、先と同様に、「びしっ」と。こうしたことを言われ続けて、1年間で、何とか、マウスの扱い、クリーンベンチの操作もできるようになったというか。すべての基本操作の基礎ができたのかもしれない。ただ、やっぱり、解剖したマウスをそのまま、アルミホイルに包み、凍結して、ということでよいと言われたが、たえられず、農学部の隅に穴を掘って埋めて、棒をたてて、お線香を供えて、手を合わせた。ここまでやって、何か妙に落ち着いたような記憶がある。心の問題かもしれないが。。。
こんなに血を見ることが苦手なこともあって、生き物の中でも、植物・作物を扱っている。もちろん、植物の様々な部分を集めて、解析する。植物の側からすれば、もちろん、我慢しているとかでなくて、いたいのかもしれないが、現時点の科学力ではその声が聞こえないことも幸いしている。ところが、卒論実験で行ったのは、マウスを利用した抗体作成と特異性の調査。最初はあり得ないと思った。。。1 week考えても。。。でも、教授に説得され。。というか、最後は自己責任なのだろう。やることにした。マウスに免疫するというが、腹腔内に抗原を注射する。。。注射が嫌いな自分が。。。どう考えてもあり得ない(マウスをいじめている気持ちになったのかもしれない。。。。)。まず、きちんとマウスを押さえることができず、何度も持ち直し。。。注射をする手元も震える。。。そのたびに、実験を教えてくれていた先輩が、「びしっ」と、指導。実験の都合上、解剖したことも。。。。(頭の中では、すべてあり得ないと思っていても、これが卒論だと思って、。。気合で。。)。クリーンベンチの操作もあり、ピペット、ピンセット、解剖道具の手元の先がクリーンベンチから少しでも出ると、先と同様に、「びしっ」と。こうしたことを言われ続けて、1年間で、何とか、マウスの扱い、クリーンベンチの操作もできるようになったというか。すべての基本操作の基礎ができたのかもしれない。ただ、やっぱり、解剖したマウスをそのまま、アルミホイルに包み、凍結して、ということでよいと言われたが、たえられず、農学部の隅に穴を掘って埋めて、棒をたてて、お線香を供えて、手を合わせた。ここまでやって、何か妙に落ち着いたような記憶がある。心の問題かもしれないが。。。
 こうして覚えた技術も、大学院生の頃までは使ったものの、それ以降は使わずじまい。。ただ、指導してくれた先輩からの「びしっ」とした、厳しい指導があったからこそ、次につながっている。1日に何時間もクリーンベンチに座ることができるようになったことから、他の実験も同じように、長時間でも耐えることができるようになったと思っている。日本人が得意な手先の器用さと言うことも、できるまでやるという繰り返しと、先輩方からの厳しい指導があってこそ、こうして継承してきたものではないだろうか。10回でできなければ、さらに。。。というような、「気合いと根性」と「努力」が、mm単位、いやそれより小さなところでの完璧な仕事を可能にしたような気がしている。それらをもう一度思い出し、サイエンスに精進したいと思った、土曜日の献血であった。。。
こうして覚えた技術も、大学院生の頃までは使ったものの、それ以降は使わずじまい。。ただ、指導してくれた先輩からの「びしっ」とした、厳しい指導があったからこそ、次につながっている。1日に何時間もクリーンベンチに座ることができるようになったことから、他の実験も同じように、長時間でも耐えることができるようになったと思っている。日本人が得意な手先の器用さと言うことも、できるまでやるという繰り返しと、先輩方からの厳しい指導があってこそ、こうして継承してきたものではないだろうか。10回でできなければ、さらに。。。というような、「気合いと根性」と「努力」が、mm単位、いやそれより小さなところでの完璧な仕事を可能にしたような気がしている。それらをもう一度思い出し、サイエンスに精進したいと思った、土曜日の献血であった。。。
わたなべしるす
 こんなに血を見ることが苦手なこともあって、生き物の中でも、植物・作物を扱っている。もちろん、植物の様々な部分を集めて、解析する。植物の側からすれば、もちろん、我慢しているとかでなくて、いたいのかもしれないが、現時点の科学力ではその声が聞こえないことも幸いしている。ところが、卒論実験で行ったのは、マウスを利用した抗体作成と特異性の調査。最初はあり得ないと思った。。。1 week考えても。。。でも、教授に説得され。。というか、最後は自己責任なのだろう。やることにした。マウスに免疫するというが、腹腔内に抗原を注射する。。。注射が嫌いな自分が。。。どう考えてもあり得ない(マウスをいじめている気持ちになったのかもしれない。。。。)。まず、きちんとマウスを押さえることができず、何度も持ち直し。。。注射をする手元も震える。。。そのたびに、実験を教えてくれていた先輩が、「びしっ」と、指導。実験の都合上、解剖したことも。。。。(頭の中では、すべてあり得ないと思っていても、これが卒論だと思って、。。気合で。。)。クリーンベンチの操作もあり、ピペット、ピンセット、解剖道具の手元の先がクリーンベンチから少しでも出ると、先と同様に、「びしっ」と。こうしたことを言われ続けて、1年間で、何とか、マウスの扱い、クリーンベンチの操作もできるようになったというか。すべての基本操作の基礎ができたのかもしれない。ただ、やっぱり、解剖したマウスをそのまま、アルミホイルに包み、凍結して、ということでよいと言われたが、たえられず、農学部の隅に穴を掘って埋めて、棒をたてて、お線香を供えて、手を合わせた。ここまでやって、何か妙に落ち着いたような記憶がある。心の問題かもしれないが。。。
こんなに血を見ることが苦手なこともあって、生き物の中でも、植物・作物を扱っている。もちろん、植物の様々な部分を集めて、解析する。植物の側からすれば、もちろん、我慢しているとかでなくて、いたいのかもしれないが、現時点の科学力ではその声が聞こえないことも幸いしている。ところが、卒論実験で行ったのは、マウスを利用した抗体作成と特異性の調査。最初はあり得ないと思った。。。1 week考えても。。。でも、教授に説得され。。というか、最後は自己責任なのだろう。やることにした。マウスに免疫するというが、腹腔内に抗原を注射する。。。注射が嫌いな自分が。。。どう考えてもあり得ない(マウスをいじめている気持ちになったのかもしれない。。。。)。まず、きちんとマウスを押さえることができず、何度も持ち直し。。。注射をする手元も震える。。。そのたびに、実験を教えてくれていた先輩が、「びしっ」と、指導。実験の都合上、解剖したことも。。。。(頭の中では、すべてあり得ないと思っていても、これが卒論だと思って、。。気合で。。)。クリーンベンチの操作もあり、ピペット、ピンセット、解剖道具の手元の先がクリーンベンチから少しでも出ると、先と同様に、「びしっ」と。こうしたことを言われ続けて、1年間で、何とか、マウスの扱い、クリーンベンチの操作もできるようになったというか。すべての基本操作の基礎ができたのかもしれない。ただ、やっぱり、解剖したマウスをそのまま、アルミホイルに包み、凍結して、ということでよいと言われたが、たえられず、農学部の隅に穴を掘って埋めて、棒をたてて、お線香を供えて、手を合わせた。ここまでやって、何か妙に落ち着いたような記憶がある。心の問題かもしれないが。。。 こうして覚えた技術も、大学院生の頃までは使ったものの、それ以降は使わずじまい。。ただ、指導してくれた先輩からの「びしっ」とした、厳しい指導があったからこそ、次につながっている。1日に何時間もクリーンベンチに座ることができるようになったことから、他の実験も同じように、長時間でも耐えることができるようになったと思っている。日本人が得意な手先の器用さと言うことも、できるまでやるという繰り返しと、先輩方からの厳しい指導があってこそ、こうして継承してきたものではないだろうか。10回でできなければ、さらに。。。というような、「気合いと根性」と「努力」が、mm単位、いやそれより小さなところでの完璧な仕事を可能にしたような気がしている。それらをもう一度思い出し、サイエンスに精進したいと思った、土曜日の献血であった。。。
こうして覚えた技術も、大学院生の頃までは使ったものの、それ以降は使わずじまい。。ただ、指導してくれた先輩からの「びしっ」とした、厳しい指導があったからこそ、次につながっている。1日に何時間もクリーンベンチに座ることができるようになったことから、他の実験も同じように、長時間でも耐えることができるようになったと思っている。日本人が得意な手先の器用さと言うことも、できるまでやるという繰り返しと、先輩方からの厳しい指導があってこそ、こうして継承してきたものではないだろうか。10回でできなければ、さらに。。。というような、「気合いと根性」と「努力」が、mm単位、いやそれより小さなところでの完璧な仕事を可能にしたような気がしている。それらをもう一度思い出し、サイエンスに精進したいと思った、土曜日の献血であった。。。わたなべしるす