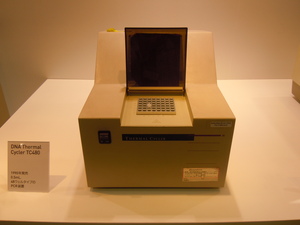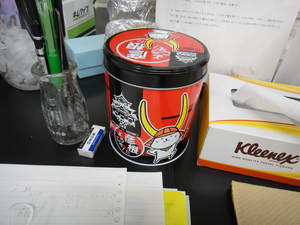あと10日ほどで、年が変わり、2012年も終わります。2011年3月11日の震災から、今年は復興元年と言われ、何とか全員でがんばろうという1年になったのではと思っています。そこで、今年1年をいろいろな角度から振り返ってみたいと思います。最初は、研究とか、教育とかと言うことかいくことが筋なのかもしれないですが、このHPから発信が一番多かった、アウトリーチ活動、いわゆる、出前講義等について、ということにしたいと思います。
アウトリーチ活動については、labのHPにもまとめてありますし、それぞれのプロジェクト(新学術領域研究、若手研究(S))のHPにも記してあります。細かなことは、そちらをご覧下さい。もちろん、研究室ダイアリーのところをカテゴリー別にしておりますので、出前講義、研究室訪問をclick頂ければ、新しいものから見るようになりました。これも4月からのHPの大幅更新で、見やすくなったのではと思います。
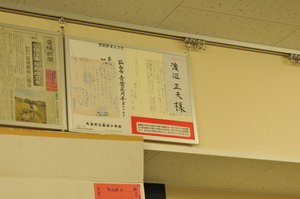 では、その中身ですが、14府県(青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島、栃木、埼玉、石川、大阪、兵庫、香川、愛媛、鹿児島)の小中高と交流できました。ダイコンコンソーシアムに参加頂いている高校も入れれば、3県(岐阜、和歌山、佐賀)、追加されます。それなりのところにうかがえたのではと思います。何より、今年、大阪、兵庫とうかがえたのも、他のSSH校での講義、交流会などでのつながりのおかげです。改めて、ヒトのつながりに感謝したいと思います。もちろん、それぞれの学校に十分なことができたところもあったかもしれないですが、体調を崩して十分な対応ができなかったこともありました。ぜひ、2013年はそうしたことのないように自己管理をしたいと思います。また、時間の調整がつかず、うかがえなかったところも多くありました。そうしたところを来年には改善して、さらには、内容も充実させ、来年もこうした活動をできればと思います。
では、その中身ですが、14府県(青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島、栃木、埼玉、石川、大阪、兵庫、香川、愛媛、鹿児島)の小中高と交流できました。ダイコンコンソーシアムに参加頂いている高校も入れれば、3県(岐阜、和歌山、佐賀)、追加されます。それなりのところにうかがえたのではと思います。何より、今年、大阪、兵庫とうかがえたのも、他のSSH校での講義、交流会などでのつながりのおかげです。改めて、ヒトのつながりに感謝したいと思います。もちろん、それぞれの学校に十分なことができたところもあったかもしれないですが、体調を崩して十分な対応ができなかったこともありました。ぜひ、2013年はそうしたことのないように自己管理をしたいと思います。また、時間の調整がつかず、うかがえなかったところも多くありました。そうしたところを来年には改善して、さらには、内容も充実させ、来年もこうした活動をできればと思います。
訪問したり、見学してもらうだけでなく、その時に質問できなかったことをmailで頂いたり、人生相談のようなものだったり。そうしたものへのmailでの回答も数多くありました。また、そうした方々から、出前講義の記事をHPで見ているというお知らせはありがたいものでした。
今年度の新しい取り組みとしては、「国際植物の日」への参加でした。期間中に、10校近くで講義をできたのではと思っております。来年は、期間が長くなるのもあり、より多くのところに、うかがえるようにしたいと思います。
どこまでをアウトリーチ活動と呼ぶのか、難しいですが、アウトリーチ活動を取材頂き、新聞紙上にも数多く取り上げて頂きました。また、初めてでしたが、石川県でテレビ取材もうけ、ニュースにも取り上げて頂きました。さらに、ヒトのつながりのおかげで、11月には、愛媛・今治のFMラジオにも出演しました。ありがとうございました。現在、そのラジオをHPで公開できないか調整をしております。でき次第、また、お知らせします。こうした広報に近い活動かもしれないですが、愛媛新聞社様のご依頼で、今年は、1月から、5週に1度、日曜コラムの「道標」というのを書かせて頂き、次の日曜日が最終回となります。何を書けばよいのかと思った側面もありましたが、何とか、11回を無事つとめさせて頂き、現在、最終稿のゲラの校正段階になりました。ある意味、ほっとしているところです。
 こうした活動ができるのも、外に出ていてもlabを支えてくれる皆様、その間、mail, 電話での対応で了解頂いた、学生の皆さんに感謝したいと思います。ありがとうございました。次回は、教育・研究活動を少し整理したいと思います。
こうした活動ができるのも、外に出ていてもlabを支えてくれる皆様、その間、mail, 電話での対応で了解頂いた、学生の皆さんに感謝したいと思います。ありがとうございました。次回は、教育・研究活動を少し整理したいと思います。
わたなべしるす
アウトリーチ活動については、labのHPにもまとめてありますし、それぞれのプロジェクト(新学術領域研究、若手研究(S))のHPにも記してあります。細かなことは、そちらをご覧下さい。もちろん、研究室ダイアリーのところをカテゴリー別にしておりますので、出前講義、研究室訪問をclick頂ければ、新しいものから見るようになりました。これも4月からのHPの大幅更新で、見やすくなったのではと思います。
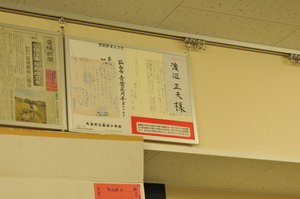 では、その中身ですが、14府県(青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島、栃木、埼玉、石川、大阪、兵庫、香川、愛媛、鹿児島)の小中高と交流できました。ダイコンコンソーシアムに参加頂いている高校も入れれば、3県(岐阜、和歌山、佐賀)、追加されます。それなりのところにうかがえたのではと思います。何より、今年、大阪、兵庫とうかがえたのも、他のSSH校での講義、交流会などでのつながりのおかげです。改めて、ヒトのつながりに感謝したいと思います。もちろん、それぞれの学校に十分なことができたところもあったかもしれないですが、体調を崩して十分な対応ができなかったこともありました。ぜひ、2013年はそうしたことのないように自己管理をしたいと思います。また、時間の調整がつかず、うかがえなかったところも多くありました。そうしたところを来年には改善して、さらには、内容も充実させ、来年もこうした活動をできればと思います。
では、その中身ですが、14府県(青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島、栃木、埼玉、石川、大阪、兵庫、香川、愛媛、鹿児島)の小中高と交流できました。ダイコンコンソーシアムに参加頂いている高校も入れれば、3県(岐阜、和歌山、佐賀)、追加されます。それなりのところにうかがえたのではと思います。何より、今年、大阪、兵庫とうかがえたのも、他のSSH校での講義、交流会などでのつながりのおかげです。改めて、ヒトのつながりに感謝したいと思います。もちろん、それぞれの学校に十分なことができたところもあったかもしれないですが、体調を崩して十分な対応ができなかったこともありました。ぜひ、2013年はそうしたことのないように自己管理をしたいと思います。また、時間の調整がつかず、うかがえなかったところも多くありました。そうしたところを来年には改善して、さらには、内容も充実させ、来年もこうした活動をできればと思います。訪問したり、見学してもらうだけでなく、その時に質問できなかったことをmailで頂いたり、人生相談のようなものだったり。そうしたものへのmailでの回答も数多くありました。また、そうした方々から、出前講義の記事をHPで見ているというお知らせはありがたいものでした。
今年度の新しい取り組みとしては、「国際植物の日」への参加でした。期間中に、10校近くで講義をできたのではと思っております。来年は、期間が長くなるのもあり、より多くのところに、うかがえるようにしたいと思います。
どこまでをアウトリーチ活動と呼ぶのか、難しいですが、アウトリーチ活動を取材頂き、新聞紙上にも数多く取り上げて頂きました。また、初めてでしたが、石川県でテレビ取材もうけ、ニュースにも取り上げて頂きました。さらに、ヒトのつながりのおかげで、11月には、愛媛・今治のFMラジオにも出演しました。ありがとうございました。現在、そのラジオをHPで公開できないか調整をしております。でき次第、また、お知らせします。こうした広報に近い活動かもしれないですが、愛媛新聞社様のご依頼で、今年は、1月から、5週に1度、日曜コラムの「道標」というのを書かせて頂き、次の日曜日が最終回となります。何を書けばよいのかと思った側面もありましたが、何とか、11回を無事つとめさせて頂き、現在、最終稿のゲラの校正段階になりました。ある意味、ほっとしているところです。
 こうした活動ができるのも、外に出ていてもlabを支えてくれる皆様、その間、mail, 電話での対応で了解頂いた、学生の皆さんに感謝したいと思います。ありがとうございました。次回は、教育・研究活動を少し整理したいと思います。
こうした活動ができるのも、外に出ていてもlabを支えてくれる皆様、その間、mail, 電話での対応で了解頂いた、学生の皆さんに感謝したいと思います。ありがとうございました。次回は、教育・研究活動を少し整理したいと思います。わたなべしるす