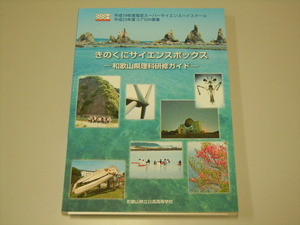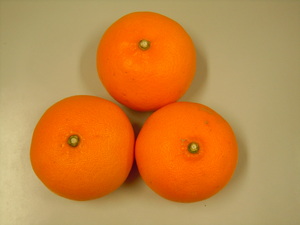子供の頃から現在でもそうであるが、何かを決めるときに、いろいろな方法があるが、じゃんけんは比較的majorな気がする。一時期、あみだくじでと言うこともあったが。。小学校の頃のじゃんけんでは、「かばんもち」なるものをやっていた。今でもやるらしいと言うのをきいたことがある。数名で負けた人がランドセルを全員のを背負って帰る。帰り道全体でなくて、電信柱何本とか。。。あと、神社の階段で、ぐーなら、「グリコ」で、3歩。ぱーは、「パイナップル」で6歩。ちょきなら、「チョコレート」で、同じく6歩。階段の先までいったら、勝ち。そんなことをして遊んでいた。今、じゃんけんをするのは、お菓子をgetするためとか。。。では、実験でじゃんけんは。。。というと、アブラナ科植物の自家不和合性は、少し難しいが、胞子体的に機能するS複対立遺伝子系で制御されていて、S対立遺伝子間に優劣性なるものが存在する。実際、今もその研究をしているのだが。。。優劣性というのは、対立遺伝子間の相互作用で、ヘテロ接合体になったとき、どちらの対立遺伝子が表現型として表に表れるかということである。3つの対立遺伝子間での関係を考えたとき、S1>S2>S3というような直線的な関係が、普通に考えられるかも知れないが、じゃんけんのように、S1>S2, S2>S3, S3>S1。ここで、「>」と言う記号は、左が右より強いと言うことを意味させる。実際のアブラナ科植物の自家不和合性のS対立遺伝子間では、直線的というのはあるが、じゃんけんと同じような複雑な関係になるのはなかったような。あったら、興味深いし、どんなメカニズムになっているのか、知りたいと思ったからである。。。ただ、もちろん、あってはいけないというか、ないのは、「後出しじゃんけん」。。。これで子供頃にずいぶんケンカになったような。。。S対立遺伝子間では、これがないのが幸いである。。。
 子供の頃といえば、ずいぶんと砂遊びというか、地面を使って遊んだ。陣地取りといったであろうか。地面に正方形を書いて、じゃんけんをして、ぐー、ちょき、ぱーの勝ったての形で、地面を確保していく。どのタイミングで終わりになったのかを思い出せない。あと、四国の地質はよくわからないが、花崗石は多かったような気がする。なので、砂というか、小さな石も多く、粘土質の粒子の小さな土は少なかったような。それを集めて、何かを作るのが、楽しみであったが、集めるのに苦労した。大きなびわの葉っぱをとってきて、その表面構造を活かして、石などを排除して、粘土質の粒子だけを集めていた。懐かしい。あと、石英ガラスというか、石であるが、それも結構あった。遠足などで、拾って、さらに透明度が高い、水晶に近いものを見つけては、自慢し合った。同じものでも結晶の形などで、ずいぶんと形がが違う。炭素が平面というか、つながったのが、黒鉛というか。鉛筆の芯というか。最近であれば、カーボンナノチューブという炭素が、60個くらい結合したものもある。一方で、ダイヤのように堅い構造体をとることもできる。何とも不思議である。ダイヤといえば、明日から、JRのダイヤ改正。今回のダイヤ改正では、東北大を受験に来た時に初めて乗った、「200系」が引退する。当時は、大宮からの始発。東京から上野まで、手線。そのあと、新幹線リレー号で大宮まで。ずいぶん、時間がかかったが、揺れなかったというイメージはあった。東海道・山陽新幹線と比べて。あれから、30年近く。ご苦労様、というべきなのであろう。
子供の頃といえば、ずいぶんと砂遊びというか、地面を使って遊んだ。陣地取りといったであろうか。地面に正方形を書いて、じゃんけんをして、ぐー、ちょき、ぱーの勝ったての形で、地面を確保していく。どのタイミングで終わりになったのかを思い出せない。あと、四国の地質はよくわからないが、花崗石は多かったような気がする。なので、砂というか、小さな石も多く、粘土質の粒子の小さな土は少なかったような。それを集めて、何かを作るのが、楽しみであったが、集めるのに苦労した。大きなびわの葉っぱをとってきて、その表面構造を活かして、石などを排除して、粘土質の粒子だけを集めていた。懐かしい。あと、石英ガラスというか、石であるが、それも結構あった。遠足などで、拾って、さらに透明度が高い、水晶に近いものを見つけては、自慢し合った。同じものでも結晶の形などで、ずいぶんと形がが違う。炭素が平面というか、つながったのが、黒鉛というか。鉛筆の芯というか。最近であれば、カーボンナノチューブという炭素が、60個くらい結合したものもある。一方で、ダイヤのように堅い構造体をとることもできる。何とも不思議である。ダイヤといえば、明日から、JRのダイヤ改正。今回のダイヤ改正では、東北大を受験に来た時に初めて乗った、「200系」が引退する。当時は、大宮からの始発。東京から上野まで、手線。そのあと、新幹線リレー号で大宮まで。ずいぶん、時間がかかったが、揺れなかったというイメージはあった。東海道・山陽新幹線と比べて。あれから、30年近く。ご苦労様、というべきなのであろう。
ダイヤ改正といえば、時刻表。仙台にきた頃は、暇な時には、仙台駅に入場券で、ホームへ。愛媛から、1,000km近くあるのだろうか。ただ、この線路の先は、つながっていて。。。とおもったら、ホームを端から端まで歩いていた。今のように入場してから、2hrという制限もなかったので。何をしていたのかは思い出さないが。。。時刻表を見ているだけで、どこかに行った気分になった。時刻表の見方を教えてもらった友達の影響もあって、毎月買っていた。出張にも必ず、JTBの時刻表を持ち歩いていた。そのうち、それと同じくらいというか、それよりも重たい、ノートパソコンを持ち歩くようになった。その頃は、もちろん、Internetなどなかった。なので、時刻表がわからないのが困って、しばらくは、両方を持っていたような気がする。若かったので、持つことができたのかもしれない。netで検索できるようになった頃からか、パターンが決まったからか、時刻表を持ち歩かなくなり、買わなくなった、最初は、消費税もなく、650円だったような。今は、込みで、1,150円。30年で、ずいぶんと値段が変わった。もちろん、中身のダイヤも進化した部分と絶滅した部分と。時間の流れ方が、昔と違う訳ないが違っていて、時刻表を見ながら、最短で、全県を回るとか、そんなことを考える時間がとれない。。。久しぶりに、時刻表を眺めてみたら、新しい発見に出会えるのではという気がした。やっぱり、アナログの方が便利というと、年なのだろうか。。。もちろん、これを書くために使っているのは、パソコン、デジタルの象徴というのが、不思議であるが。。。今年も、遠くから東北大に来る方もいるだろう。今は新幹線でなくて、飛行機なのかもしれないが。。。来年度の入学式は、4/4(木)。ずいぶんと早い。そういえば、この日に、渡辺が制作に関わったテレビが放送される。不思議なご縁かもしれない。。。
今月もあと半月というのか、今年度もあと半月というのか。あっという間だが、まだやり残したことがたくさん。。。ためないように片付けるようにすることにしよう。。。

わたなべしるす
 子供の頃といえば、ずいぶんと砂遊びというか、地面を使って遊んだ。陣地取りといったであろうか。地面に正方形を書いて、じゃんけんをして、ぐー、ちょき、ぱーの勝ったての形で、地面を確保していく。どのタイミングで終わりになったのかを思い出せない。あと、四国の地質はよくわからないが、花崗石は多かったような気がする。なので、砂というか、小さな石も多く、粘土質の粒子の小さな土は少なかったような。それを集めて、何かを作るのが、楽しみであったが、集めるのに苦労した。大きなびわの葉っぱをとってきて、その表面構造を活かして、石などを排除して、粘土質の粒子だけを集めていた。懐かしい。あと、石英ガラスというか、石であるが、それも結構あった。遠足などで、拾って、さらに透明度が高い、水晶に近いものを見つけては、自慢し合った。同じものでも結晶の形などで、ずいぶんと形がが違う。炭素が平面というか、つながったのが、黒鉛というか。鉛筆の芯というか。最近であれば、カーボンナノチューブという炭素が、60個くらい結合したものもある。一方で、ダイヤのように堅い構造体をとることもできる。何とも不思議である。ダイヤといえば、明日から、JRのダイヤ改正。今回のダイヤ改正では、東北大を受験に来た時に初めて乗った、「200系」が引退する。当時は、大宮からの始発。東京から上野まで、手線。そのあと、新幹線リレー号で大宮まで。ずいぶん、時間がかかったが、揺れなかったというイメージはあった。東海道・山陽新幹線と比べて。あれから、30年近く。ご苦労様、というべきなのであろう。
子供の頃といえば、ずいぶんと砂遊びというか、地面を使って遊んだ。陣地取りといったであろうか。地面に正方形を書いて、じゃんけんをして、ぐー、ちょき、ぱーの勝ったての形で、地面を確保していく。どのタイミングで終わりになったのかを思い出せない。あと、四国の地質はよくわからないが、花崗石は多かったような気がする。なので、砂というか、小さな石も多く、粘土質の粒子の小さな土は少なかったような。それを集めて、何かを作るのが、楽しみであったが、集めるのに苦労した。大きなびわの葉っぱをとってきて、その表面構造を活かして、石などを排除して、粘土質の粒子だけを集めていた。懐かしい。あと、石英ガラスというか、石であるが、それも結構あった。遠足などで、拾って、さらに透明度が高い、水晶に近いものを見つけては、自慢し合った。同じものでも結晶の形などで、ずいぶんと形がが違う。炭素が平面というか、つながったのが、黒鉛というか。鉛筆の芯というか。最近であれば、カーボンナノチューブという炭素が、60個くらい結合したものもある。一方で、ダイヤのように堅い構造体をとることもできる。何とも不思議である。ダイヤといえば、明日から、JRのダイヤ改正。今回のダイヤ改正では、東北大を受験に来た時に初めて乗った、「200系」が引退する。当時は、大宮からの始発。東京から上野まで、手線。そのあと、新幹線リレー号で大宮まで。ずいぶん、時間がかかったが、揺れなかったというイメージはあった。東海道・山陽新幹線と比べて。あれから、30年近く。ご苦労様、というべきなのであろう。ダイヤ改正といえば、時刻表。仙台にきた頃は、暇な時には、仙台駅に入場券で、ホームへ。愛媛から、1,000km近くあるのだろうか。ただ、この線路の先は、つながっていて。。。とおもったら、ホームを端から端まで歩いていた。今のように入場してから、2hrという制限もなかったので。何をしていたのかは思い出さないが。。。時刻表を見ているだけで、どこかに行った気分になった。時刻表の見方を教えてもらった友達の影響もあって、毎月買っていた。出張にも必ず、JTBの時刻表を持ち歩いていた。そのうち、それと同じくらいというか、それよりも重たい、ノートパソコンを持ち歩くようになった。その頃は、もちろん、Internetなどなかった。なので、時刻表がわからないのが困って、しばらくは、両方を持っていたような気がする。若かったので、持つことができたのかもしれない。netで検索できるようになった頃からか、パターンが決まったからか、時刻表を持ち歩かなくなり、買わなくなった、最初は、消費税もなく、650円だったような。今は、込みで、1,150円。30年で、ずいぶんと値段が変わった。もちろん、中身のダイヤも進化した部分と絶滅した部分と。時間の流れ方が、昔と違う訳ないが違っていて、時刻表を見ながら、最短で、全県を回るとか、そんなことを考える時間がとれない。。。久しぶりに、時刻表を眺めてみたら、新しい発見に出会えるのではという気がした。やっぱり、アナログの方が便利というと、年なのだろうか。。。もちろん、これを書くために使っているのは、パソコン、デジタルの象徴というのが、不思議であるが。。。今年も、遠くから東北大に来る方もいるだろう。今は新幹線でなくて、飛行機なのかもしれないが。。。来年度の入学式は、4/4(木)。ずいぶんと早い。そういえば、この日に、渡辺が制作に関わったテレビが放送される。不思議なご縁かもしれない。。。
今月もあと半月というのか、今年度もあと半月というのか。あっという間だが、まだやり残したことがたくさん。。。ためないように片付けるようにすることにしよう。。。

わたなべしるす